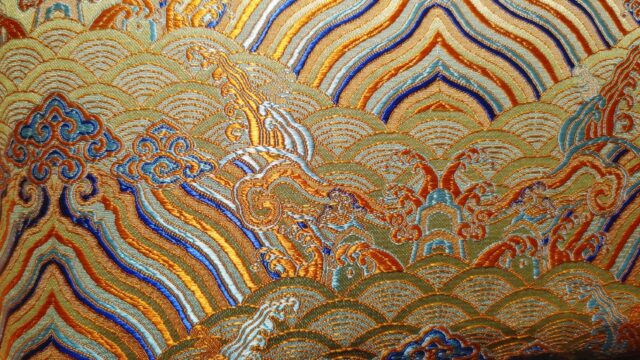「ぬぃの中国文学ノート」にご来訪ありがとうございます。
こちらの記事では、後漢の文章によくみられる作風についてかいてみたいと思います。後漢の文章って、ふだんはあまり文学として出てこないのですが、わたしは独特の渋い味わいが大好きなので、こちらで紹介していきます。
ちょっと話が脱線してますが、だいたい後漢あたりから四文字でひとつの句になって、それを並べるようにして書いていくスタイルが主流になっていきます。それをさらに対句で埋めていくと、六朝時代の駢文(対句の多い装飾的文体)になっていく――みたいになります。
というわけで、いよいよ後漢の文章についてみていきます。
天地の産物
まず、後漢らしいなぁ……と思うのは、「この世の人間や自然などは、すべて天地の霊気を受けて生まれている」という感性が、いつも流れていることです。
天地の間を流れている霊気みたいなものは、あるときは人間のつくったものに現れたり、あるときは自然の山川などに湧いていたりします。
魯の霊光殿は、前漢が一度衰えたときに、盗賊があちこち出て、長安の未央宮・建章宮などはいずれも燃えたり壊れてしまったときに、この霊光殿だけはぎらぎらと一人残っていて、これはきっと天地の神が護っており漢の王家を支えていたのだろう。その姿をみれば、やはり天の星々と重なるように造られており、それも永く残ってきた理由なのだろう。
わたしは南方の田舎から、この魯に伎芸を習いにきて、この霊光殿をみて「あぁ、詩人の想いは、物をみて生まれてくるというが、今日のようなときに、古き世の功績は字の中に残り、德を含んだ音も詩の響きになるのだろう。良き物を並べ立てて描き、良き事を讃えるようにして書くというが、そのような文章がなくては、きっとこの想いも残せないのだろう……。」
魯霊光殿者、……遭漢中微、盗賊奔突、自西京未央建章之殿、皆見隳壊、而霊光巋然獨存。意者豈非神明依憑支持以保漢室者也。然其規矩制度、上應星宿、亦所以永安也。予客自南鄙、観蓺於魯、睹斯而眙曰「嗟乎。詩人之興、感物而作。故……功績存乎辞、德音昭乎声。物以賦顕、事以頌宣、匪賦匪頌、将何述焉。」(王延寿「魯霊光殿賦」)
こちらは、魯(山東省の内陸のほう)にあった霊光殿という、きらきらと飾られた宮室のことをかいています。
とくに後漢らしいのは、「きっと天地の神が護っており漢の王家を支えていた(意者豈非神明依憑支持以保漢室者也)」「天の星々と重なるように造られており、それも永く残ってきた理由なのだろう(其規矩制度、上應星宿、亦所以永安也)」です。
こんなふうに、天地の神々のふしぎな気を浴びて、この世界はできている――という感性が後漢のものには、すごくよく出てきます。
あと、後漢の作品って、すごく質感重視の表現がでてきます。たとえば、こちらでは「德を含んだ音も詩の響きになる(德音昭乎声)」の「徳音」って、かなり無理な結びつきじゃないですか……(徳を含んだ音って、どんな音かは謎だけど、雰囲気はすごく出ている――みたいな)
こういうふうに、ちょっと無理のある字の結びつきで、天地の間をもやもやと流れる生気・霊気を伝えるような表現が、すごく後漢の文章には多いのです。
淮水を祭る
つづいては、淮水(黄河と長江のあいだにある大きい川)を祭る様子をかいている碑文です。いかにも後漢にありがちな味わいが魅力的です(笑)
しずやかに流れる淮水は、古くは禹王が整えた水――。さらさらと行きて、海まで下っていく。穢れをながして遠くまで運び、穏やかにして柔らかく、ひっそりとして深き力を湛えて、やさしくしてときに激しく沈みけり……。実に四つの大きい川として、黄河と並ぶ貴き川。
つつしみて祀れば、その川の德に背かず。それでいて、近き世にはその祭りの廃れて、心して行われず。災いも起こりて、陰陽も乱れれば、あの廟(社)のある岡にのぼりて、この廟のそばに至りて、つつしみて敬えば、神霊も福を降せり。ゆったりとなごやかにして、民も悦び従い、そよそよとして楽しく、その年の米も豊かにして……。
泫泫淮源、聖禹所導。湯湯其逝、惟海是造。疏穢済遠、柔順其道。弱而能強、仁而能武。……実為四瀆、与河合矩。……虔恭礼祀、不愆其德。惟前廃弛、匪躬匪力。災眚以興、陰陽以忒。陟彼高岡、臻兹廟側。肅肅其敬、霊祗降福。雍雍其和、民用悦服。穣穣其慶、年穀豊殖。(「桐柏淮源廟碑」)
こちらも、淮水が「古くは禹王が整えた水」というように、どこかで禹(古い時代の聖王)のころの霊気みたいなものを少し含んでいるような――みたいな感じになっています。
さらに「さらさらと行きて、海まで下っていく(湯湯其逝、惟海是造)」だったり、「ひっそりとして深き力を湛えて、やさしくしてときに激しく沈み……(弱而能強、仁而能武)」みたいに、どこかで形のない不思議で永遠なものとつながっているような――という雰囲気もあります。
ばらばらにみえるけど、実はどこかで形のない生気・霊気みたいなものがきっとこの世にはたくさん流れていて、人間も自然もきっとその一つなのだろう……というのが、やはり後漢っぽいです。
あと、「泫」って、玄(黒い)の水verなのですが、どろどろとやや深みを湛えながら重く流れていく淮水の様子が、いかにも「穢れをながして遠くまで運びつつ、ひっそりとして深き力を湛えている(疏穢済遠、……弱而能強)」みたいにみえます。
こんなふうに、後漢の質感重視の字は、じつはこの世界の裏にある生気がわずかにのぞいている感じを描いているのが、すごく魅力的です。あと、実はこういう碑文って、文学よりも書として有名だったりして、固いような粘り気のあるような書体がすごくかわいいです。

(ちなみに、全てではないですが、四文字ずつでセットになるときに、一文字だけ意味が薄い字が入っていることが後漢の文章では多いです。ここでは「其」「而」「所」など)
ばらばらなのに、どこかでつながっているような
最後は、墓碑銘(お墓に刻まれる碑文)です。
袁満来は、流れ出る才と美しき姿にして、これは天の授けたもので、その識は深くその想いは馳せる如く、もろもろの心を兼ね備えて、話していれば泉の乱れなく涌き出て、しかも詰まることもないような心地がして、名族の宝物、国家の支えになるはずだった。
その人柄は、たとえ幼い者でも、その高い香りを感じているほどだったのに、その生は永からずして、年はわずか十五にして、病に遭いて亡くなり、既に美しき苗に似て穂は出でず、その花を枯らして落ちていき、あぁ悲しくして収まらず。ゆえにわずかに碑を立てて、これを墓表に刻みて、それでもなお悲しみは止まずして、ただ悲しむのみ。
袁満来、……逸才淑姿、実天所授。聡遠通敏、……情性周備。……無決泉達、無所凝滞。……允公族之殊異、国家之輔佐。……雖則童稚、令聞芬芳、降生不永、年十有五、……遭疾而卒。既苗而不穂、凋殞華英、嗚呼悲夫。乃假碑、旌于墓表、嗟其傷矣。惟以告哀。(蔡邕「袁満来碑銘」)
こちらは、後漢の終わりごろの蔡邕(さいよう)という人がつくったものなのですが、蔡邕は墓碑銘がすごく得意でした。
こちらも「流れ出る才と美しき姿は、天の授けたもの(逸才淑姿、実天所授)」というのが、やはり天地の生気を吸って人間も生きている――という感覚になっています。
もっとも、こちらも作品がすごく味わい深いのは「その高い香りを感じているほどだったのに、既に美しき苗に似て穂は出でず、その花を枯らして落ちていき――(令聞芬芳……既苗而不穂、凋殞華英)」のような、花の様子に喩えているところです。
天地の生気が、あるときは豊かに美しく咲いて、あるときは悲しく萎れていく様子が、人間の世界にも重ねられていて、この世界にはただ永遠な生気の漂い流れていく様子だけがあって、ひとときばかりのうちに生まれて生きていくだけなのかもしれないけど、やはりどこかで果てしない天地とつながっているような――みたいな分かれているけど裏でつながっている感性が、後漢っぽいなぁ……とか私は思っています♪
なので、後漢の文章って、表向きはすごく乾いていて、どこか殺風景な感じもあるのに、なんともいえない潤いがどこかに滲んでいて、他の時代にはない魅力になっています。
というわけで、ふだんはあまり語られない後漢の作品の味わいについて、私なりに感じていることを書いてみました。もはやほとんど私の好みを語っているだけの記事になってしまいましたが、少しでもその魅力が伝わっていたら嬉しいです。
お読みいただきありがとうございました。