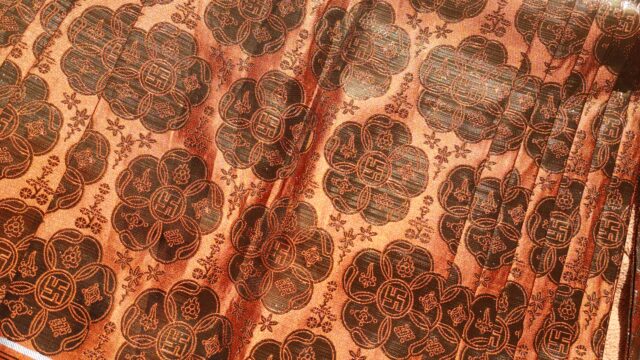「ぬぃの中国文学ノート」にご来訪ありがとうございます。
こちらの記事では、中国の擬態語についてかいてみたいと思います。これを感じられるようになると、中国の詩がさらに深く味わえるので、ぜひみていただけると嬉しいです。
どうでもいいけど、わたしが中国文学に惹かれたきっかけは、こちらの「擬態語が美しい……」というのがすごく大きかったです(ちなみに、擬態語は「もこもこ」「するする」etc)
というわけで、さっそく、本題に入っていきます。
中国の擬態語
中国の擬態語は、子音が同じもの(双声)・母音が同じもの(畳韻)・同じ字をかさねたもの(重言)があります。
もっとも自然な形は、同じ字をかさねている「重言」です。たとえば、「蕭蕭(しょうしょう)」は、さらさらと葦が鳴るような、ちょっともの寂しい雰囲気のことになります。
その双声verが「蕭索」、畳韻verが「蕭條」になります(意味はだいたい同じですが、響きがすこし異なります)
さらに「索索」というと、さらさらと乾いてもの寂しい様子になっていて、「瀟瀟」というと、葦にひんやりと雨が降っていて濡れている感もあります。こんなふうに、擬態語は互いにどこまでも派生していくのです♪
もうひとつ、「依依」というのがあります。やわらかい柳のゆれている様子などを“依依”というのですが、それが道のうねうねとつづいている様子になると「逶逶(いい)」になります。
さらに「逶逶」と似ているものには「迤迤(いい)」「迤邐(いり)」もあります。だいたい意味は一緒です。
さらに「逶逶」系は、どちらかというと細くうねうねしていることに重みがありましたが、より曲がっていることに重みがあるときは「蜿蜿」「蜒蜒」(どちらも「えんえん」)があります。
こちらの蜿蜿系も「蜿蜒」「蜿蟺(えんせん)」みたいに派生して、ちょっと水っぽいところを這っているときは「灗灗(せんせん)」、カワニナのように曲がっているときは「蜿蜷(えんけん)」みたいになります。
もっとも、「蜿蜷」までくると、もはやくるんと丸まっている様子に重みがあるので「連蜷」「蜷曲」「屈曲」「回曲」などが近いものになっていきます。
しかも、くるんと丸い中でも、「屈曲」「回曲」などはk行のどこか硬い音になっていて、固いものが複雑にごちゃごちゃと絡みあっている様子も入っているので「奇怪」だったり(複雑怪奇みたいな)、それが木でつくられていると「機械」になります。
さらに硬いものの内側がからんと広いときは「廓落(かくらく)」、その廓落が山っぽくなっていると「崆巃(こうろう。からんと空洞になっているような山)」、そんな感じの仙山を「崑崙(こんろん)」、そんなふうなヒョウタンを「葫蘆(ころ)」といいます。
ちなみに、「崆」がもっと細く痩せているときは「崎嶇(きく)」「崎嶔(ききん)」「崎嶬(きぎ)」みたいになります。すごく面白くないですか(笑)
詩の韻律
つづいては、詩の韻律美(音の美しさ)についてです。
これは中国の作品でも日本の作品でも、だいたい同じようになっているので、わかりやすいように日本の例をみていきます。
この韻律美をすごく活かしているのは、江戸時代の俳人 与謝蕪村です。蕪村の句は、どれも音のもっているイメージが、風景ときれいに重なるようにつくられているのが魅力です。
さみだれや大河を前に家二軒
こちらは、すごくわかりやすい例です。まず、最初の「さみだれや大河を前に」は、濁音とaがかなり多く入っていて、ごぼごぼと膨らんだ大きい川がみえてくるような音です。
ですが、そのあとの「家二軒」は、i・eの小さく細い音になっていて、大きい川の前にぽつんとある小さい家ふたつ――みたいな感じがしてきませんか。
もうひとつ、ちょっとマイナーな例もいきます。
春雨や小磯の小貝ぬるるほど
こちらは、「小磯の小貝」があえて固い響きになっていますが、その前後には「春雨・ぬるる」みたいに、ぼんやりと柔らかい音がならんでいます。これが、ぼんやりとほの暗い春雨の中で、黒々と固い磯の石が、しっとり濡れている雰囲気になっています。
甲斐ヶ嶺や穂蓼の上を塩車
こちらはちょっと複雑です。まず「甲斐ヶ嶺(かいがね)」はk・gがあって、しかもaも多くて、大きくてごつごつと広がっている嶺の様子がありますが、そのあとの「穂蓼(ほたで)」がちょっとほこほことやわらかいです。
この組みあわせが、ごつごつと大きい嶺の上に、すこしほわほわと咲いている蓼の花みたいな印象になります(こういう技巧、すごく好きです……)。「塩車」にあえてaを入れないのも、塩車の小ささが出ていておしゃれです。
水仙や寒き都のここかしこ
これはわかりやすいです。まず、全体がさらさらきしきしして、わずかに雪のつもったような雰囲気になっています。「水仙や寒き」のs多めなところも綺麗です。
あと、終わりのほうにあえて「ここかしこ」みたいに、すこしガタガタした音が入るのも、都のいくらか段差があって、そんな中に水仙が咲いている感があったりしませんか……。
まぁ、そんなわけで、蕪村の例ばかり出してしまいましたが、中国の詩でも、だいたい同じような感じで、漢字の音を擬態語っぽくみてみると、風景などときれいに重なっていることがあって、すごく魅力が感じられます。
あまり中国文学について、詩の響きを味わう――みたいなことって紹介されないので、あえてかいてみました。少しでも鑑賞の参考になっていたら嬉しいです。
お読みいただきありがとうございました。