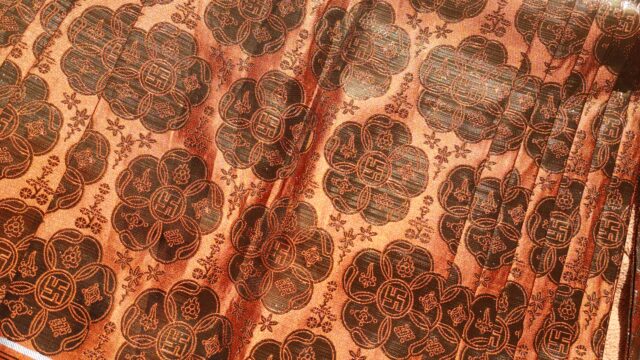「ぬぃの中国文学ノート」にご来訪ありがとうございます。
実は、わたしは、すごく気が向いたときに、ごくまれに漢詩などをつくることがあります(まぁ、本音を云ってしまうと、それほど熱心ではない笑)でも、たぶん一生発表する機会がないので、とりあえずここにのせておきます。
あと、記事のタイトルに「随時更新」なんて入っていますが、いつ追加するのか未定です……。
玉樹
玉樹瓊柯路、清笙靄靄帰。紗光湿昼積、綺冰翻夕霏。
玉色の木の白い枝ばかり――、清い笙は何処かでほんのりと聞こえるのでした。紗の光は昼に湿って積もり、きらきらとした冰は夕べに咲いて散りました。
こちらは雪が降ったときに、家の近くの梅林をなんとなく想像してつくったものです(実際にはみていない笑)
前半の二句は、ちょっと南宋っぽい感じで、後半の二句はかなり六朝後期っぽい雰囲気にできているのが気に入ってます。
昔游詩 其二
珊珊連璐水、靡靡湧千琅。瓊樹蔭古階、繍甍雲暗霜。璨璨白灘褙、琳琳青瀾裳。既游霊女宅、更観其汩揚。錦襞縈翠室、素素戯清房。
珊々(さらさら)として璐(玉)を浮かべた水、ひらひらとして千の白玉を涌かせて、にぶい耀きの樹々は古い階に翳りて、あでやかな甍(瓦)は雲が霜を蔽うのに映えて、きらきらと白い瀾のごとき衣と、ちらちらと青く沈んだ裳をまとう神――。
既に霊女の宮に遊びて、さらにその沸く波をみれば、錦の襞のごとく冬の翠はめぐりて、さらさらと清房にいる心地がするのでした。
こちらは、石川県の白山比咩神社のことをかいています。もはや題名からして、南宋の姜夔をすごく真似しています……(作風も真似しているけど)あの不思議な翳りのある雰囲気は、いかにも日本海側っぽくて大好きでした。
あと、わたしの詩は、かなり漢賦の癖が入っていて、字に悩むと擬態語で済ませる癖がついています(笑)
昔游詩 其三
緬曠尾瀬原、百草紛瑟瑟。碧綺敷蘭水、青琱披錦色。行行灘浦續、迤迤澄泥湿。徙倚顧青塘、彷徨臨岸側。杳然霈雨至、龍魚喜洄潏。淟濁如結轖、羅鱗兮媚嫉。涸沼連無倪、湛湛盈淵室。穿薄畏霄霆、褰裳蹈川礫。川澌流復聚、潭潭八溟凓。
ぬるぬるとつづく尾瀬ヶ原――、百草はひらひらさらさらと艶やかにして、碧の絹のごとくして蘭水を敷いて、青い玉は錦の色にも似ているのでした。行き行きて浦の色はつづき、うねうねとして澄んだ泥は湿っていて、少し行きては青い塘(池)をふりかえり、うろうろと岸のそばに居るのでした。
たちまちにしてどろどろと黒い雨雲が涌いて、龍や魚たちはその溢れめぐる流れを喜び、どろどろと濁った流れは筵の如く絡みあい、鱗を並べてきらきらと踊るように舞いますので、涸れた沼たちものよのよと果てもなく繋がりあい、さらさらするすると淵の底を盈していきます。
木々の間をぬけて鳴る雷霆を恐れ、そろそろと隠れる如くして川の礫(石)を踏んでいけば、川は溢れ満ちて流れ聚まり、淵ごとにして八方の水は冷ややかなのでした――。
こちらは、尾瀬(群馬の北のほうの湿原)に行ったときに、死にかけた話をもとにした詩です。
夏の尾瀬は、午後になると雷が来るとはいわれていましたが、午後二時くらいから急に暗くなって、まわりに隠れるものがないときに雷が鳴り始めて、もはやここで雷に焼かれて死ぬことを覚悟しました(笑)
まぁ、なんとか無事だったのですが、そのときの夏の尾瀬は、午前中はやや乾いていて水も少なかったのに、雨がふると小さな淵どうしが互いにつながりあって低いほうに流れていき、その水はしだいに大きく膨らんでいく様子がすごかったです……。
あと、尾瀬の下のほうには淵どうしがつながっている穴があって、複雑な迷路のようになっている――というのを、昔みたことがあったので、詩の中の「淵室」はそれのことです。
詩のスタイルは、晩清の王闓運にのめり込んでいた時期なので、もはやコピーみたいになっています。好きな句は「碧綺敷蘭水・魚龍喜洄潏・涸沼連無倪」あたりですかね(かなり古色もあって、いい句が多いのも嬉しかったです♪)
昔游詩 其四
兀兀二荒山、霊蛇亘族峰。眇莽復漫漫、巨蚣赤城墉。樺榅蓊鬱鬱、湫壑夏洪洪。一日何隤圮、相噬牙為蜂。身戴檜與蘿、其血赤洶洶。土苔忽傾覆、緑蘚碎巃嵷。齧肉且縈骨、毒燎繞上衝。蚣痿灗灗去、奔遯爍泉中。泉滌淫淹瘴、百足奮窿窿。震石起超騰、連黝理如虹。躨跜遶澗勢、剋捷爛烘烘。粤若天衢降、燡燡瑰明豊。
ごつごつと高い二荒山、霊蛇は幾つもの峰にからんでいて、ぼやぼやとしてのろのろと延びて、大きな蜈蚣(ムカデ)も赤城の山々に住んでいる。樺や杉は鬱々として暗く、深い湖は夏でもひんやりと澄んでおり、一日にして天は崩れ傾き、ふたつの神々は噛みつき合って牙は毒を帯びる。
その身は老いた檜やまとう草を帯び、その血は赤々として流れ出し、土や苔はがたがたと傾き覆り、緑の蘚(苔)も割れてごろごろと落ちて、肉を齧りて骨を締めあい、毒は焼くごとくして身体をめぐり突いていく。
蜈蚣の神はしびれてがたがたと這って去り、ほわほわと湯気をあげている泉の中に逃げていく。泉に入りて身に溜まった毒も溶けだして、百の足はさらにつやつやと耀き、石を震わせて高く首をもたげて、青黒い殻もぎらぎらと濡れて虹の如く、うねうねとして傾いた澗(谷)にまといつけば、巨蛇を迎え撃ちてその姿は灼ける如し――。
どうやら天の衢(路)はこの泉にも下りてきていて、赤々として此の泉から溢れ出ているらしい。
こちらは、群馬県の老神温泉にいったときのことです。もともと、赤城山のムカデの神と、二荒山(日光)の蛇の神が争って、傷をうけたムカデの神が、ここの老神温泉で傷を癒して、ふたたび日光の蛇の神と戦って追いかえした……という伝承をもとにしています。
なんていうか、いかにも古代的な荒唐無稽な話ですよね(笑)
あと、「身戴檜與蘿、其血赤洶洶(身は老いた檜やまとう草を帯び、その血は赤々として流れて……)」は、実は八岐大蛇の「その身には苔や檜・杉が生えていて、その腹をみればつねに血が爛れ流れている……」をもとにしています。
というわけで、すごく自己満足の記事になりましたが、ここまでお読みいただきありがとうございました。