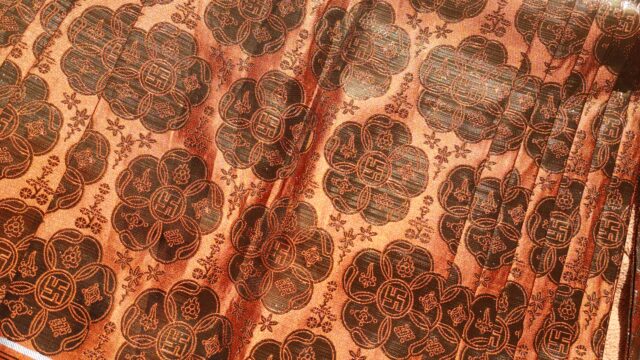「ぬぃの中国文学ノート」にご来訪ありがとうございます。
こちらの記事では、中国の詩の様式(絶句・律詩など)と、その内容についてかいていきます。
もっとも、律詩は八句で、絶句は四句だよね……ということは、なんとなく知っている方も多いとおもいますが、実はそれぞれの様式で“どのような想いを描くのか、どのような雰囲気が似合うのか”というのもあります。
なので、こちらの記事では、それぞれの詩の様式ごとに、似合いやすい雰囲気などをみていきます。あと、「平仄(ひょうそく)」というものについても紹介していきます(平仄は、漢字の音の並べ方のことです。平仄が整っていないものを「古詩」といいます)
というわけで、さっそくいってみます。
五言詩
まずは、一句が五文字の「五言詩」です。五言詩は、どこか古風で上品な含みがあって、すごくかわいいです。
五言古詩
まずは、長さが不規則で、平仄が整っていない五言古詩です。
こちらは、後漢~六朝のときのスタイルなので、後漢っぽく古めかしく素朴で、六朝っぽく貴族的な上品さをおびていて優美な味わいがあります。
ちなみに、もともと後漢の民謡(楽府)から生まれたので、民間の生活っぽいものはとくに「楽府体」といいます。ここでは、楽府らしいものをひとついきます。
秋の水はすんなりと澄んで、越の女性はするするとその水に映るのですが、小舟にて蓮の実をつめば、ひらひらと小さな袖がゆれました。落ちる花は宝玉の珥(耳かざり)を流すようで、わずかな風は冠の纓(紐)をやさしくゆらすのですが、舟から垂れた帯が湿り、小さく漕げば櫂は軽いのでした。
風に乗ってわずかにどこかの話声が聞えるような――、波にふくまれてちょっと憂いが洩れるような。きらきらとした紐を結んだ舟は、薄闇の中で葦の蔭に隠れていきました。
秋江見底清、越女復傾城。方舟共采摘、最得可憐名。落花流宝珥、微吹動香纓。帯垂連理湿、棹挙木蘭軽。順風傳細語、因波寄遠情。誰能結錦纜、薄暮隠長汀。(北斉・盧思道「棹歌行」)
民間の生活っぽいところもあって、しかも優美な雰囲気もあるのが、すごく五言古詩らしいです。
わたしが好きなのは「波にふくまれて憂いの洩れるような……(因波寄遠情)」みたいな、あえてぼんやりと婉曲にしてある句です。くねくねと揺れているのに、思っていることがもったり籠って書ききれない――というのが、とても上品な余韻なのです。
五言絶句
つづいては、五言絶句です(ちなみに、平仄が整っていない絶句を「古絶」といいます)
ひとりの客は春の夕暮れをみて、昔のつながりを思い出して手紙を書きました。海の果てには人もさびしく思いやすくて、その手紙は洛陽についたでしょうか。
孤客逢春暮、緘情寄舊遊。海隅人使遠、書到洛陽秋。(唐・韋応物「答李澣三首 其一」)
この様式は、六朝前期の長江あたりの民謡から生まれています。なので、どこか湿った雰囲気があって、ちょっとだけ官能的な味わいが込められているのが、いい作品に多いとおもいます。
上にあげた作品も、「春の夕暮れ(春暮)」「海の近く(海隅)」みたいな、どこかあでやかな風景が、ぼんやりと遠目で描かれているのが、しっとり湿っていてなんとなく官能的です。でも、それをつやつやと描きすぎるより、わずかに少しのぞいた感じにするのが、五言絶句の魅力です。

五言律詩
五言律詩は、もともと南斉(六朝の中期)あたりに、官人の贈答として宴席などでつくられるようになったスタイルです。なので、五言詩のなかでは、かなり“きちんと感”を大事にしています。
蓬莱の隠れ住む人は、岩穴にてぼんやりと草が垂れ下がり、雲が流れ帰ると仙水の井は暗く、霧が晴れると石の橋は通じている。影は峰に鳴く鶴を帯びて、身は風雨の雑じるのに任せ、師を尋ねて路に迷わず、飛ぶ鴻に乗って去っていくのでした。
蓬莱遁羽客、岩穴轉蒙籠。雲帰仙井暗、霧解石橋通。影帯臨峰鶴、形随雑雨風。尋師不失路、咸欲馭飛鴻。(陳・張正見「賦得山卦名詩」)
こちらの作品では、「雲帰仙井暗、霧解石橋通」「影帯臨峰鶴、形随雑雨風」が、どちらも対句になっています。
律詩では、いつも真ん中にふたつの対句があるので、最後の二句で短くまとめる――みたいな形式になります。この「ほどよい長さで描写を入れて(ふたつの対句)、その後に一言で結ぶ(最後の二句)」という流れが、律詩のきちんと整えられている感じになります。
これが、“五言絶句ほどぼんやりしてないけど、五言古詩ほど長くくねくねしない”みたいな、ほどよい感じになります。
ちなみに、ふつうの律詩は対句がふたつだけですが、もっと多くの対句が並べられているものを「排律」といいます(排は並べる)。逆に、八句でも対句が整っていないときは古詩になります。
あと、六朝後期あたりでは平仄がどこか崩れている“律詩っぽい古詩”みたいなのもあります(完全な五言律詩は、唐の初期に出てきます)
七言詩
七言詩は、賦のエンディング部分から生まれてきたものです(たぶん)
なので、きらきらぎらぎらと飾り立てられて人工的な趣きが入っているのが、いい作品に多いとおもいます。
七言古詩
七言詩も、もともとは長さが不規則な「七言古詩」だけでした。
ちなみに、六朝後期あたりに多くつくられたのですが、その頃の七言古詩は、楽府(漢代の民謡。「○歌行」「○○行」という題が多い)に似ていることを書いていたので「七言歌行」ということもあります。七言歌行は、「生きることの悲しみ」をぎらぎらと吐いています。
寒風がさらさらと切るごとくして白い霜を散らす頃、蒼い鷹は高く飛びて朝の光に映えるのでした。雲を割って霧を裂き虹を縫っていくようで、きらきらと細い光は雷が丘をかすめる如く、からりと翮(羽)は荊の隙間に入り、狐兔などを攫って空に帰っていくのです。
その爪は深く刺さって百鳥たちも逃げていき、ひとり飛びては四方に馳せて激しく舞うばかりでしたが、あるとき煮るような暑さがきて、毛羽もやぶれてみずから隠れるしかなくなり、草の中にひそんでは狸鼠の害を恐れ、一夕のうちにたびたび見まわしては驚き怖れるばかりなのです。
あぁ、願わくは再び澄んだ秋風に舞いて、萬里の彼方へ立って雲の間に戻りたいのです。
淒風淅瀝飛厳霜、蒼鷹上撃翻曙光。雲披霧裂虹蜺断、霹靂掣電捎平岡。砉然勁翮翦荆棘、下攫狐兔騰蒼茫。爪毛吻血百鳥逝、獨立四顧時激昂。炎風溽暑忽然至、羽翼脱落自摧蔵。草中狸鼠足為患、一夕十顧驚且傷。但願清商復為假、拔去萬里雲間翔。(唐・柳宗元「籠鷹詞」)
この死生興廃が幾重にも重なっているのを、ぎらぎらと飾られた字で詠んでいくのが「七言歌行(七言古詩)」らしさになります。
あと、「雲披霧裂虹蜺断(雲は散って霧は裂かれ、虹も断たれるごとく)」「霹靂が雷を馳せるように(霹靂掣電)」みたいな句って、かなり賦みたいな詰め込み感です。ぎらぎらと装飾的な描写があると綺麗なので、七言歌行は賦らしい句がかなり入っています。
(まぁ、明清くらいになると七言歌行と七言古詩は別物……という人も多いのですが、もともとは七言歌行的なものしか無かったので、一緒だとわたしはおもいます笑)

七言絶句
こちらの七言絶句は、隋~唐の初期あたりの民謡から生まれています。なので、五言絶句よりもさらに細かくて日常的なことを、さらっと写したような名品が多いです。
木の先にはぼんやりと小霧をおびた家があり、あでやかな堂は水に臨んでさらに澄んで、ここを過ぎるのは初めてだったのに、塔からみてみれば秋の雲がわたしのために溜まっておりました。
木末誰家縹緲亭、画堂臨水更虚明。経過此処無相識、塔下秋雲為我生。(南宋・姜夔「過徳清二首 其一」)
このちょっとした出来事や思ったことなどを、さらさらと短く書いたようなのが七言絶句らしさです(どんな内容でも可なのも魅力的です)
七言律詩
こちらの七言律詩は、中国の詩の中でも、もっとも人工的な趣きがあります(なんとなくです)
もともとは五言律詩の平仄のルールがまとめられた後に、700年代前半(唐の玄宗のころ)になって、七言でも律詩をつくってみる――ということで、平仄のルールが整えられていったものです。なので、ここまでみてきた中で、もっとも新しい様式になります。
さらさらと淡い雲月は軒にわずかにかかったような、そよそよと薄い天河は半ば山に沈んだような――、でも魚の鎖飾りはまだ垂れていて清夜も長く、鳳の如き簫の音もゆらゆらと山霧の翠に漂いました。
冷たい風はひんやりと刺して琴の柱を割るようで、香りの籠った霧はぼんやりと青くして高い髻鬟(結った髪)にまとうのでした。こちらの上官は鼓楽を好む方なので、城内の人たちはみな祭儀の明かりを眺めてから帰るのでした。
娟娟雲月稍侵軒、瀲瀲星河半隠山。魚鑰未収清夜永、鳳簫猶在翠微間。淒風瑟縮経絃柱、香霧淒迷著髻鬟。共喜使君能鼓楽、萬人争看火城還。(北宋・蘇軾「與述古自有美堂乗月夜帰」)
すごくきらきらとしていておしゃれです。七言律詩は、どちらかというと技巧が入っていて流麗な趣きになっているものが好まれている気がします。
あと、描かれる風俗も、どこか洗練された趣きにしていくとすごく似合います。
賦
さらに、中国では「賦(ふ)」という様式もありました。こちらの賦は、多くは四文字or騒体(楚辞ふう)のふたつの様式がまざっています。
あの霊光殿をみてみれば、その姿はぎちぎちがたがたと山の如く、ぎりぎりがくがくと切り立っていて、なんとも人を驚かせる様子になっている。そのするするとろとろと崩れる如く、はらはらひらひらと溢れるごとく、ぼんやりと薄暗くてがたがたごろごろと絡みあってつづいていく。
きりきりと峰の如く立っていて低く溜まっているところもあり、ぐちゅぐちゅと捩れ固まって雲を帯びているようで、もったりごつごつとしてどろどろと凝って、さらさらきらきらとして龍の鱗の綾を重ねた如く、ぼこぼこがらがらとして煌きを含み、赤々と練られる色の地を照らす如く大きいのでした。
瞻彼霊光之為状也、則嵯峨㠑嵬、峞巍㠥磈。吁、可畏乎其駭人也。迢嶢倜儻、豊麗博敞、洞轇轕乎其無垠也。……屹山峙以紆鬱、隆崛岉乎青雲。鬱坱圠以嶒𡵓、崱繒綾而龍鱗。汨磑磑以璀璨、赫燡燡而爥坤。(後漢・王延寿「魯霊光殿賦」)
四言
まずは、一句が四文字のところです。もともと中国の文章は、なんとなく収まりがいいという理由で、「四文字でひとつ」になりやすいのです。なので、もっとも自然な句形が、こちらの四言です。
四言詩は、先秦のころに多かったのですが、それ以降にも賦に入っていたり、ふつうの文章も四言になったりするので、たぶん最も有名な様式になります。こちらは、安定感があってぎっちり詰まっているような重厚さが魅力です。
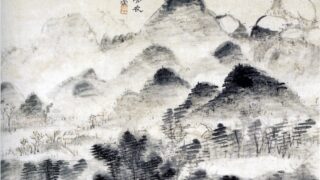
あと、分け方はほとんどの場合は「嵯峨/㠑嵬」みたいに、前後で分かれます(真ん中の二字がつながることは滅多にないです)
騒体
こちらの「騒体」というのは、楚辞(騒ともいう)の「○○○兮○○」みたいな形になっているものです。
兮は「~(語尾の伸び)」「♪」みたいなもので、あまり意味はありません。こんなふうに、句の真ん中あたりに、あまり意味のない字を入れるのが騒体になります。
さっきの例だと「邈希世而特出」「屹山峙以紆鬱」の「而・以」などが、あまり意味のない字になっています。こちらの様式は、かなり一句の字数が多いので、複雑な内容もぐにゅぐにゅと詰め込めて、しかも「而(~して……)」「乎(~で……する)」「其(~して、それは……でした)」みたいに、真ん中に入れる字によって、句の意味がかなり変わります。
あと、たまに「丹柱歙赩而電烻」「虯龍騰驤以蜿蟺」みたいに、わずかに形が変わることもあります(いずれも王延寿「魯霊光殿賦」より。五言・七言も入ることがありますが、基本は四言・騒体になります)
平仄
というわけで、ようやく平仄です。
中国では、漢字の音を“平声(平らな声)・仄声(傾いている声)”にわけています。
平声は、現代中国語の一声・二声のことで、高くて平らな響きです。仄声は、上声・去声・入声をあわせています。
上声は、現代中国語の三声で、語尾が上がっているように聞こえます。去声は、現代中国語の四声で、語尾がするりと消えるように下がっていきます。入声は、現代中国語には無くなっていますが、日本語では残っていて「白・積・室」などの詰まったような音です。
そして、平仄の並びをルール化していくのは、六朝の南斉くらいからです。そのときの基本ルールはこんな感じです。
さきに平声があれば、あとには仄声を置いて、ふたつの句でも、平声・仄声が入れかわるようになっていて、全体としても異なる響きがつぎつぎ出てくるのがいい。
若前有浮声、則後須切響。一簡之内、音韻尽殊。両句之中、軽重悉異。(『宋書』巻六十七 謝霊運伝)
まず、一句の中でも“さきに平声があれば、あとには仄声を置く”ので、平声:○、仄声:●であらわすと、四言の句では「○○●●」みたいに二字ずつでみていきます(とくに大事なのは、二・四字めです。それ以外はちょっと崩れていても大丈夫だったりします)
そして、ふたつの句でも、平声・仄声が入れかわるので、さっきの例だと「○○●●、●●○○」みたいになります。
さらに、全体としても異なる響きがつぎつぎ出てくるのが理想なので、さっきの例では、「○○●●、●●○○。●●○○、○○●●」みたいになります(大きく二句ずつセットでみていくと、最初の二句は「平仄仄平」、つぎの二句は「仄平平仄」みたいになります)
これをさらにつづけていくと「○○●●、●●○○。●●○○、○○●●。●●○○、○○●●。○○●●、●●○○」みたいになります。
こんなふうにして、五言詩:二・四字め、七言詩:二・四・六字め重視――みたいになります。
賦では、四言:二・四字め(上に書いた例です)、騒体:「邈希世而特出」の「世・出」みたいにあまり意味のない字の直前と句のおわり――というふうになります(賦から派生している駢文も同じです)
まぁ、これ以外にもかなり色々複雑なルールはあるのですが、わたしは六朝末期が好きなので、平仄はちょっと未整理なほうがおしゃれだと思っているのですが……(笑)
どうでもいいけど、古詩をつくるときは、あえて平仄が崩れている句が多いようにつくることが多いです。なので、いざとなったら「これは古詩です(律詩っぽい古詩です)」みたいな感じで通せば大丈夫です。
というわけで、いろいろな詩の様式について、すごく大まかにではありますが、その由来とあわせて解説してみました。平仄は、まぁ気になる方は他のところで調べてみてください(人任せ……)
かなり内容が詰まり気味になってしまいましたが、ここまでお読みいただきありがとうございました。