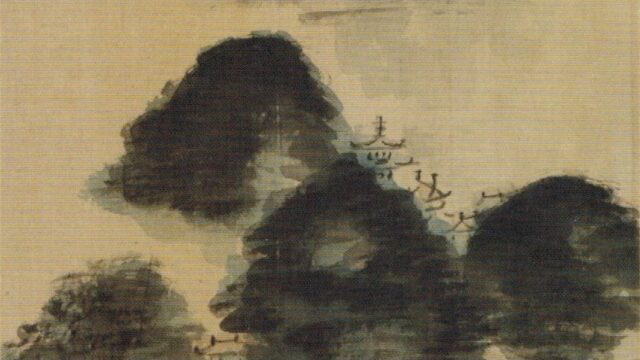「ぬぃの中国文学ノート」にご来訪ありがとうございます。
こちらの記事では、民国期の聞一多についてみていきます。
聞一多という人をたぶん多くの方は知らないかもですが、すごく独特な古典文学の研究をしていて、西洋の民俗学・神話学などを入れていくのが魅力です。
ちなみに、そのころの文学研究についてみてみると、清代末期くらいには、古い名品を再現するための分類法などが、もはや完璧になっています(いままでの名品をどのように再現するのか――というのが、明清期の風潮です)

というわけで、そんな爛熟期のあとに、全く違う方向から作品をみていくのが、聞一多の魅力です(とりあえず古代についての研究を紹介してみます)
九歌の神々
まずは、九歌(戦国期の楚の神楽)で祀られていた神々についてです。
この「九歌」って、十一個あるのに、なぜ九歌なのか……ということについて、聞一多は「東皇太一・雲中君・湘君・湘夫人・大司命・少司命・東君・河伯・山鬼・国殤・礼魂」がある中で、「東皇太一」は神を迎える曲、「礼魂」は神を送る曲――としています。
さらに、最初の「東皇太一」はどこか落ちついた雰囲気があって、ほかの多情な神楽とは違っているので、たぶん最も格の高い神なので、尊ばれている一方で、信仰がどこか形式化しやすい――としています(ヒンドゥー教のブラフマー神みたいな感じです)
ちょっとだけ「東皇太一」と「大司命」をみてみます(大司命は寿命をあやつる神です)
良き日の美しきときに、おごそかに東皇を楽しませる。その神体は長い剣をさげて玉の耳飾りで、さらさらと重ねた環が鳴りました。その霊はゆらりと垂れて美しき服につつまれて、花の香りはひらひらと堂に満ちて、五つの音がはらはらと集まり奏でれば、その神も安らかに楽しまれました。
がらがらと天門をあけて、もやもやとあふれる黒い雲に乗りて、速き風を前に馳らせ、冷たい雨は塵を清めていく。眼下にざわめく九つの州は、その寿は私のつかさどるものでもなく、ただ高らかに車を馳せて飛んでいけば、天の清気に乗りて陰陽をみちびくだけなのだ。
吉日兮辰良、穆将愉兮上皇。撫長剣兮玉珥、璆鏘鳴兮琳琅。……霊偃蹇兮姣服、芳菲菲兮満堂。五音紛兮繁會、君欣欣兮楽康。(「東皇太一」より)
廣開兮天門、紛吾乗兮玄雲。令飄風兮先駆、使涷雨兮灑塵。……紛總總兮九州、何寿夭兮在予。高飛兮安翔、乗清気兮御陰陽。(「大司命」より)
東皇太一はほとんど動きませんが、大司命はすごく勢いがあります。
さらに、「大司命・小司命」はもともと斉(山東省)のほうで生まれている神、「湘君・湘夫人」は楚にあった湘水の土着神としています。そして、「東君」は晋(山西省)の太陽神で、「雲中君」が趙(山西~河北省)の雲神なので、太陽と雲であわせて祀られていた……みたいになります。
こんなふうに、九歌の神々がどういう由来なのかを、神話学などでみていくのがすごく新しいのです(ここまで「什么是九歌」より)
宋玉のアレンジ
つづいては、神話と文学の間について、宋玉(戦国末期の楚の人)の「高唐賦」からいきます。
楚の襄王は、宋玉を引きつれて雲夢の楼にきて、高唐の館より外をみていると、空にはもやもやと雲気が漂っていた。
ここでは昔の楚王も昼寝をしたときに、夢でひとりの婦人があらわれて、「私は巫山の神女です。楚王が高唐まで来たときいて、遊びに参りました」といったので、王はそれを喜んだ。さらに神女は帰るときに「私は巫山の南にて、朝には雲になり、夕には雨になるのです」と残していった。
楚襄王與宋玉遊於雲夢之台、望高唐之観。其上獨有雲気、……昔者先王嘗遊高唐、怠而昼寝、夢見一婦人、曰「妾巫山之女也、……聞君遊高唐、願薦枕席。」王因幸之。去而辞曰「妾在巫山之陽、……旦為朝雲、暮為行雨。」(宋玉「高唐賦」)
聞一多は、なぜ神女が雨や雲になるのだろうか……、なぜ高唐なのか……ということを考えていきます(いままでの人は、あまり疑問を持たない路線です)
まず、中国ではこの話がもとになって、「雲雨」で情交のことになります。でも、先秦~漢代にかけては、虹が「情交」と深く結びついています。
虹は、陰陽の気が交わっているもの。
二つの虹が耀いているのは、君主が内にて淫らなため。
九つの虹が一度にでて、五色がきらきら交わり、互いの尾をくわえたり、頭に絡みついたりしていると、節度を失っていて、後宮では九人の貴嬪たちが策をめぐらし、正妃が追い出される。
虹、陰陽交気也。(『呂覧』節喪篇 高誘注より)
虹霓主内淫也。(『開元占経』巻九十八の『春秋潜潭巴』より)
九虹倶出、五色縦横、或頭銜尾、或尾繞頭、失節。九女並譌、正妃悉黜。(『開元占経』巻九十八の『春秋感精符』より)
虹が陰陽の気のまざって生まれる――というのは、たぶん「陽の光と雲雨のふたつがあるときにできる」みたいなことです。
そして、虹と雲雨はいつも一緒にあらわれるので、宋玉は「虹と情交がつながっているなら、雲雨と情交もあわせて大丈夫だろう」というふうにして、“雲雨をまとった神女”みたいな描写にしていきます(古代の神話っぽいのに、詩的な美しさをすごく大事にしています)
さらに、「雲夢」「高唐」という地名についても、こんな感じでみていきます。
燕国の「有祖」は、たとえてみれば斉国の「社稷」、宋国の「桑林」、楚国の「雲夢」みたいなもので、歌垣が行われるところ。
桑林とは、桑山の林のこと。雲雨を起こす力がある。
燕之有祖、当斉之社稷、宋之桑林、楚之雲夢也。此男女之所属而観也。(『墨子』明鬼篇)
桑林、桑山之林、能興雲作雨也。(『呂覧』順民篇 高誘注)
まず、こちらでは、楚の「雲夢」は、歌垣が行われる場所――としています(歌垣も、まぁ情交みたいな意味です)。さらに、「雲夢」と似たような役割をもっていた「桑林」は、雨乞いをするところでもありました。
さらに「高唐」の唐は、もともと「啺(とう)」の別字があって、「高啺」と「高陽」は、音がかなり似ています。ここから、楚の祖先には顓頊(せんぎょく。姓は高陽氏)がいるので、高唐は“楚の祖先を祀る場所”だった――としていきます。
これをみていると、「高唐」「雲夢」はどちらも祖先や情交、雨乞いなど、楚の人々の生殖や豊穣などとつながりのある地名です。
なので、宋玉の「高唐賦」は、神話らしさもまだ濃いときに、わずかに詩的なアレンジ(虹と雲雨)も入っているのが名品になっている――みたいになります。
ちなみに、この神女の姿は「華色のひらひらとした衣を重ね、翡翠の羽を奮わせるに似て……」みたいに、かなり極彩色の虹みたいな色になっています。

(もっとも、「高唐」の地名については、かなり難しい話があるのですが、ここでは端折ってしまいました……。こちらは「高唐神女伝説之分析」からです)
ひょうたんの神
さっきのがすごく難しかったので、ちょっとゆるめにいきます(笑)
中国には、伏羲(ふくぎ)・女媧(じょか)という神様がいて、人面蛇身で、兄妹にして夫婦とされています。また、泥をこねて人間を生み出したとされ、ふたりは人間の始祖ともされます(この二人は、二匹の蛇がねじれて絡みあう姿で描かれることが多いです)
そんな中、「伏羲」「女媧」って、どういう意味なのでしょうか……ということを聞一多は考えていきます(本質的すぎます……)
実は、伏羲・女媧のように兄妹で夫婦の神々が、人間を生み出した――という神話は、中国の南西部の地方伝承にもかなり多いのです。しかも、神の名をみていると、兄のほうはP・H、妹のほうはKが入ることが多くて、「伏・媧」の音みたいじゃないですか。
しかも、地方伝承verでは、大洪水を生き残ったふたり――という設定もあって、箱舟神話みたいになっています(ひょうたん・瓜の中で生き残ることが多いです)
ちなみに、ひょうたんは「瓢」「匏(ほう)」「瓠(こ)」「葫蘆(ころ)」など、どこか伏羲・女媧に似ている音になっています。なので、伏羲・女媧は、実はふっくらころんと丸いひょうたんの神なのではないか――というふうになります(これは初めてみて衝撃でした……)
さらに、蛇の身体になっていることについては、古い時代には蛇(龍)の神がたくさんいたことを示していきます。
まず、「螣蛇(とうだ)」という蛇神について、「螣蛇は霧の中を泳ぐ(淮南子・説林訓)」みたいに雲雨をまとった蛇……みたいになっています。「螣」は、滕(とう)と同じで、ぐねぐねぐちゃぐちゃしていることです(藤・籐とかも蔓がぐちゃぐちゃあふれまわる植物です)
なので、螣蛇はぐねぐねと絡みあっている蛇のことで、その姿は伏羲・女媧とすごく似ています。
すごく余談ですが、むかし奇門遁甲の本で「螣蛇夭嬌」という配置になったときは「痴情沙汰が起こりやすい」みたいにあって、なぜ蛇が痴情沙汰なのかとても謎だったのですが、夭嬌はうねうねなので、うねうね絡みあう二匹の蛇――という意味なのかもです(笑)
あと、句芒(くぼう)・蓐収(じょくしゅう)などの神は、“二匹の龍にのっている”とあって、これも二匹の蛇が小さく取りこまれているもの――みたいになります。
そして、聞一多は古代の帝王たちも、実は蛇神だった――とみていきます(混乱をきわめた古層の神々については、こちらに書いてます笑)

まず、祝融(南の火神)は、「䖺䗤(ちょうよう)は、黄色い蛇のようで、水に出入りするときに光を出して、あらわれると雨を奪う(山海経・東山経)」だったり、「燭龍は、人面蛇身で赤くて、目をひらくと明るくなり、閉じると暗くなる(山海経・大荒北経)」みたいな“熱をおびた蛇神”と、すごく音が似ていて、もとはひとつのイメージにも思えてきます。
さらに、黄帝(軒轅ともいう)は、「軒轅の国は、人面蛇身で、尾がその首に絡んでいる(山海経・海外西経)」とあります。しかも「軒轅(けんえん)」という星座もあるのですが、「黄色い龍の姿で……(史記・天官書)」とあって、じつは黄色の龍が「黄帝(軒轅)」になっている――としています。
こんなふうに、いままで無味乾燥なつなぎ合わせしかできなかった中国の神話を、生き生きとあざやかで詩的に蘇らせていくのが、すごく魅力的なのです……。もはや神の名が、ひとつの詩みたいになっています(ここまで「伏羲考」からでした)
というわけで、かなり難しい話が多くなってしまいましたが、民俗学・神話学などを入れて、中国文学をみていくところを、少しでも感じていただけたら嬉しいです。
お読みいただきありがとうございました。