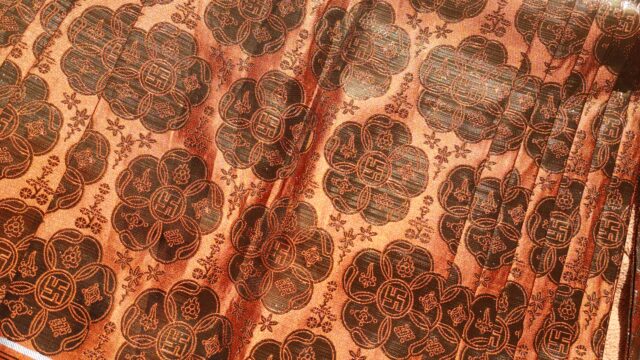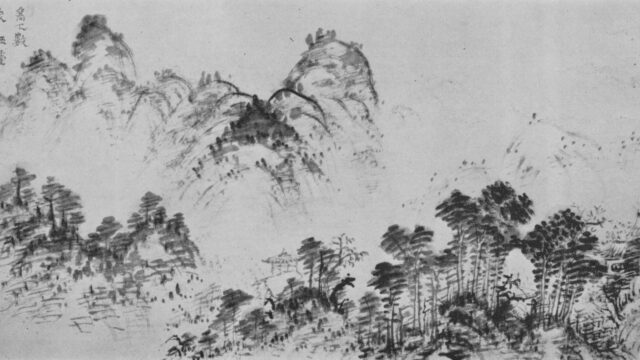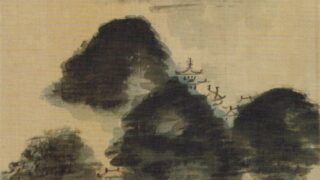ぬぃの中国文学ノート」にご来訪ありがとうございます。
こちらの記事では、わたしが中国文学をいろいろみていて、日本語について感じたことを書いてみます。
いきなり結論を云ってしまうと、日本語では古代から現代まで「ふたつの雰囲気が混ざるような表現」があって、日本の名品は、いずれもその派生形みたいに思っています。
なんか我ながらすごく大きいことを書いているなぁ……と思うのですが、かなり長いのですごく暇な方だけみてみてください(笑)
ぬるぬるした姿
まず、すごく古いところから行くと、『万葉集』の序詞・枕詞は、風景なのか比喩なのかわからないのです。
見わたせば 明石の浦に 燭(とも)す火の 穂にぞ出でぬる 妹に恋ふらく(万葉集326)
こちらの歌は、「見わたせば 明石の浦に 燭す火の」が序詞になって「(ゆれる火の)穂先のごとく、恋する気持ちがあらわれてしまう……」としています(ちなみに、実際に灯りをみて作ったので、風景と序詞は重なってます)
もうひとつ、序詞をのせてみます。
み吉野の 真木立つ山に 青く生ふる 山菅の根の ねもころに 我が思ふ君は 大君の 任(ま)けのまにまに 鄙離(ひなさか)る 国治めにと …… 朝立ちいなば …… 延(は)ふ蔦の 別れのあまた 惜しきものかも(万葉集3291)
これは「み吉野の 真木立つ山に 青く生ふる 山菅の根の」までが序詞になって、「ねもころに(親密に・みっしりと)」につながります。
ですが、序詞をみていると、どんよりと薄暗い吉野の山中がみえてきて、狭く絡みあった菅の根のように重く固まっている……という気分の比喩にもなっています。
さらに、蔦がいくつも枝分かれするように、わたしたちも裂かれていくのです……みたいに、こちらも風景と比喩が重なります。
そして、これをみたあとに、ふつうの風景だけの歌をみてみます。
信濃路は 今の墾(は)り道 刈りばねに 足踏ましなむ 沓(くつ)はけ我が背(万葉集3399)
意味としては「信濃路は、最近ひらいたばかりの道だから、刈りばね(切り株)に足をぶつけないように、靴を履いてください」というようになっています。
この「信濃路は」と「み吉野の 真木立つ山に 青く生ふる 山菅の根の」って、どちらもざわざわと不気味に木々が騒いでいて、あやしげな魍魎たちが棲んでいる万葉期の自然っぽくないですか(こんなふうに、枕詞・序詞はどこか風景っぽいのです)
さらさらした姿
風景と比喩がひとつになっている歌は、平安初期になると縁語と掛詞になります。
『古今和歌集』は、平安初期(9c初め、作者不明の歌が多い)・六歌仙の時代(9c中ごろ、在原業平・小野小町などが活躍)・撰者の時代(9c終わり~10c初め、古今集をつくった人たちの時代)にわかれています。
とりわけ縁語・掛詞がきれいなのは、平安初期のものです。でも、その前にふつうの風景だけを書いている歌をみておきます。
深山(みやま)には霰ふるらし 外山なる正木のかづら色づきにけり(古今集1077)
神垣の御室(みむろ)の山の榊葉は神のみまへにしげりあひにけり(古今集1074)
このふたつは、どちらも宮中のお祭りの歌です(永遠につづく季節だけがあるような世界がすごく好きです)
深い山には霰が降っているのか、寒さがぼんやりと降りてきて、里の近くの山まで木の葉が色づいてきた……だったり、みむろ(神が籠る山)の榊は、その神秘を浴びてか綺麗に茂っている……のような、湿った匂いに満ちています。
というわけで、縁語・掛詞についてです。
龍田川錦おりかく神な月しぐれのあめをたてぬきにして(古今集314)
ほととぎす鳴くや五月のあやめ草 あやめも知らぬ恋もするかな(古今集469)
まず、ひとつめは「錦・たてぬき(経糸と緯糸)」の縁語で、紅葉の色と雨の糸がひとつに混ざりあって、しっとりあでやかな色になっています(さっきの二首にすごく似ている風景です)
さらに、ニつめは、梅雨の中をぼんやり過ごすように、あやめ草を眺めつつ、あやめ(分別)も忘れて思いにふけってしまうのです……という歌です(風景と気分のつながりが、掛詞になっています)
こんなふうに、平安初期の歌では、縁語・掛詞などで二つのものの間に漂っている雰囲気をみせています(あと、万葉集では鬱蒼としていた自然が、さらさらと淡い色になります)
もっとも、平安時代がすすんでいくと、和歌の約束事などが決められてしまい、その場の雰囲気を感じて歌をつくる、ということが減っていきます。
もっとも、魅力的な歌はそれなりにあります。
都にも初雪ふれば小野山のまきの炭竃たきまさるらむ(後拾遺集401、相模)
こりつみて槇の炭やく気(け)をぬるみ大原山の雪のむらぎえ(後拾遺集414、和泉式部)
このふたつは、炭竃とひんやりした雪の混ざりあいが、すごく綺麗です(もっとも、縁語・掛詞のないものに名品は多いのですが……)
そして、『古今集』が平安の美意識とすると、鎌倉~室町(中世)の美意識は『新古今和歌集』でつくられています。
ひんやりした姿
『新古今集』の魅力は、なんといっても、その「ひんやりとうすら寒いのに、あでやかで色が濃い」というところだと思います。
くれてゆく春の湊はしらねども霞に落つる宇治の柴舟(新古今集169、寂蓮法師)
儚くて過ぎにし方をかぞふれば花に物思ふ春ぞ経にける(新古今集101、式子内親王)
薄霧の立ちまふ山のもみぢ葉はさやかならねどそれとみえけり(新古今集524、高倉院)
これらはいずれも新古今集時代の人の作品なのですが、しっとり冷たく艶やかな色に溢れています。さらに『新古今集』に入っている歌は、万葉時代の人でも、すごく新古今風なのです。
篠の葉は深山もそよに乱るなりわれは妹思ふ別れ来ぬれば(新古今集900、柿本人麻呂)
百敷(ももしき)の大宮人は暇(いとま)あれや櫻かざして今日もくらしつ(新古今集104、山部赤人)
あしひきの山の蔭草結びおきて恋やわたらむ会ふよしもなみ(新古今集1213、大伴家持)
荒小田(あらおだ)の去年の古根の古蓬今は春べとひこばえにけり(新古今集77、曾禰好忠)
最初の三つは、いずれも万葉の歌人ですが、さらさらとした秋草のような新古今調の雰囲気になっています(人麻呂・赤人って、こんな作品あるんだ……とか思います笑)
あと、山部赤人の歌は、櫻のしっとりきらびやかで、やや物憂い色彩が、なんとなく曇った色ですごく綺麗です♪
最後の曾禰好忠(そねのよしただ)は、平安時代にやや異色な歌を詠んだ人です(「去年(こぞ)の古根の古蓬」みたいな卑俗な語は、約束事が多い平安時代には忌まれる面もありました)。やはり「冷ややかな中にある春の芽のあでやかさ」が好まれています。
そして、この歌風は、中世和歌において“どこか荒さもあって、ひんやりとした秋草のような優美さ”という美意識になっていきます。
まぁ、中世和歌は一種のマンネリに陥っているという評価もあるのですが、その中でもいいものをあげてみます。
夜半にたく鹿火屋が煙立ちそひて朝霧ふかし小山田の原(新勅撰集276、慈円)
里のあまの定めぬ宿も埋もれぬ寄する渚の雪の白浪(新勅撰集425、八條院高倉)
冬きぬとけさは岩田の柞原音にたてても降るしぐれかな(続拾遺集381、藤原知家)
立田姫今やこずえのから錦おりはへ秋のいろぞしぐるる(続拾遺集357、衣笠内大臣)
「鹿火屋(かひや)」は田んぼに近寄る鹿を追いやるために火を焚く小屋、「柞(ははそ)」はナラの木です。
いずれも秋は枯れ色と紅葉、冬は雪と時雨……みたいに、もはや蒔絵の意匠みたいに様式化された色彩です(これもふつうに好きです)
うねうねした姿
ですが、そんな和歌の世界で、京極派の歌人たちがあらわれて、新古今ふうの様式を真似するだけになっていた中世和歌を大きく変えていきます。
京極派の和歌は、すごく魅力的な様式性があります。
猶さゆるあらしは雪を吹きまぜて夕暮れさむき春雨の空(玉葉集33、永福門院)
日の影は竹より西にへだたりて夕風すずしき庭のくさむら(風雅集422、祝子内親王)
風に落つる草葉の露も隠れなくまがきに清きいりがたの月(風雅集620、儀子内親王)
山もとの竹はむらむら埋もれて烟もさむき雪のあさあけ(風雅集842、花園院一條)
これを読んでいて思うのは、いずれも「ものごとの中間」を感じるのがとても上手です。
「雪を散らしながら、春雨が降っている空」「竹を隔ててさす夕日と、さらさらゆれる草むら」「竹に雪が降りかかって、上には霧がきらきらと舞う様子」みたいに、ふたつのものの間を描くのが京極派らしさです。
あと、もうひとつ注目したいのが、「風に舞う雪が入ってきていて、しかも夕暮れにうすら寒い春雨の空」だったり「草の葉の露もはっきりみえるほどに明るくて、しかも籬に清らかな光を落としている月」みたいに、ひとつの風景の中をうねうねと曲がるようにつなげて書いていることです。
この様式をもちいていくと、かなり無理やりなつながりもできてしまいます(笑)
呉竹のめぐれる里を麓にて烟にまじる山のもみぢ葉(風雅集678、花園院)
こちらは、初めはふもとの里だったのに、いつの間にか離れたところの山の紅葉になっています(この取り合わせ、すごく綺麗ですよね……)
平安初期の歌たちが、時雨にぼんやりつつまれた山全体をひとつの匂いで満たしてしたのに比べて、京極派の和歌では、新古今集のひんやりとした中世的自然を継ぎながらも、あちこちの風景をうねうねと結びつけて、やや異質な取り合わせの美しさになっています。
そして、紅葉や里の竹ではなくて、そのふたつの間にある匂い・雰囲気を好んでいる……というのが、すごく平安初期に似ています。
きらきらした姿
ここまでいろいろな例をみてきたのですが、お気づきの方もいるとは思いますが、実はこの“混ざりあいの文体”は、風景の美しさは書けるけど、ちょっと難しい話を書くときにはほとんど用いられない、という難点があります。
ですが、その限界を超えていったのが、中世最大の漢文学家とされる一条兼良です。
この人は、漢文だけでなく、和歌だったり、日本の儀礼などにも通じていました。ここでは、勅撰和歌集の序文をみていきます。(ちなみに、一条兼良は京極派よりも後のひとです)
浦々にかき置く藻塩草は千はこの数よりも多く、家々に積れる言の葉は五つの車に載すとも堪ふまじ。…… これによりて延喜に芸閣の風かうばしく、天暦に梨壺の蔭栄えし昔を慕ふのみならず、元久に鳥羽の跡かさなり、文永に亀山の齢久しき例をおぼしめして……(『新続古今和歌集』真名序)
「藻塩草」は心の奥にくすぶって燃えている想いの比喩なので、「奥底に秘めた想いを詠んだ歌は、日本の浦々にあって千よりも多く」という意味です。
つぎの「五つの車に載すとも堪ふまじ(五つの車に載せても、載りきらないだろう)」は、中国の『荘子』の中にでてくる「恵施は学問がとても広く深くて、その書は五つの車に載せて運ぶほどだった(恵施多方、其書五車)」をもとにしています。これも和歌の書がいくつもある喩えです。
「延喜」は古今集のときの年号、「芸閣」は宮中の蔵書楼です。梨壺(後宮の昭陽舎のこと。庭に梨の木があった)は天暦年間に『後撰和歌集』を編纂したところです。
元久は後鳥羽院の年号で『新古今集』が生まれます。「鳥羽の跡」とは、中国で蒼頡(そうきつ)が鳥の足跡から文字をつくったように、新古今集でさらに和歌の文字がふえたことです。
文永は亀山天皇のときの年号です。「亀山の齢久しく」は、『楚辞』天問などで蓬莱などの仙山は、大きい亀(鰲:ごう)が支えているという伝承です(このころ、『続古今和歌集』ができました)
これをみると、一条兼良は歴史的なできごとだったり、和歌がさかんなことなどを日本と中国の出典をもちいながら、しかも一つの風景にしてます(しかも、どこかおめでたい雰囲気も出ています)
あと、対句を整えて出典をたくさん並べる文体を、中国では「駢文(べんぶん)」というのですが、これは日本語の駢文ですね(中国の駢文では、対句と出典はきれいに整えますが、全体が一つの景色になっていないです)

そして、この表現をさらに深めていったのが、江戸時代の上田秋成になります。
其後十三年を経て治承三年の秋、平の重盛病に係りて世を逝(さり)ぬれば、……頼朝東風に競ひおこり、義仲北雪をはらふて出るに及び、平氏の一門ことごとく西の海に漂ひ、……武(たけ)きつはものども多く鼇魚の腹に葬られ、赤間が関壇の浦にせまりて、幼主海に入らせたまへば、軍将(いくさぎみ)たちものこりなく亡びしまで、露たがはざりしぞおそろしくあやしき話柄(かたりぐさ)なりけり。其後御廟は玉もて雕り、丹青を彩りなして、稜威(みいづ)を崇めたてまつる。(『雨月物語』「白峰」の終わりから)
上田秋成といえば、やはり『雨月物語』です。こちらは、崇徳院の怨霊が平家の滅びを予言した後のところです。
私が好きなのは「頼朝東風に競ひおこり、義仲北雪をはらふて出るに及び……」です。これがもし「頼朝は○○にて……と争い、その間に義仲は◎◎にて――して」だったら、このやや遠巻きにみている雰囲気を壊してしまいます。
もうひとつ、「多く鼇魚の腹に葬られ」のところも、崇徳院が繰り出したあやしげな鬼神のような「鼇魚(鼇:ごう、大きい亀のこと)」が突如水中から襲ってくるような感じになっています。
そして、終わりのほうにある崇徳院の御廟(祭殿)のきらきら妖しくかがやく様子とあわせて、翳りのあってすさまじい鬼神たちに取り囲まれた崇徳院の雰囲気がよくでています。
もうひとつ、秋成の例をみてみます。
豊雄も日々に心とけて、もとより容姿(かたち)のよろしきを愛(めで)よろこび、千とせをかけて契るには、葛城や高間の山に夜々ごとにたつ雲も、初瀬の寺の暁の鐘に雨収まりて、只あひあふ事の遅きをなん恨みける。(『雨月物語』「蛇性の婬」より豊雄と真女子の婚儀)
ここでは、結婚と合わせて、雲が涌いたり、雨が収まったりするのが描かれています。
これは、宋玉「高唐賦」の「旦為朝雲、暮為行雨。朝朝暮暮、陽台之下(わたくしは朝には雲となって、夕には雨となって、朝な夕なに陽台の下にてお会いしましょう)」という楚王と神女の逢瀬から「雲雨」で情交の意になることをもとにしています(でも、山の風景としても、すごく自然です)
こんなふうに、怨霊が使役するあやしげな鬼神だったり、夜ごとに涌く情交の意だったりと、かなり複雑な内容を、漢文の出典などをもちいて風景に溶かしていき、どんなことでもおしゃれな趣きにしてしまいます。
ひっそりした姿
ところで、江戸期にはもうひとつ、風景に複雑な意味を入れていく文学がありました。それが俳句になります。
ちょっとどういうことかわからない方も多いと思うので、いくつか例を示します。
鳥羽殿に五六騎いそぐ野分かな 蕪村
これは有名な与謝蕪村の句です。「鳥羽殿」は平安末期に上皇が住んでいた御所のことです。平安末期の不穏な状況のなかで、五六騎の使いが鳥羽殿に駆けていくときには、さらに不穏な野分(のわき、台風のこと)が薄暗い風を吹かせている……というように、「野分」と「鳥羽殿」のあいだにある「不穏さ」がぼんやりと滲み出ています。
あえて有名ではない作品もいきます。
春雨や桐の芽作る伐木口(きりこぐち) 本好
こちらも、「春雨」のほのかな生気が「桐の芽」が小さく出てきている様子とうっすら重なっています。「ほのかな生気」だったり「動乱の不穏さ」だったりと、いままでの和歌にはあまり書かれなかった内容でも、江戸時代にはふたつの雰囲気の重なりにできるようになった感があります。
霊徳の邂逅
タイトルがやばいな……と思うのですが(笑)、こんな日本語の性質について、近代の北原白秋がすごく興味深いことを書いています。
ここに紅と緑との林檎が二つある。紅は紅、緑は緑で何れも明確である。而もこの二つがこの如くこの卓上のこの時間に重りころげて、深く深く相親しみ、色と色とを映じ、香りと香りとを混へ、影と影とをぼかし、本質と本質との接触を愉楽し呼吸することは真にこれ千万年にただ一度の機会である。……かうした場合、紅と緑とが愈々明確である故に、その中間の色合は、陰影は、その背後の空気は愈々深く、愈々美しく揺曳する。
……殊に万物の観照に於て、真の伝神の秘法、象徴の奥儀はこの日本固有の俳句若くは短歌の如きに初めて、世界無二の光輝を放たれたのであつた。(『水墨集』序文「芸術の円光」より)
この「芸術の円光」という詩論は、とにかく人を酔わせる文章で(笑)、その中には物そのものがもっている気品・味わいなどを「霊徳」といっているところがあるのですが、詩はその霊徳どうしの混ざりあう様子を言葉で示すこと、というふうにしています(紅と緑の林檎の喩え)
この紅と緑の林檎を、「時雨のふる山・紅葉」だったり、「西の竹にかげる夕日・風にゆれる庭の草」、もしくは「怨霊・東風北雪を帯びて暴れる鰲魚」などのようにみると、このような「万物の観照(ものごとの本質を見ること)」において、日本の短歌・俳句は最もすぐれた表現をつくってきた、というふうにみえませんか。
これは、白秋の作品にもよくみられます。
やどり木
あらはに透いて冴ゆるは
高いけやきのやどり木、
丹沢山の北風。(北原白秋『水墨集』より)
こちらは、「透いて冴ゆる」という質感が風だけでなく、やどり木まで及んでいるような……というふうになっています。こんなふうに、ふたつの雰囲気がどこか混ざりあうような感じが、日本語の名品にはいろいろな形であるのかもです。
おわりに
ということで、すごく削ったつもりですが、とにかく長いですね……。ちなみに、こういう表現は、現代でも少し生き残っています。
なんとなく私のみてきた感じだと、ボーカロイドの歌詞などではたまにあるかもです。SEVENTHLINKSさんの「p.h.」では、化学用語や医療用語を混ぜています。
aとaが混ざり合って
自己解離定数を満たした
たとえばこの辺りとかは、自分の精神が崩れることを「自己解離」と書いています。(もともと自己解離は化学用語らしいです。あと、「p.h.」は酸性・アルカリ性の濃度を示す数値です)
このショッキングな色彩、すごくいいですよね(全然関係ないけど)。というわけで、こんな長すぎる記事をお読みいただき、ありがとうございました。