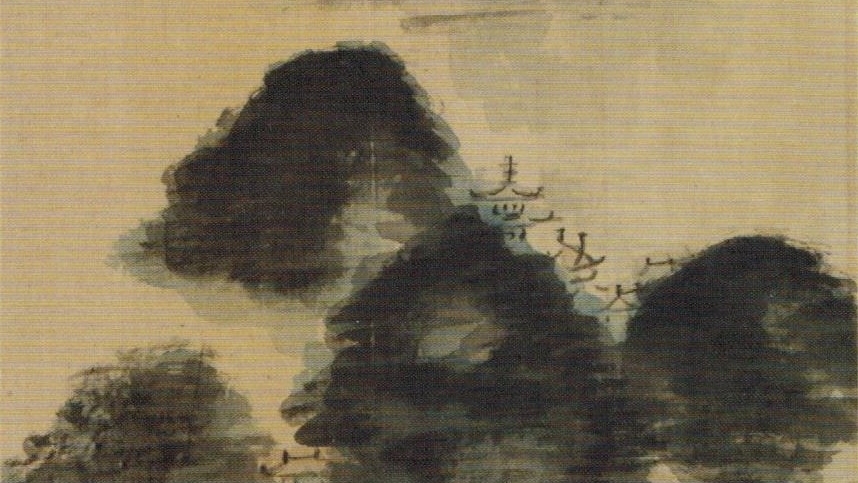「ぬぃの中国文学ノート」にご来訪ありがとうございます。
こちらの記事では、清の終わり~民国期に生きていた王国維についてみていきます。
王国維という人は、はじめは西洋思想から入って、つぎに中国文学(詞)のほうに興味が移っていく……という、やや変わった経歴があります。
なので、その作品や文学論は、西洋の文化をうまく混ぜて生みだされていて、いままでのものとは全然違う魅力をもっています。
ちなみに、清代末期~民国期の詞の研究では、「それぞれの詞人たちは、想いをどのような形で描いているのか」というのを、一字一句丁寧に分析していく……というスタイルが流行っていました(これはこれですごく深い世界です)

ですが、王国維は、かなり雰囲気が異なります。というわけで、まずは理論からみていきます。
ショーペンハウアー的な芸術論
王国維は、ショーペンハウアー(19世紀前半のドイツの哲学者)をすごく好んでいました。
ショーペンハウアーの思想は、すごく大まかにいうとこんな感じです(これが正しいか否かはとりあえず置いておきます)
まず、人間はとにかく自分が生き残るための欲に突き動かされて生きている――、さらにその欲は生きている間は絶え間なく涌きだして、みずからの身をひたすら生き残るための殺し合いに向かわせていく――としています。
なので、この世界に生きていることはその欲に駆り立てられているだけで、たまにその欲が満たされても、しばらくすると再び殺し合いに巻き込まれて生きていくしかない――みたいになります。
ならば、この世界に生まれてしまった苦しみから、どのように逃れられるのかといえば、生きるための欲とは関わらない楽しみをみつけるのがいい(その楽しみは、みずからの身と関わらないような、世界そのものをみて楽しむ如きもの――)としています。
王国維はこれを取り込んで、『人間詞話』という評論をつくっていきます。人間(じんかん)は、“人の世”のことなので、人の世に生きることと詞の関わり……みたいな意味だと思います。
詞は「境界(作品の中のひとつの世界)」があるのが最も良いものになる。
境界には、「有我の境」「無我の境」のふたつがある。有我の境とは、私からの目線で物をみている。無我の境では、物そのものとして世界をみている。
詞人がみずからの生を憂いているのは「昨夜の西風で木々は萎れ、ひとり楼に上って、天の果てをぼんやりみていました――」みたいな句。
詞人がこの世を憂いているのは、「さまざまの花草はそろそろ艶やかな春めいて、うつくしき車は誰の家に停まるのでしょうか……」みたいな句。
詞以境界為最上。
有有我之境、有無我之境。……有我之境、以我観物。……無我之境、以物観物。
詩人之憂生也、「昨夜西風凋碧樹。獨上高楼、望尽天涯路。」……詩人之憂世也、「百草千花寒食路、香車系在誰家樹。」
まず、この「境界(作品の中の世界)」とは、たぶん「この世は生まれてしまった苦しみだけがある世界」というふうに、世界が描かれていることです。
さらに「有我の世界」は、生き残るための殺し合いの中でつくられた詞にあって、「無我の世界」は、そこから離れて見ているような詞にあります。
また、みずからの苦しみだけを書いているのが「みずからの生を憂いている詞」、この世の苦しみを憂いているのは「世を憂いている詞」です。
(「うつくしき車は誰の家に……」は、誰もが春のざわめく心を抱えているのですが……という意味です)
これだけみても、王国維的ないい作品というのは、ショーペンハウアー感があります。
さらに、王国維は古詩十九首などにも、この世界に生きていく苦しみが描かれている――ということを評価しました。やや俗っぽいけれど、その想いの深さが魅力になっていて、もともと妓楼の曲だった詞もそういう魅力がある、とみています。

なので、優れた作品とは、難しい技巧を用いていたり、長くて複雑な形になっているものではなく、この世界の苦しみを描いていて、読んでいるとみずからの身を忘れて、世界そのものをみているような気がしてくるもの――という感覚が漂います。
というわけで、王国維の作品をみていきます。
優美な悲しみ
まずは、私がすごく好きなものからいきます(笑)
ひんやりと前庭を濡らして、さらさら雨が過ぎていく頃、暗い街には鈍く鐘が鳴りました。眠りは浅くしてわずかに微睡んで、また東風がひんやり過ぎていくので。たった一人で、たった一人で。そろそろ夜が明けていきそうのでした。
点滴空階、疏雨迢遞、厳城更鼓。睡浅夢初成、又被東風吹去。無拠、無拠、斜漢垂垂欲曙。(王国維「如夢令」)
これは「無拠、無拠(たった一人で、たった一人で)」というのが、すごく悲しみに満ちた世界をみせているようで、大好きなのです。
わずかな眠りの安らぎすら、風に吹き破られて、夜明けの近づいてきて、春の雨も弱くなってくると、また一日が始まって、夜の安らぎも終わっていくのです……みたいな感じも泣けます。
あと、王国維って、「夢」「眠り」がすごく儚くて悲しいのです。
紅い楼は遠くでさらさらとした雨がふっていて、しとしとと暮れていく色が木々にぼやけておりました。樹の影はわたしの窓にかかり、あなたの家では灯りをつける頃でしょうか。 風がさらさらと枝を揺らして、私の西の窓をみだすので、夢が醒めればもとの寝室で、窓に花の影が落ちました。
紅楼遥隔廉繊雨、沈沈暝色籠高樹。樹影到儂窗、君家燈火光。 風枝和影弄、似妾西窗夢。夢醒即天涯、打窗聞落花。(王国維「菩薩蛮」)
……寂しいのに美しいというか、ほんのりと優美な悲しみのある詞です。王国維の詞って、晩唐~宋の初期っぽいというか、どこか宮女の趣きがあります。
こちらも作品は、起きているときは寂しくて、眠っているときはわずかに欲を満たしたようだったのに――のような、いつまでも癒されない寂しさがすごく素敵です。
どうでもいいけど、私の家で障子にさす木の影が、寝室にこんなふうにみえていました(どこか白い色を帯びたような影にみえるみたいな……。夜の安らぎは、生きる悲しみをひととき忘れるもの――みたいな感性が、王国維はあります)
ちなみに、この詞でもっとも好きなのは、最後の「窓に花の影が落ちました(打窗聞落花)」です。延々と世界は美しいはずなのに、いつまでもさびしい感じがすごく出ています。
もう一つ、夢を描いた不思議な作品をいきます。
ごろごろと延びている蓬莱の山――、夢の中で小舟で近くまでいってみると、その巌の岸はぎちぎちと曲がり、波の間から舟を近づけていく。 瀾の上の楼閣と、幾重にも重なった波たち。誰が住んでいるの――。断崖は鋸のようで、舟をつけるところも無いのです。
萬頃蓬壺、夢中昨夜扁舟去。縈回島嶼、中有舟行路。 波上楼台、波底層層俯。何人住。断崖如鋸、不見停橈処。(王国維「点紅唇」)
これはたぶん仙境の蓬莱まで行けたはずなのに、蓬莱には入れずにまた苦しみの世界に帰るしかない――ということだと思うのですが、中国っぽさとショーペンハウアー思想の混ぜ方がほんとうに綺麗です。
大きな地と高すぎる天、その中にいると自らの身すら消えていく気がして、小さな書斎は舟のようで、いくらでも自在なはずだけど。 わずかに浮かんだ命は、ひとときの私になって、天地は大きく、霜色の林にひとりで坐れば、紅葉がひらひら私を埋めていくのでした。
厚地高天、側身頗覚平生左。小斎如舸、自許迴旋可。 聊復浮生、得此須臾我。乾坤大、霜林獨坐、紅葉紛紛堕。(王国維「点紅唇」)
なんていうか、うす暗い書斎と、ひんやり紅い秋の林が、すごく似合っています(どこか薄暗い我が身と、その外で永遠に美しいはずの世界――みたいな悲しさがあります)
ちなみに、王国維が詞をつくっていたのは、1910年前後の数年なので、三十歳くらいのときです(わずか数年で、たくさんの傑作を出していきます)
その後は、しだいに甲骨文字などに興味が移っていき、そっち方面の研究をしていきます。そして、五十歳のときに入水自殺しています……(このどんよりと薄暗いのが王国維なんですよね……)
というわけで、やや暗い記事になってしまいましたが、王国維の魅力を感じていただけたら嬉しいです。最後にすごく余談ですが、私が中国文学にのめり込んだのは、王国維の『人間詞話』からでした(まぁ、それ以降に、もっと別の作品の良さにも気づいていくのですが、それでも王国維も好きです)
お読みいただきありがとうございました。