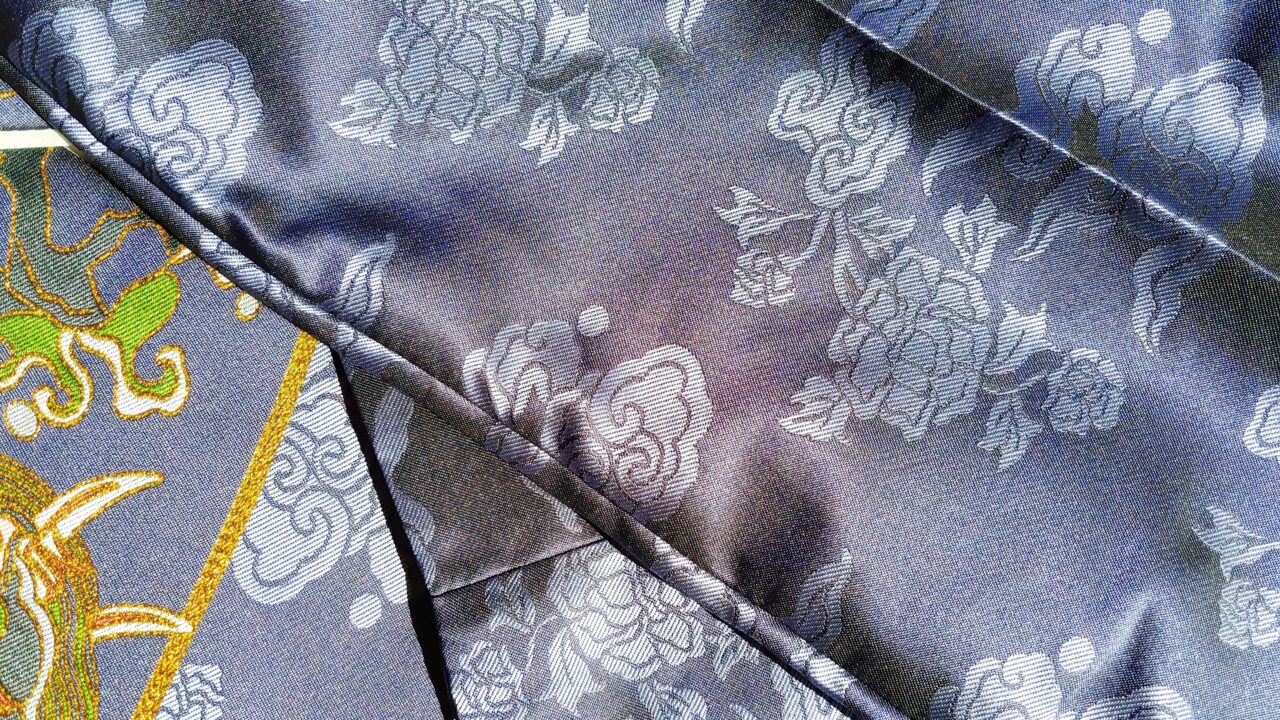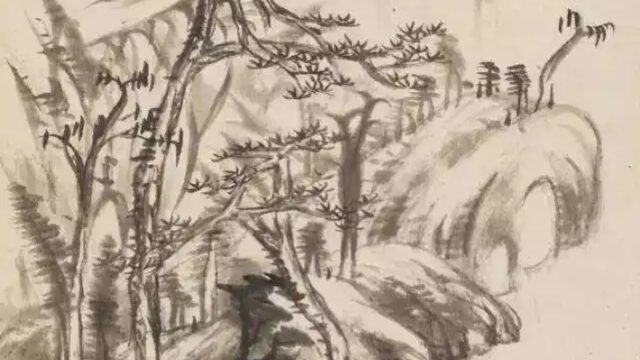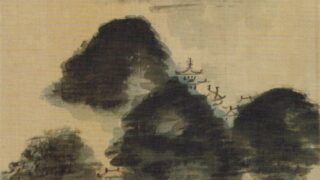「ぬぃの中国文学ノート」にご来訪ありがとうございます。
こちらの記事では、『芸概』という文学評論についてかいていきます。
この『芸概』というのは、晩清(1840~1911。アヘン戦争以降の清)において、劉熙載(りゅうきさい)というひとが、さまざまな文学などについてまとめた評論です。
こちらの『芸概』の魅力は、なんといってもさまざまなスタイルの作品の味わい方を、かなり体系化して整理してあるところです。もはや、いままでの中国文学をすべて理論として完成させた――とすら云えるほどの綺麗にまとまっています。
というわけで、すごく大まかにですが、その体系化された理論を紹介してみます。
詩は酔い泣き
まず、劉熙載の名言をひとつだけ選ぶことになったら、わたしは間違いなくこちらです(笑)
文は醒めていて、詩は醉っているふうに書くといい。醉っているときの話は、ふだんは云えないもので、きっと自然な想いがでているのだろう。
文においては「賢き人は、百里の先まで見て話す――」のようで、詩においては「わたしは誰よりも深く憂いて心が乱されている――」みたいなのが良い。
文善醒、詩善醉、醉中語亦有醒時道不到者、蓋其天機之發。……論文旨曰「惟此聖人、瞻言百里。」論詩旨曰「百爾所思、不如我所之。」(『芸概』巻二「詩概」)
これをみるだけでも、詩の本質がどこか滲んでいるくらい、劉熙載の見識は深いのです♪(こんなふうに、劉熙載を読むのはすごく楽しいです)
さらに、もうひとつ詩の本質については、こちらも大切だと思います。
詩は「楚辞」っぽい憂いをおびているものが王道で、「荘子」っぽい悟りをおびているのは変種。蘇軾の詩は、荘子らしいものが八~九割くらいある。
詩以出於騒者為正、以出於荘者為変。……東坡則出於荘者十之八九。(「詩概」より)
これは、楚辞が“見離されていく憂いや悲しみ”を感じさせることが多くて、ほとんどの詩は楚辞っぽい憂いが入っている……ということです。
ですが、荘子は“雑多な変化のひとつとして生まれて死んでいく”という悟りがあって、蘇軾の作品は、かなり荘子らしさが多いです。
流れる水は朱い欄に照り返し、浮き草は澄んだ水面にゆれるようなのでした。欄の上の人は、そんなとき物が移りかわるのをみていたのです。
流水照朱欄、浮萍乱明鑑。誰見檻上人、無言観物泛。(蘇軾「次韻子由岐下詩 其五 曲檻」)
あえてすごく短い作品ですが、この「欄の上の人は、物が移りかわるのをみていた」というのが、すごく荘子らしい雑多な水の光の変化みたいじゃないですか……(一方で、楚辞っぽいものは、どこか寂しげな趣きがあります)
海の鶴は一たび別れてのち、存亡して三十秋が過ぎましたが、今きてみて涙を流しながら、ひとりで駅の南楼に止まるのでした。
海鶴一為別、存亡三十秋。今来数行涙、獨上驛南楼。(柳宗元「長沙驛前南楼感舊」)
こちらは、時ばかりが流れてしまう憂い……みたいなものを感じさせます。こんなふうに、荘子らしい詩は悟りがあって、楚辞らしい詩は憂いがあります。
詩の様式美
さらに劉熙載は、さまざまな詩の様式(絶句・律詩など)は、それぞれどのようなものが理想かを整理していきます。
さまざまな詩の様式について理想を云えば、「絶句は多くのものを小さくまとめたようで柔らかい味わいがあるもの、律詩は短く切れているようですっきりまとまっているもの、五言古詩は落ちついていて素朴で優雅なもの、七言古詩はきらきらとしてあでやかに耀くもの」。
論古近體詩、……曰:絶「博約而温潤」、律「頓挫而清壮」、五古「平徹而間雅」、七古「煒煜而譎誑」。(「詩概」より)
これは、詩の様式ごとに名品の特徴をすごくとらえています。たとえば、さっきの蘇軾と柳宗元の絶句は、「さまざまな光をみせる波」だったり「三十年の存亡」みたいに、多くのものを小さくまとめていて、ぼんやりほのめかすように描かれています。
さらに、劉熙載は絶句については、こんなふうにいっています。
絶句のつくり方は「深みがあって遠まわし」なのがいい。想いが書ききれずにあふれているのが、むしろ想いの深さを感じるので、正面から描かずに横からわずかにのぞくようにすれば、いいものになる。
絶句取径貴深曲、蓋意不可尽、以不尽尽之。正面不寫寫……旁面、……乃妙。(「詩概」より)
「正面から描かずに、横からわずかにのぞくように……」というのは、さっきの蘇軾だったら「荘子のような流れる変化」を書きたいときには「浮草のきらめき」だけを書いて終わらせる……みたいなものです。
「七言古詩はきらきらとしてあでやかに耀くもの」が理想というのは、たぶん七言古詩がもともと乱(賦の終わりのもっとも賑やかで盛り上がる乱調子)から生まれたので、ちょっとキラキラして眼をあざむく感がほしい――というようなことだと思います。

軽い身はさらさらと白い衣を舞い上げて、高くのびている腕は白い鶴の羽に似て、龍の低くもぐるごとくめぐりて上がり、ひたひたと湿る眸はやわらかき秋の光を帯びたり――。流れるごとく引くごとく止まって落ちて、するすると世々ごとに姿を変じて定まらず……。
軽躯徐起何洋洋、高挙両手白鵠翔。宛若龍轉乍低昂、凝停善睞容儀光。如推若引留且行、随世而変誠無方。(無名氏「晋白紵舞歌詞 其一」)
もはやキラキラぎらぎらです(笑)「龍轉(龍のようにめぐる)」「容儀(きちんとした姿)」みたいな語が、すごくきらびやかに飾られていておしゃれです。
あと、五言古詩はもともと漢の民謡なので、どこか古色があって素朴で、しかも六朝期にも盛んだったので、貴族っぽく落ちついて優雅な感じがいい――みたいな雰囲気かもです。律詩はもともと官人の贈答用なので、それなりにきれいにまとまっていて、しかも対句が間延びせずに短く整っているもの――という感じですかね。

賦はたくさん並べる
さらに劉熙載は、賦についてもかなりたくさんの評論をのこしています。
賦についてすごく簡単にいうと、もともと楚辞(戦国期の楚にあった「○○○兮○○」という句で、楚の風物や神々を描くもの)から、漢代になって宮廷などを讃えるために生まれてきた長編美文です。
なので、劉熙載は、楚辞と漢賦をあわせて評していきます。
賦は、想いがあふれてごちゃごちゃとして、ふつうの詩では収まらないときに、賦によって想いをならべてつくる。なので、いろいろな風景や物事が入り乱れて、つぎつぎに現われても、なかなか想いが吐ききれない。
楚辞は、情感あふれる音楽のような賦。漢賦はきちんとして大がかりな儀礼のような賦。楚辞は心を重んじて、漢賦は事実を重んじているが、漢賦の名品はすべて楚辞から生まれている。
賦起於情事雑沓、詩不能馭、故為賦以鋪陳之。斯於千態萬状、層見迭出者、吐無不暢、暢無或竭。
楚辞、賦之楽。漢賦、賦之礼。……楚辞尚神理、漢賦尚事実。然漢賦之最上者、機括必従楚辞得来。(『芸概』巻三「賦概」)
劉熙載は、「賦」は、詩のなかでも想いがごちゃごちゃと溢れるようなときに、それを並べて長くなっていくもの――としています(楚辞・漢賦はすごく長いのです)
そして、楚辞は自然な情感がたくさんあり、漢賦は実際の物などが多いのですが、漢賦の名品は、かならず楚辞をさらに飾るようになっています。
たとえば、楚辞のなかで「湘夫人(湘水の神女)」では、祭具がこんなふうに出てきます。
水中に祭室をつくれば、荷の葉で上を覆って、白玉で蓆(むしろ)をおさえて、石蘭を飾って香りを満たし、芷(香草)でさらに屋根を葺いて、杜衡(香草)でそれを縛りつける……。
築室兮水中、葺之兮荷蓋。……白玉兮為鎮、疏石蘭兮為芳。芷葺兮荷屋、繚之兮杜衡。
ここでは「石蘭・芷・杜衡」などの楚の土着植物がたくさんあって、湘水の神女のいる部屋を飾っています(情感メインなので、あまり細かく書かないけど)
それが漢賦になると、もっとぎちぎちと技巧を詰め込んだような字になっていきます。
雲色の木組みと飾り柱は、龍のような枝が雕り込まれていて、飛ぶ鳥と走る獣が、木々の形によってさまざまに生まれてくる。沼の龍はぎりぎりと身を反らせてめぐりうねり、顎は高く上がってよじれ跳ねるごとく、朱い鳥はひらひらとしてその龍を迎えるごとく、もつれる蛇はぬらぬらとして梁に巻きつき、白い鹿はひとりで細い柱の上に立っていて、ぶくぶくと膨らみ絡まる蛇たちは門の柱にたまっている。
雲楶藻梲、龍桷雕鏤。飛禽走獣、因木生姿。……虯龍騰驤以蜿蟺、頷若動而躨跜。朱鳥舒翼以峙衡、騰蛇蟉虯而遶榱。白鹿孑蜺於欂櫨、蟠螭宛轉而承楣。(後漢・王延寿「魯霊光殿賦」)
これをみていると、漢賦はより細かい装飾などをならべるようになります。でも、神々や宮殿のうつくしさを讃えるような気持ちは似ています。
こんなふうに、楚辞をもとにしながら漢賦の名品はつくられていて、どちらも「並べることで想いを伝える」というものになります。
劉熙載は、こんなふうに「素材になる想いを、どのように書いていくのがいい作品か」というのを、律詩・絶句・賦などさまざまな様式ごとにマニュアル化していきます。
しかも、その理論はどんな作品の魅力でも、漏らすところなく分析できる――というすごく体系化されたものになっています(まぁ、これは私の好みかもですが)
というわけで、晩清の文学評論でも、すごく整理されている理論をもっている劉熙載の『芸概』でした。実はもっといろいろ面白いところはあるのですが、すごく大事なところだけを書くとこんな感じです。
やや難しい話が多くなってしまいましたが、お読みいただきありがとうございました。