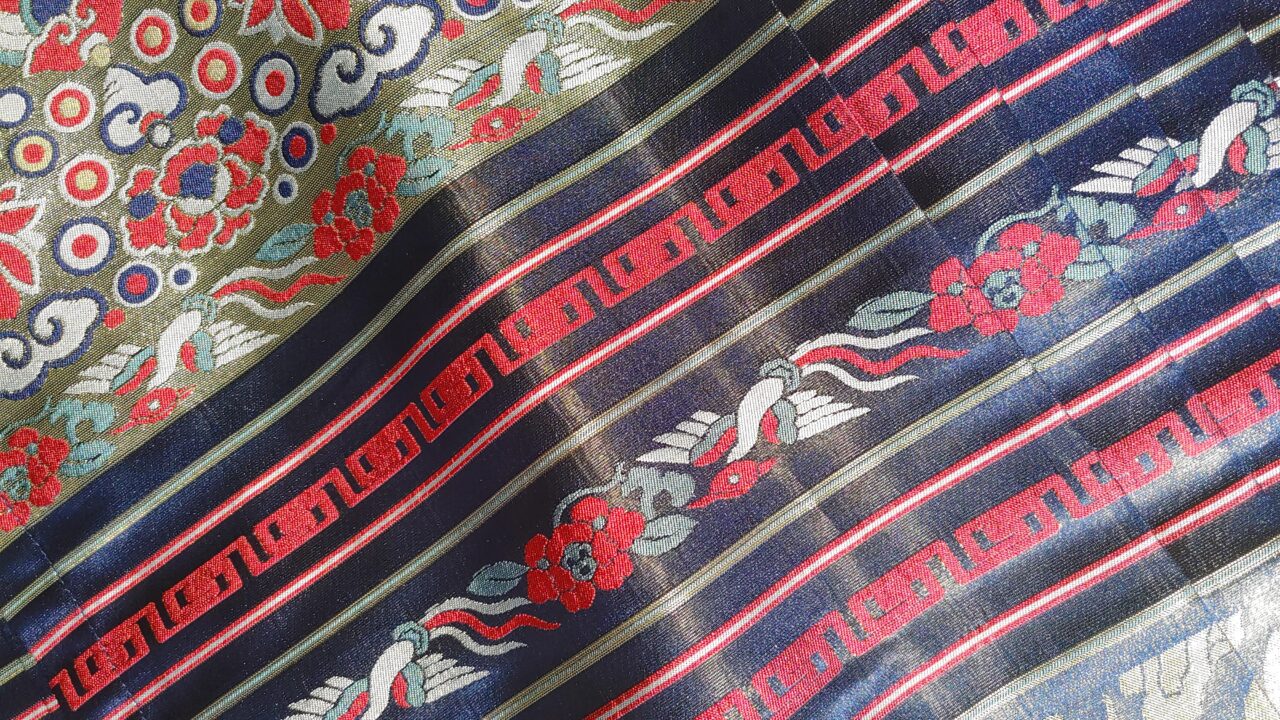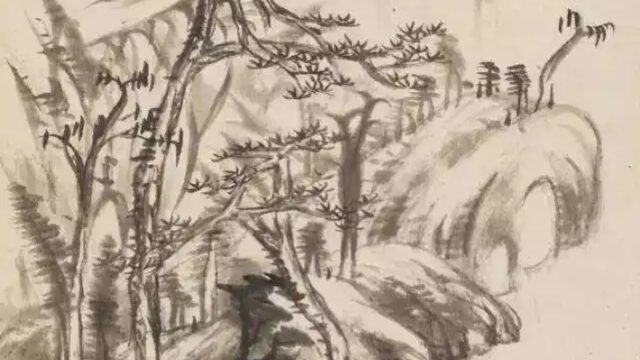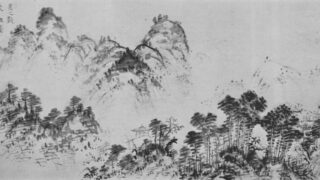「ぬぃの中国文学ノート」にご来訪ありがとうございます。
こちらの記事では、晩清にうまれた『白雨斎詞話』についてみていきます。
晩清(1840~1911。アヘン戦争より後)の文学評論は、すごく深いものがあります。その中でも、こちらの「白雨斎詞話」は、陳廷焯(ちんていしゃく)という人がつくったもので、いままでの詞をひとつの理論で体系的に鑑賞できる――というのがすごいのです。
実は、作品の評論っぽいものは南宋くらいにもあったのですが、そのころはまだ実用的な技がメインなので、どういう作品がいい作品か――みたいなことはあまり書かれていませんでした。
明代くらいになると、それなりに体系化した理論もでてくるのですが、やはり好みの作風に甘いところもあるかな……というのが、やや気になるところです。
清代になると、好みの作風を重んじるというよりも、もっと多くの作品をみていく方にいきますが、まだ理論が完成しません。
そんな中、晩清になっていくと、どんな作風の魅力でもきれいに説明できる理論がつくられていきます。というわけで、その理論とはどんなものなのかを紹介していきます。
重く沈んでわずかに漏れる
まず、詞(妓楼の歌詞)の名品については、こんなふうにまとめています。
詞をつくるときは、深く沈んで重い気分がいい。
詩と詞はひとつの理論の中にあるのだが、すべてが同じわけではない。詩のいいものは、重く沈んでいるものもあれば、古めかしく枯れているものもあり、さらさらと淡く柔らかいものもあり、きらきらと耀くものもあり、ざらざらと大きく痩せているものもある。
でも、詞は短いものが多いので、もし重く沈ませてわずかに漏れるようにしていないと、たとえ技巧をつめこんでいても、どこか薄くみえてしまう。
その“重く沈んでいる”というのは、想いは筆からわずかに漏れているけれど、本音はもっと書ききれないところにあって、冷たく切り離された思いだったり、この世に漂うような気分などが、春の花や秋の草などをみていると、ぼんやり思い出されるようなこと。
それを描くときは、かならずちょっと見えてはすぐ隠れてしまうようにして、そんな気分がたびたび繰りかえし、ついに云いきれずに終わるようなもの。
作詞之法、首貴沈鬱。
詩詞一理、然亦有不盡同者。詩之高境、亦在沈鬱、然或以古朴勝、或以沖淡勝、或以鉅麗勝、或以雄蒼勝。……若詞……篇幅狭小、倘一直説去、不留餘地、雖極工巧之致、識者終笑其浅矣。
所謂沈鬱者、意在筆先、神餘言外、……凡交情之冷淡、身世之飄零、皆可於一草一木發之。而發之又必若隠若見、欲露不露、反復纏綿、終不許一語道破。(いずれも『白雨斎詞話』巻一より)
これはなかなか深い理論だとおもいます。
詞というのは、もともと唐~宋くらいの妓楼などで歌われていた曲についていた歌詞です。なので、どちらかというと、ちょっと俗っぽいような、繊細なような情緒が好まれています。
詩では、枯れているもの(陶淵明)、淡く柔らかいもの(王維)、きらきら耀くもの(初唐の詩)などもありますが、詞では「わずかに愁いをおびて重く沈んでいる味わい」が、どこか妓楼の曲にのぞいている愁い――みたいになります。
あと、すべて吐ききってしまうと、どこか底の浅いものにみえてしまうので、もっと奥に重い気分が溜まっていて、わずかに吐いても慰めきれず……みたいなのが、さらに深みがでてきます。
そして、ここからは様々な作風を、その理論のなかで説明していきます(それがすごく参考になります笑)
重く溜まってぐねぐね折れて――
まずは、北宋の周邦彦(しゅうほうげん)についてです。
周邦彦の魅力は、やはり重く沈んでいてぐねぐねと折れ曲がっているところにある。折れ曲がっているので様々な姿が美しくて、重く沈んでいるのでとても深い味がある。
「六醜・薔薇謝後作」という作品では「遠いたびのうちに、日々が過ぎていくのが空しいのです」という句があって、これが作品の根っこになっている。そこから先は、なんども想いを吐ききれないところがあって、いろいろな風景を書いていき、どろどろと趣きが溢れている。
ほとんどの周邦彦の詞は、それぞれの作品の中に根っこになる句があり、それがみつけられれば、するすると読めてしまうが、それがみえないと繰り返しごちゃごちゃとしているだけにみえる。
其妙処、亦不外沈鬱頓挫。頓挫則有姿態、沈鬱則極深厚。
「六醜・薔薇謝後作」云……「悵客裏光陰虚擲」之句、此処点醒題旨、……下文反覆纏綿、……且有許多不敢説処、言中有物、呑吐尽致。大抵美成詞一篇皆有一篇之旨、尋得其旨、不難迎刃而解。否則病其繁碎重複。(いずれも『白雨斎詞話』巻一より)
これはすごく深い読みこみです。周邦彦の作風は、いろいろな景色がつぎつぎにあらわれる――というものです。なので、どんな気分を描きたいのかが分からないと、いつまでもごちゃごちゃと風景だけが並んでいるようにみえます……。
例として、途中にあった「六醜・薔薇謝後作(薔薇の散ったあと)」というものをのせてみます。
衣を正して酒に臨むに、遠いたびのうちに、日々が過ぎていくのがどこか空しいのです。春を留めたいと思っても、春は鳥のように過ぎていきます。一たび去って跡も残らず、花がどこにあるのかと問えば、昨夜の風雨が、楚王の後宮を散らしたようなのでした。
螺鈿のかんざしの落ちた場所には湿った香りがするようで、ひらひらと桃の道に落ちて、はらはらと柳の路に舞うのです。こんなとき、私はなにを惜しんでいるのかわからず、ただ蜂や蝶ばかりが、窓を叩くほどにざわめくのです。
小さな花びらをひとつ拾ったのですが、それは簪のきらきらした紅碧の房飾りにも似ず、さらさら落ちて――、流れる先には、潮があふれておりますから、わずかな紅に想いを寄せても、きっと深い海の底――。
正単衣試酒、恨客里、光陰虚擲。願春暫留、春帰如過翼。一去無跡。為問花何在、夜来風雨、葬楚宮傾国。釵鈿墮処遺香澤。乱点桃蹊、軽翻柳陌。多情為誰追惜。但蜂媒蝶使、時叩窓隔。 ……殘英小、強簪巾幘。終不似一朵、釵頭顫裊、向人欹側。漂流処、莫趁潮汐。恐断紅、尚有相思字、何由見得。(周邦彦「六醜・薔薇謝後作」)
こちらは春の景色が並んでいるだけのようですが、じつはどれも「遠いたびのうちに、日々が過ぎていくこと」の愁いが、花や春の景色などをみるたびに思い出される――という感じになっています。
底のほうに重く沈んだ気分がありつつ、「昨夜の風雨が後宮を散らしたような」「花びらは簪の房飾りにも似ず、さらさら落ちて……きっと深い海の底――」みたいに、どこか愁いを帯びた風景がつづいていて綺麗です。
そんなわけで、こちらが「根っこに重く沈んだ気分がありつつ、ぐねぐねと様々な姿で折れ曲がり、それでも想いが吐ききれない……」という作風になっています。

沈んだ果てに大きくねじれ固まって
こちらの辛棄疾(しんきしつ)は、重厚でやや荒々しい味わいがあります。さっきの周邦彦とは、かなり味わいが違いますが、こんなふうに評しています。
辛棄疾は、詞の中の龍のような味わいがある。その気はとても大きく激しく、その姿は飛ぶようで、それでいて重く沈んで深くねじれている。
この趣きは、心の中で幾度もぎちぎちと気持ちがねじれ果てた末にでてくるもので、虎のごとく激しい力がある。
辛稼軒、詞中之龍也。気魄極雄大、……姿態飛動、極沈鬱頓挫之致。……是従千回萬轉後倒折出来、真是有力如虎。(『白雨斎詞話』巻一より)
……これはちょっと作品がないとわかりづらいですね。というわけで、短めのものをのせてみます。
梅の花たちが頭上にて咲いて、氷雪は寒い中でひらひらとゆれました。霜の月はさらさらとさして、春の風がどこかで吹くのですが、主人は心深き人にして、江妃の神に恨まれるのも気にせず、最もうつくしき枝を折り取って、冷たい色の壺にさしております。
百花頭上開、冰雪寒中見。霜月定相知、先識春風面。 主人情意深、不管江妃怨。折我最繁枝、還許冰壺薦。(辛棄疾「生査子・重葉梅」)
このぎちぎちと重くて鋭いというか、激しい感情がもつれているような味わいが辛棄疾らしさです(もやもやと春の霞が立ち籠めるような周邦彦とは、かなり違います)
とくに「主人は心深き人にして、最もうつくしき枝を折り取って(主人情意深、……折我最繁枝)」みたいな、重くて激しい感情がどこか滲んでいるのがすごく魅力的です。
これについて、「気はとても大きく、その姿は飛ぶようで――」という評はかなり近いです。ですが、面白いのはすぐ後の「これは心の中で幾度もぎちぎちと気持ちがねじれた末にでてくるもの」です。
主人のちょっと荒いような激しいような表向きの姿は、じつは最も美しい枝をさがして飾りたい……という優美な感情が、ひとときばかりの荒さを帯びるようにねじれて姿を変えたもの――ということです。
ただ荒いだけでなく、むしろわざわざ来てくれた客をもてなしたい――という優美な想いが深く溜まって、それがついに溢れ出て荒々しく激しい趣きができている……というふうに、やはり「奥に深く溜まった気分」を重視しています。
こんなふうに、作風が違っても、その魅力の本質はどこにあるのか――ということを、かなり綺麗に説明できているのが、こちらの『白雨斎詞話』のすごいところなのです。
というわけで、かなり短く詰めこみましたが、詞の魅力は「重く沈んだ気分」にある、という理論はかなりいいと私はおもっています(晩清の文学評論、深すぎですよね……)
ちなみに、この話がすごく合った人として、おなじく晩清の劉熙載がいます(どちらも、想いをどのような形で描くのがいい作品か――をすごく重視しています)

なかなか狭い話題でしたが、お読みいただきありがとうございました。