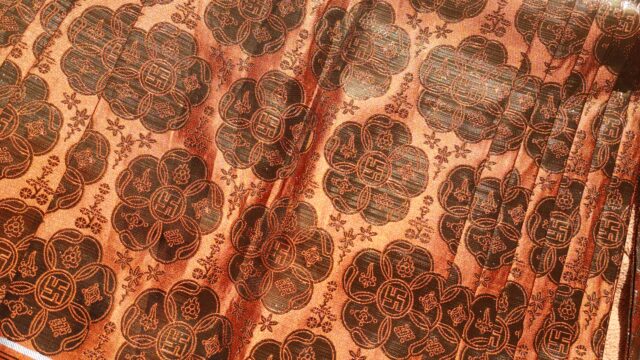「ぬぃの中国文学ノート」にご来訪ありがとうございます。
こちらの記事では、「対聯(ついれん)」という文学について紹介してみます。
対聯というのは、すごくわかりやすくいうと「対句で書かれた詩」みたいなものです。
だいたい宋~清くらいにすごくたくさんうまれていて、日常の場面をおしゃれに描いたような雰囲気がとても魅力的な文学だとおもいます。あと、中国の詩の魅力がぎっちりと短いなかに詰めこまれていて素敵なものが多いです。
というわけで、さっそく紹介していきます。
対句だけで広く深く
対聯は、ほんとうにいろいろな場面でつくられていて、たとえばきれいな風景だったり、新年のお祝いだったり、亡くなった人を追悼するときだったり、座右の銘を対句で書いたり……みたいに、どんなことでもOKです。
そして、対句だけで「広く深く」ものごとを要約したような作品がいい対聯だとされます。すごく古い対聯をひとつのせてみます。
水と天は蒼ひとつで、風月はさらさら――。
(水天一色、風月無辺。)
これ、日本語に訳すと、全然雰囲気が出ないので、すごく困るんですよね……。
こちらは李白が、岳陽楼(湖のちかくの楼閣)にのぼったときに、「一、虫、二」と壁にかかれているのを人々があつまって騒いでいて、これは何だろう……となっていたのを、李白が「これは神仙の文字で“水天一色、風月無辺”とかかれている」としてつくられた逸話があります。
わずか八字で、みずうみと楼の雰囲気がすごくでています。風月は趣きのことです。前半に実際のみずと天をならべたので、後半はあえてみえない「風月(趣き)」みたいなものがでてきて、楼の様子を実際の風景とみえない趣きのふたつからみせていきます。
こういうふうに、微妙にふたつの句が、対になっていながら少しずつずれているのが、広がりと深みを感じさせます(これが対聯っぽさになります)
というわけで、つづいてはいろいろな対聯をみてみます。
対聯の文体
対聯は、宋~清くらいに流行ったので、どちらかというと中国文学の完成期になります。
なので、対聯の中には、それまでのさまざまな様式が入っています。ここからは、そのいくつかを紹介してみます(実際はもっと混ざったようなのもあります)
詩っぽいもの
まずは王道ですが、詩のようなスタイルです。
やわらかい風はそよろと柳の枝をつつみて、淡い月はほんよりと梅の花に迷いけり。
軽風扶細柳、淡月失梅花(北宋・蘇小妹)
この対聯にはちょっと面白いつくり話があります。
あるとき、蘇軾と黄庭堅(どちらも北宋の文人)がふたりで「軽風細柳、淡月梅花」の句があるので、その真ん中にひとつの字をいれて、五文字の対聯にしてみる――という遊びをしていました。
まず、蘇軾が「軽風揺細柳、淡月映梅花(やわらかい風はそよろと柳の枝をゆらし、淡い月はほんよりと梅の花に映えたり)」をつくりますが、蘇小妹(蘇軾の妹。実際にはいない)が「それは微妙ですね笑」といいます。
つづいて黄庭堅が「軽風舞細柳、淡月隠梅花(やわらかい風はそよろと柳の枝に舞いて、淡い月はほんよりと梅の花に隠れけり)」といいますが、蘇小妹は「まぁ、さっきのよりはいいけど、まだ微妙ですね笑」といいます。
蘇軾と黄庭堅は、「じゃあ、どんなのがいいのかね」と蘇小妹にきくと、蘇小妹は「“柳の枝をつつみて、梅の花に迷いけり”なんていうのがいいとおもいます」といいます。
二人はそれをきいて「たしかに春のもやもやと朧ろな雰囲気がよく出ている……」と驚きつつ感心していました。
まぁ、真偽はさておき、五文字or七文字になっていると、詩っぽい対聯になります♪
詞っぽいもの
つづいては、詞のように不規則な形のものです。
大きな江は東に去って、千年の英雄たちを流しつくし、楼外の青山に問えば、山の外には白い雲があって、どこが唐の宮室、漢の宮城だったのか。
小さな院には春がまた来て、鶯は一庭のうららかさを唄い、池のそばの緑樹をみれば、樹を濡らす紅い雨の花で、これが古き世の安らかな日だったのだろうけど――。
大江東去、浪淘尽千古英雄、問楼外青山、山外白雲、何処是唐宮漢闕。
小院春回、鶯換起一庭佳麗、看池辺緑樹、樹辺紅雨、此間有舜日尭天。
こちらも前半で茫々として大きい江のどこか寂しげな感じをかいて、後半でそんな中にもうららかな春がきて……みたいに、ふたつの味わいで季節や月日のめぐりをかいています。
あと「紅雨(紅い花を濡らす雨)」みたいなすごく感覚重視の語がでてくると、すごく詞っぽいです。
駢文っぽいもの
駢文そのものがそもそも対句の塊なので、対聯ってもしかすると駢文の派生ジャンルみたいなものかも……みたいに私はおもいます(笑)
まぁ、そんな話はさておき、駢文っぽい対聯としては、なんとなく四文字の句がたくさん出てくるイメージです。こちらは結婚のお祝いで詠まれたものです。
きらきらとした衣は朝ごとに華やかにして、吳の歌は喜びを歌います。玉梅はおぼろな月にかげりて、朝ごとに鏡の前には粉が散りました。
繡藻新暉、吳歈送喜。玉梅初月、朝鏡修容。(清・王闓運「劉景韓子昏」)
駢文はもともと実用的なことを漢の賦みたいにおしゃれに書いていきたい――ということから生まれましたが、そのおしゃれな対句だけを取りだしているところが、もはや駢文の本質っぽくもみえてきます。
(駢文がほかのジャンルまで飲み込んでいる姿が対聯なのかも……)
中国語っぽいもの
清代くらいになると、しだいに現代中国語っぽいような対聯もでてきます(清代末期の曾国藩はこのスタイルが得意でした)
大きな天はこの楼を潰してしまうことを惜しみ、国中の神工たちをあつめて、ふたたび千年の名勝をつくらせた。ゆえに黄鶴はいまだにこの地に来て、仙人の玉笛を聞いて、長く平安の舞を奉じることを願うのでした。
蒼天不忍没斯楼、全仗那国手神工、再造千秋名勝。
黄鶴依然来此地、願借得仙人玉笛、長吹一片承平。(清・曽国藩「題黄鶴楼」)
「那(あれらの)」「得(~できる)」みたいな現代語っぽい字が入っているのが、こちらのスタイルの特徴になります。半分は漢文っぽいけど、どこか中国語っぽい感じが、なんとなく味わい深いです。
戯文っぽいもの
これはすごく面白いです。(戯文は、ふざけてつくった文章のこと)
海水朝朝朝朝朝朝朝落、浮雲長長長長長長長消。(南宋・王十朋)
なんですか、これ(笑)
じつは、こちらは「朝」が「あさ」「潮(あさの潮)」のふたつの意味があって、「長」も「いつも」「漲るようにあふれる」のふたつの意味があります。なので「海水潮、朝朝潮、朝潮朝落。浮雲漲、長長漲、長漲長消」というふうになります。
がんばって訳すと「あさのなみはあさなあさなになみなみとしてあさになみなみあさにしぼみ、うかぶくもはいつもいつももふもふとしていつももふもふいつもほろほろ」とかですかね♪
慣用句っぽいもの
さらに、古くからの慣用句になっているような有名な一節をつなぎあわせたり、微妙に変えて組みあわせたような対聯もあります。
天のめぐりは狂いなく、わたしの生も丁寧に――。
天行惟健、命事惟醇。(清・八大山人)
こちらの前半はもともと易経の乾より「天行健(天のめぐりは強くして狂わず)」です。
後半は、尚書の説中命より「政事惟醇(まつりごとは丁寧に)」です。
もっとも、すべてを慣用句にせずに、わずかに混ぜるようなこともあります(あと、こちらの対聯は、じつはすごく皮肉が入っています……)

対聯を短くまとめると……
門の左右にかかれている対聯では、さらに短くまとめたものがつくことがあります(門の上にかけられている額で、2~4字が多いです)
それのことを「横批」と呼んでいます。
堤をめぐる柳はあふれるばかりの翠を浴びて、岸の向こうの花は一脈の香りを漂わす。
横批:碧花の川
繞堤柳借三篙翠、隔岸花分一脈香。
横批:沁芳
(『紅楼夢』第十七回より)
もはや「沁芳」が訳に残っていないけど、とりあえず雰囲気で理解してください(笑)
対聯のほうでは、「柳はあふれるばかりの翠を浴びて」が色、「花は一脈の香りを漂わす」が匂いになっていて、ふたつの面から庭園を描いています。
横批では、柳・花などの装飾みたいになっていた川をメインにして、そんな庭園を「碧花の川」みたいなところです――としていきます。
ちなみに、「沁」は沁み出す、「芳」は植物の豊かな香りのことです。こんなふうに、対聯であまり大きく書かれていないことをあえて書いていくのが、いい横批とされています。
というわけで、対聯についてご紹介してみました。対聯があると、庭園の鑑賞ポイントなどもわかって、さらに楽しめることが増えるかもです♪
中国ではいろいろな名所などにもたくさん対聯があって、その場に行ってみないとみられない隠れた名品があったりします(しかも、すごくおしゃれなものが多いです。あと、古典文学などとは違った味わいがあるのも素敵です)
というわけで、対聯の魅力を少しでも感じていただけたらすごく嬉しいです。お読みいただきありがとうございました。