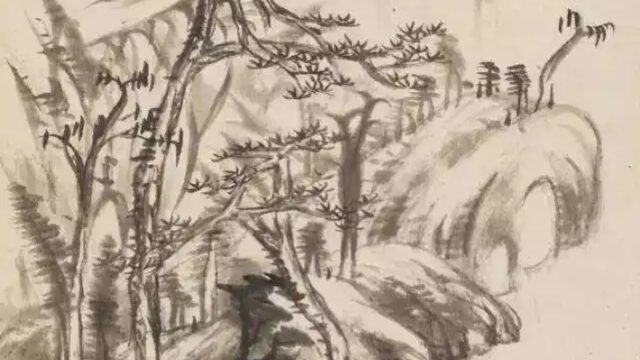「ぬぃの中国文学ノート」にご来訪ありがとうございます。
こちらの記事では、清代の文学について、すごくざっくりとした流れをご紹介していきます。
清って、すごく近い時代なのに、たぶんすごく謎ですよね(笑)私も調べてみるまで全然わからなかったのですが、中国の伝統的な文学は、清において完璧なものになります。
そして、名品もすごく多いので、ぜひ知っていただきたいです。
ちなみに、明~清にかけては“いままでの名品をどのように再現していくか”というのが関心になります。明代は、まだまだ不慣れだったのですが、清代はすごく安定して名品がつくれるようになります。

そして、清代末期になると、その完成された技巧をさらにアレンジしていくことになります(なので、清代末期の文体は、ちょっと変形していて不規則になります)
というわけで、さっそく解説にいってみます。
そこはかとない清代初期
まず、清代初期(1600s中ごろ)の作品についてです。このころは明代末期から生きている人が多いです。
明代末期は、おもに格調説(古い名品をコピーしていく)がいて、その反対派がいて……という感じになっていました(でも反対派の性霊説でも、やはり過去のものを参考にしています)
そんなとき、明がほろんで北から入ってきた満州族の清がうまれます。でも、清ができてから数十年は、こういう混乱期の国はすぐになくなるはず――とおもっている人もそれなりにいました。
なので、一時的に入ってきただけの清に協力するよりも、明の再興を願って待つ――みたいな人たちを、「遺民(いみん)」といいます(遺は“残された”です)
清代初期は、この遺民っぽさがどことなく漂います。明末期からつづいていた古い作品のコピーっぽさの上に、どことない喪失感・虚無感みたいなものが入っているという雰囲気です。
さっと跳ぶ猿を真似しようとして、その苔の深くて滑るのを恐れていれば、木々は深く茂っていて、落ちかけた日が前のほうの林を照らしている――。
欲作飛猱度、不畏蒼苔深。森森開一面、斜日照前林。(王夫之「懐入山来所棲伏林谷三百里中小有丘壑輒暢然欣感各述以小詩得二十九首 其十四 青谿石門」)
東の湖には漁夫がいて、舟をとめて清渓を行く。竿を垂らして秋の雨はふり、わずかに歌って夕陽のかげに入っていく。九月の葦の花は白く、西風がふいて鯉も大きくなっているが、釣糸を垂れてもかならずしも釣れず、釣ってもいつも売るわけでもなく、舟を漕いでは何もいわず、ぎしぎしと遠く下っていく。
東湖有漁父、艇倚清渓瀬。垂竿秋雨中、棹歌夕陽外。九月芦花白、西風鯉魚大。釣亦未必得、得亦未必売。扣之黙無言、鼓枻悠然邁。(邵長蘅「漁父」)
このころの詩って、どこか山僧っぽいなぁ……とか私はおもっています(笑)
ひとつめの詩は、悩んでいるうちにじりじりとまだ明るいけど陽が傾いている感じだったり、ふたつめはものさびしげな秋の夕暮れの、雨なのか晴れているのかわからないところが、すごく虚無的で好きです。
なんか世界がちょっといつも崩れつづけている――みたいな雰囲気がにじみ出ています。それぞれのひとが自分の好みにあわせて、好きな作風を真似していても、それよりも清代初期っぽさがすごくあります。
王漁洋の神韻説
ところで、清代初期に王漁洋(おうぎょよう)というひとが「神韻説」という理論をつくっています。
この「神韻」というのは、詩から漂うなんともいえない不思議な味わいのことです。そして、王漁洋が好んだのは、濡れたような植物がしっとりと静かにあって、ひんやりと落ちついた山中にいるような澄んだ情緒です。それをどこか含みをもたせてふんわりと匂わせるのが「神韻」をおびた詩です。
泰山はひんやりと聳え立って、陰は海に向いて日向はどこまでも陸なので、真ん中に谷の楼があって、峰々は門戸を蔽っているのです。石の壁は天までの井戸のように高く、さらさらとして垂れる蔓草は雨に浸されているのでした。
岱宗趨肅然、陰斉陽則魯。中有夾谷台、連峰作門戸。石壁造天関、蕭蕭緑蘿雨。(王士禛「甕口峡」)
この「ただ美しくて心に浸みる――」というのが、神韻のある詩になります。清代の詩人のなかで、もっとも有名なのはこちらの王漁洋、というほどいい作品が多いです。

清代全盛期の花園
そんなわけで、清代初期が終わっていくのですが、しだいに生まれたときから清代だった人が多くなって、あまり喪失感みたいな感情もなくなっていきます。
そして、いよいよ清の全盛期として、康熙帝・雍正帝・乾隆帝の時代がはじまります。だいたい1680~1800年くらいまではとても安定しているので、文化がすごく豊かになって、作品をつくることをすごく楽しんでいる感があります。
この時期の特徴は、どんなスタイルでも名品だらけ&様式がとても多彩です(もはやぎっしりと花が溢れるように咲いている庭園のような時代です)
格調説
明の格調説は、みるからに唐っぽくする――みたいな極端さもありましたが、清代になってほどよい感じになります。
一峰ごとにその姿はがたがたとして、囲む様子は屏風にも似て、べきべきと割れてはつながり、奇巧は幻のように上下する。聳える石は地霊があらわれたようで、澄んだ明るさは天が削ったごとく、古木は石の隙き間に這うように生えて、清流は石の上を落ちていく。
雲のあいだに石橋をかけて高閣にのぼり、心のひとえに澄むようで、紫の霧が窓より入ってくれば、遠くの碧も霧のごとくゆれていて、がたがたと重なった山の関所にて、遠くの雲をのぞむ心地がするようなのでした。
一峰勢嵯峩、圍抱似屏障。分剨仍聯属、奇巧幻形相。聳峙効地霊、玲瓏斵天匠。古木罅縫生、清流走石上。梯雲上高閣、心目俱一放。紫気欲撲人、空翠同難状。彷彿函関来、曾否向東望。(沈徳潜「後遊攝山詩 其五」)
なんか、いい意味であまりコテコテに唐っぽすぎないのが、すごくバランスがいいですよね(いい意味で無個性というか)
性霊説
明の性霊説は、もはや実際のことをそのまま書く――みたいな、こちらもやや極端なところがありましたが、清代ではほどほどになります。
さらさらとして金鼇(大きい亀)のような山に雨がふり、しとしととして秋の色があふれます。石の路は江のそばで斜めになって、山からの風は馬をひんやり濡らしました。大きい碑はいつの世につくられたものかも知らず、神はこの山に眠るのやら知れず――、ぼんやりと蜀の山川をみわたせば、飛ぶ鳥がひとつ溢れそうな流れに下りていきました。
泠泠鼇背雨、蕭瑟似秋残。石径臨江仄、山風撲馬寒。豊碑何代祭、神物此中蟠。愁望嘉陵棹、飛烏下急湍。(張問陶「金鼇嶺」)
もはや格調説のものと違いがわからないです(笑)
格調・性霊・神韻の三つについて、「料理法・素材・あじ」という喩えがあるのですが、これがすごくわかりやすいとおもいます。
明代の格調説は、もはや調味料ばかりが目立ってしまい、明の性霊説は、もはや素材の味だけで出す……みたいになりがちな気がします。
そんなとき、神韻説で「とりあえずいい味のするものがいい作品なんだよ」というふうになって、清代の格調・性霊説はどちらかというと料理法or素材をおもんじるけど、でもやっぱり味ですよね……という感じになります(笑)
古文
中国の文章は、古文(先秦・前漢くらいまでの古い文体)と、駢文(後漢~六朝の対句の多い装飾文体)のふたつがありました。唐~宋くらいには、駢文の良さもいれた古文がでてきます。
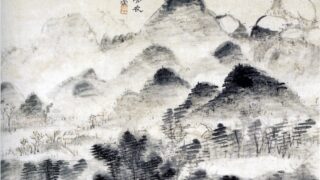
明代の古文は、先秦・前漢がいいor唐宋のものがいい――みたいな派閥がわかれていましたが、清代になると、まぁとりあえず先秦・前漢・唐宋をまぜてもいいのでは……くらいになります。
清代の古文で、そのような折衷型をつくったのは「桐城派」という一派です(安徽省桐城市のひとが多かったので)
双渓から帰って十日ほどのち、披雪の滝にいった。水は西の山から出ていて、東にむかって流れてまわりは石が狭く切り立っている。その狭い中に石が凹んで淵になっており、腹がおおきくて口をしぼんでおり壺のような形をしている。
その壺の中に上から滝がふっていて、滝の水は途中で石にぶつかり、しぶきは霧のように舞いながら、蛇のように折れて雷がながれるように散って、そのまま淵に入っていく。
双渓帰後十日、……観披雪之瀑。水源出乎西山、東流両石壁之隘。隘中陷為石潭、大腹弇口若罌。瀑墜罌中、奮而再起、飛沫散霧、蛇折雷奔、乃至平地。(姚鼐「観披雪瀑記」)
明代では、いかにも見慣れない字や、癖のある比喩などを入れて、先秦らしくしていたのに比べて、やはりすごくバランスがいいです。
対句も「蛇折雷奔」くらいは入れるけど、あまりたくさん埋め尽くさない感じにしておくあたりが、どちらかというと古文っぽいかなぁ……くらいになっています。
駢文
さらに、清代には駢文も上手い人がたくさんでてきました。ちょっと余談になりますが、清代の作者って、かなり学者としても有名なひとが多いです。
駢文はきれいな対句の取りあわせがすごく大事になってくるので、いろいろな字や表現を知っている学者はすごく駢文が得意だったりします。
夜明けの色はまだ起こる前から、天にはしらしらとめぐり明るむ星があり、秋の早風がようやく立ち始めれば、林野にそろそろとあおぎゆらす翳の鳴りて、木々は深い色を冷たく染めていき、さながら山中の鬼もさびしがる頃にして、その音色の流れ溢れてうら悲しきは、わたし一人のための秋にはあらずして……
曙色未啓、天有昭回之星、秋飇乍興、原多凌歴之響。林木幽蒨、欲晤言于山鬼、宮徴離合、非有心于作者。(洪亮吉「録楊起文白雲楼詩序」)
なんとなくフィーリング重視で訳すとこんな感じですかね(笑)
「昭回(しらしらとめぐり明るむ)」みたいな微妙なニュアンスのついた字がすごくいいです。「凌歴」も、凌がひっくり返すようにざわざわとゆれること、歴が白く明るい様子なので、草の裏葉みたいな濁った色が露にぬれてどこか光っているイメージです。
細かい字選びのセンスが、六朝の駢文とくらべて圧倒的におしゃれになります♪

もはやここまでくると、コピー元よりも綺麗だったりします(たぶんですが、いろいろな作品の欠点も分析していたかもです笑)
晩清の文学
さっきのところでもう完成では……と思っているかもですが、じつは清代は晩清(清末ともいいます。1840~1911まで)がとりわけ魅力的なのです。
さっきまでの文学は、どちらかというと机上の技巧でつくられた完璧な世界みたいなものがあります。
ですが、1800年くらいから、しだいに清が傾いてくると、もっと実務的なことが詳しく伝えられるスタイルが好まれるようになっていきます。なので、現実のいろいろなことを描くためには、もっと雑多な語彙や表現があるほうがいい――みたいになります。
(わたしとしては、それぞれの様式を完全にコピーできるようになって、さらに混ぜて用いている晩清こそが、もっとも清らしいなぁ……とおもっていて大好きなのですが笑)
晩清の足音
どことなく清の全盛期は終わったよね……というのが、1800~1840年くらいです。
まず変わっていったのは、桐城派の古文でした。いろいろと実用的な話もするためには、六朝の駢文も入れていくほうがいい――となっていきます(この一派のことを「陽湖派」といいます。陽湖は、江蘇省の地名です)
瑪瑙泉は、さらさらと澄んで鏡のごとく、上にはよく茂った木があり、長い枝は陰をつくっている。小さい池をつくってその泉を引いて水をためる。蓮はさらさらと波にぬれて、ひらひら小さな魚たちは藻を食べていて、その水はさらに東に出ていって、さらさらと石を濡らしていく。
瑪瑙泉……精瑩可鑑、上有佳木、喬枝互翳。鑿方塘引泉盈之。……芙蓉被波、繊鱗唼緑。水溢東出、潺然瀉石。(李兆洛「瑪瑙泉別墅記」)
さっきの桐城派のものとくらべてみると、より細かい風景がふえています。「繊鱗(ひらひら小さい魚たち)」のような細かいニュアンスの入った字も、やや駢文っぽいです。
というわけでしたが、いよいよアヘン戦争があって、清が大きく傾いていきます。アヘン戦争(1840年)より後のことを「晩清(清末)」といいます。
湘郷派
桐城派は、さらに分派をうみだします。それが1800s中ごろの湘郷派です。
「湘」は、中国では湖南省のことなのですが、湖南省うまれの曾国藩がこちらのスタイルをつくったので、この名前になっています。
こちらの湘郷派では、いままでの桐城派よりも実用的なものをめざしています(ここまでは、さっきの陽湖派と同じです)
ですが、陽湖派は駢文っぽさを入れていましたが、こちらの湘郷派ではさらにぎっちりと重々しい雰囲気になります(これは純粋に雰囲気のちがいです)
一月二日、わたしたちは反乱がおきている武漢(湖北省のまち)に向かいました。ですが、一月四日の夜に突如北東からの大風がおこり、荒れた波が激しく立ち、暗い中で騒ぎうねりつづけるほどで、次の日に見てみると、流され沈んだ船は二十二隻、壊れた舟は十四隻に及びました。
さらにその日の昼までに壊れた船も七隻にして、のこっている船もあちこちに傷んで割れて水が漏れて裂け、もしくは舵が折れて綱が切れたものも多く、上下混乱して顛倒するあまり、壊れた船を棄てることしかできず、なんとか無傷だった七十隻あまりを率いて、上流にむかいました。
そのまま武漢に入りて、名ばかりは上流の反乱を鎮めにいったことになりますが、実際は壊れた船を直すためになり……
正月初二日臣等……回救武漢。……忽於正月初四日東北風大作、巨波排撃、終夜喧豗、初五日早査点、漂沈……二十二號、撃壊十四號、延至午刻又破壊七號、其存者亦俱撞損漏裂、柁折纜断。倉卒之間、祗得将壊船委棄、而令略好者七十餘號、全数赴上游。直趨武漢、名為速剿上犯之賊、実則修整已壊之船。(曽国藩「大風撃壊戦船並陳近日飄辦情形摺」)
「喧豗(さわぎぶつかる)」「上犯(上流を荒している)」などのぎっちり詰め込まれたような字が入っているのが、こちらの湘郷派らしさになります。
この重々しくて、ちょっと硬い感じは、漢代の賦によくある“一字一字にかなり重い意味がつめこまれているところ”を学んでつくられています。

漢代の賦では、「嶙峋」で「鱗や筍のようにぎしぎしと連なる石」だったり、「倔佹」で「ぐったりと危なっかしく立っているひと」みたいな、すごく凝った字が入ってきます。
いままでの桐城派は、なんとなくありがちな場面をさらさらとかいていくことはできるけど、もっと細かいニュアンスが入っていて実務的な話をかいていくことをめざしているのが湘郷派です。でも、駢文ふうの装飾になるよりも、もっと重みのあるものとして漢代の賦――ということで、こちらの作風になったような気がします。
湖湘派
なんか名前がまぎらわしいですよね(笑)
こちらの湖湘派は、おなじく湖南省うまれの王闓運(おうがいうん)が、このスタイルで有名だったので、やはり「湘」がついています。
こちらの一派は、六朝っぽいスタイルの詩が有名です(だいたい1800s後半くらい)
もっとも、ただの擬古ではなくて、不穏な時代の憂いを、六朝ふうのちょっと耽美的で物憂げな雰囲気にしていく――というふうに、どこか薄暗いものがふくまれます。
とおい山のなかの楼館は冴えて、夜気は澄みて天はほんのりと翳りたり。庭の蘭は香りうつくしく、月は白々として未だ登らず――。
地遠山館涼、氛澄天宇陰。嘉茲庭蘭秀、遅彼月華臨。(王闓運「辛丑八月十五夜家集聯句」)
この月も上りきらずに、ひんやりとうつくしい夜の気にみたされながらも、どこか薄暗くて重く濁った感情がある――というのが、こちらの王闓運っぽさです。なんか憂いを吐き出しきれずに、内側にもごもごと重くたまっているところが、すごく重厚ですよね……。

同光体
もうひとつ、晩清の詩では「同光体」というスタイルがあります。
こちらは、同治帝・光緒帝のときに流行ったスタイルということになります(1800s後半あたり)。おもに宋詩っぽさの上に、それぞれの人がすきな味わいをいれているのが特徴です。
なので、ちょっと宋詩の「この世界についての考察っぽさ」をおびていることが多いです。しかも、かなり薄暗い雰囲気のものになります。
我の庭には蘭が百本あって、あなたと十年前にもその香りを楽しみました。根を生やしていても地を覆わず、種はなんども落ちて天のたくらみにもあらず――。秋の院はさらさらひんやりと散るようで、その蘭たちはさびしげな色を咲かせるのですが、その薄暗い藪はかげっていて、むかしの香りの縁も霞むようなのでした。
さらさらと流れる秋にむかしのこころも枯れるようで、蘭たちも色を失って歲月が過ぎますので、隣りの屋敷の畹(蘭畑)を訪ねられては、きっとこちらの華たちはどこか青くみえるのかもしれません。
我有蘭百本、同心盟十年。托根不藉地、保種寧非天。秋院肅清蔚、孤英想幽妍。杳然空谷思、濶絶懐香縁。流宕夙心負、衰疾歲月遷。尋芳過鄰畹、予美愁悁悁。(沈曽植「雑詩 其二」)
晩清の荒れつつあるお屋敷がなんとなくうかぶような詩です。あと、「保種寧非天(種はなんども落ちて天のたくらみにもあらず)」とかが、すごく無理やりなつながりの句です。
こういう宋っぽくて、硬く痩せたような風景をえがいていくのが同光体です。
あと、晩清の文学は、いままでの完璧な様式を混ぜたりしているので、どこか不純物が入っていて、くずれたような味わいがあります(むしろ、これこそが清の魅力だとおもいます。完成されすぎて崩れている――みたいな)
というわけで、とても長くなりましたが、清代文学の“様式美のあだ花”みたいな魅力を感じていただけたらすごく嬉しいです♪
お読みいただきありがとうございました。