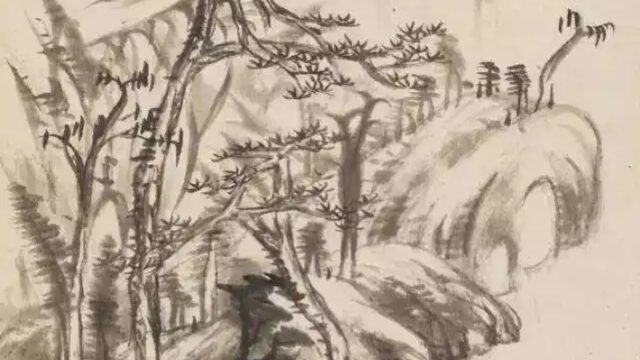「ぬぃの中国文学ノート」にご来訪ありがとうございます。
こちらの記事では、明代の文学について、だいたいの雰囲気をご紹介してみたいとおもいます。かなり謎の多い時代だとおもいますが、なるべくわかりやすく書いていきます。
まず、ひとことでいうと、明清期は「模倣の時代」になります。
宋くらいまでで、おおよその作風は出しきってしまったので、明清期はいままで生みだされた名品をどうすればもう一度作れるのか……ということが、大きな関心ごとになります(爛熟期というか、煮詰まっている感もあります♪)
あと、いろいろな詩派がでてきて理論を練りあげていくのも明清期の風潮です(ちなみに、明は熱気があって、清はすごく冷静な時代です)
というわけで、こちらでは明代のことについて、なるべく簡単にかいていきます。
力にあふれている明代初期
明代初期(1300s後半)は、とにかく力にあふれた作品が多いです。
吾はかの神龍の躍る姿をみたが、天地もそれにあわせて暗くなり明るくなり、龍は大いなる化を司り、その恩恵は四方の海までわたっていた。山を出るときは風も立たず、水にもぐるときも雷はひそんで、とおくの木々は雨を喜び、つやつやと濡れて蘇って茂るのだった。
かの神龍にくらべて、ごそごそと悪さをする蜧蜦(小さい悪龍)は、石の裂け目に巣をつくり険しい山に隠れひそんで、民はその災いを恐れながら、びくびくとしてその姿を窺わされている。
吾観神龍変、天地為晦冥。龍成宰元化、嘉澤浹四溟。出山不飄風、入水無震霆。枯萎仰沾溉、沃若生葱青。豈比蜧與蜦、裂石摧巘陘。俾民挙疾首、抏神蹙眉聴。(劉基「雑詩四十首 其七」)
堂々としていて大きいけど華やかで、威と徳をどっちも兼ねているのが明代初期っぽいです。とくに「水にもぐるときも雷をひそめて――」が、奥にひめた力の大きさを感じさせます。
なんていうか、細かいテクニックというより、内側からあふれ出すオーラみたいなのが、勢いあまって四方の海までひろがって、そのあちこちに岩を砕くほどの力がある――みたいなのが魅力です。あと、この時期の詩人は、かなりの高官になっている人も多いです(実務の間に、その気を吐きだしたような凄さがあります)
きちんとおだやかな台閣体
つづいて、明の前半(1400s)はすごく安定しています。
このころは、「台閣体(たいかくたい)」といわれるスタイルの詩が流行りました。「台閣」とは、宮中の官庁のことです。そういう場で詠まれるにふさわしく、落ちついていて温かみのある詩風が好まれました。
湘水の南あたりの江はゆったりと曲がっていて、春がきても両岸には人もいないようなとき、深い林はとろとろと日がさして鳥の声も止んだとき、山には紅白の花が咲いているのでした。
湘陰縣南江水斜、春来両岸無人家。深林日午鳥啼歇、開遍満山紅白花。(楊士奇「三十六彎」)
さっきまでの明初期が、激しく溢れ出るエネルギーだとしたら、こちらはとろりと溢れる春の日ざしのような、おだやかさです。
ですが、明の1400年代はほとんどこの詩風に染まっていたため、しだいに“もっと他のことを詠んでもいいではないか――”という声もでてきます。
擬古ってどう思う?
というわけで、台閣体ではない詩があっていい――といったのは、1400s後半の李東陽です。
李東陽は「六朝には六朝の詩があり、唐には唐の味わいがあり、宋にも宋らしさがあって、その中でも唐のものは趣きを大事にしているので、表面をコピーするよりも、その趣きを出せるようになればいい」といいます。
がらがらとしてがらがら――、壁をへだてて水車を聞く。がらがら回って水はきらきらとして、昔の故郷に帰ったような。軒のそばには美しい木を植えて、欄のちかくには新しい花があり、一たび回れば枯れた草木をうるおし、二回まわれば塵を濡らしていく……。
咿啞復咿啞、隔牆聞水車。車翻水汨汨、如在東鄰家。當軒理嘉樹、傍檻移新花。一澆潤枯槁、再濯無塵沙。……(李東陽「習隠二首 其一」)
私としては、こちらの「嘉樹・新花(うつくしい木・新しい花)」が、すごくきらきらしている水と似合っている&風景のなかに気分がとけこんでいるのが唐詩っぽいとおもいます。
唐詩の趣きの出し方をまねして、描く風景などは変えていく――というのが李東陽のスタンスでした。そして、李東陽の作品は、こんな感じでほどよく唐っぽい雰囲気もあったのですが、しだいに唐詩を重視するスタンスは偏った方向に流れていきます……。
擬古をしたほうがいい派
まず、唐の詩はいい作品がたくさんあったのだから、唐っぽい雰囲気を真似すればいいものができる――という一派がでてきます(文では、先秦・前漢をほめています。なんかいきなり極端ではありますけど笑)
1500年ごろにでてきた擬古派を「前七子」、1500s中ごろの擬古派を「後七子」といいます。(擬古は、古いものに似せることです)
夜の闇が山寺をつつむころ、しずかな堂にて思いは深く飛ぶようなのでした。灯りはひとつだけ帷(とばり)のうちに燃えていて、さらさらとして外では風が鳴ります。葉はひらひらとあふれるように落ちて、蛍は茂みを多く飛び交わしております。客の部屋からは古い寺が黒々とみえていて、そこから聞こえる鉦の音などをぼんやり聞いておりました。
鼓絶掩山城、空堂思超忽。孤燈明夕帷、悄悄涼風發。落葉何飄蕭、飛蛍互明没。客牕臨古寺、坐待微鍾歇。(何景明「普定」)
「落ち葉は舞うように落ちていて、蛍はもわもわと燃えるごとく飛び、ごつごつとした巌に貼りつくような山寺があって……」みたいなのが、まるで唐詩を絵にかいたような雰囲気です。
つづいては文章についてもみてみます。
鼉磯・大竹・小竹などの島をみていると、海気はもやもやと姿をかえて、峰や丘もつぎつぎ変わっていくのだった。断たれたり繋がったり、丸くなったり四角くなったり、険しくなったり横に延びたり、花のようになっては潰れた粘土のようになり、細くのびたり濃く溜まったり、崩れ落ちたり切り立ったり……。
顧見鼉磯・大小竹諸島、雲気驟変、峰嶼尽改、或断或続、或方或圓、或峻或衍、或英或坯、或陟或密、或墮或隒……。(王世貞「海游記」)
こちらは先秦~前漢をまねた文になります。「坯(つぶれた粘土)」「隒(切り立った岸)」などのあえて見慣れない字を入れているあたりはすごく先秦っぽいです。
もっとも、先秦の文章は、まだ書き方がよくわからないまま無理やり書いていたところもあるので、こういう字しか知らなくてとりあえず使っていた――というのが実際かもですが(笑)
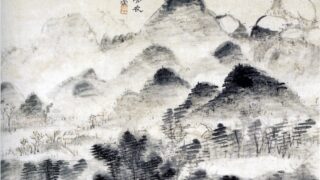
ですが、いかにも先秦ふうのやや小慣れなさも再現できています。
しいて難点をいえば、こちらの擬古派の作品って、どれも落ち葉はひらひらと舞うごとく落ちて、蜃気楼はもやもやのろのろと涌き立つごとく姿を変えて……みたいに、どこか典型的なシーンを誇張している感じになってしまいます。
なので、同じ唐詩でも、こんなふうにすごく微妙なひとときを描いたものはコピーがむずかしいです。
秋の水辺にはいくつもの嶺があって、水車嶺こそもっともうつくしく、天は危うげな石を傾けて、水はやどり木の枝を濡らす。
秋浦千重嶺、水車嶺最奇。天傾欲墮石、水拂寄生枝。(李白「秋浦歌十七首 其八」)
あと、読んでいるとどの作品も、水は躍るように涌き立ち、山はぐねぐねぎちぎちと絡みあい、秋の風はぞよぞよと遠くの草をゆらしている……みたいなものばかりが並んでいて、何をかいても同じになってしまいます。
擬古はしないほうがいい派
というわけで、いい作品はきっと心で感じたままにつくられているのだから、感じたままに書いたほうがいい――という人たちもでてきます(だいたい1500s後半くらい)
春の水にはやわらかな風が波をつくるころ、家々ごとに雪をおびた筍(たけのこ)を煮るころでしょう。こちらの野趣を君子におくれば、きっと西の窓にて楚辞を読みながら召し上がるのでしょう。
縠水温風觧凍時、家家饌得雪玻璃。憑将野意酬君子、飽食西牕読楚辞。(袁宏道「食筍時方正月 其二」)
こちらの作品では、「饌得(食べられる)」だったり「憑将(~によって)」みたいな、どちらかというと現代中国語っぽいものが入っています。あと、擬古派はいかにも山寺では物思いにふける――みたいな内容でしたが、こちらではより実際の生活っぽさをかいています。
ですが、これはこれで作品としての重みが足りないのでは……という声がでてきます(明代の文学って、なんかこの辺りから迷走しているんですよね笑)
唐宋のほうがいい派
こんなとき、さらに話を複雑にするのが「文は、唐宋の古文のほうがいい」という一派です(1500s中盤あたりです)
この人たちは「唐宋の古文は、先秦・前漢をもとにして生まれてきたのだから、そっちのほうが洗練されている。しかも、似せて書くなんてことはせずに、自分の思っていることを何でも書けたので、唐宋の古文はそういうところが魅力だった」みたいな考えです。
(文章はおもに「駢文」と「古文」のふたつがあります。古文は先秦・前漢の古い文体です。駢文は後漢~六朝あたりの対句の多い装飾文体です。唐宋あたりでは、駢文の長所もいれた古文がでてくるので、じつはかなり折衷されているのが唐宋の古文です)
こちらは、唐宋派のひとが、倭寇についてかいたものです。
東南のほうでは、倭寇がいつも襲ってきて、まだ備えが何もできておらず、それでいて連年荒されてばかりなので、その日を支えるのもぎりぎりで、物事を行うにも、あまり先のことなど考えられません。その荒廃ぶりは手と腕のつながりも切られているような壊れぶりでございます。
一年の財は半年で使いきってしまい、のこりの予算は民から毎年取っているほどで、むかし作られた倭寇への備えとして、海沿いの新田開発だったり水寨(水上の砦)などは、もはやできる状態にはありません。ゆえに西北では昔にもどせばいいのでしょうが、東南の沿海では、新たに別のものをつくらなくてはならず、まるで事情も異なっていて――
若東南事体、一則以海寇猝起、事属于草創、一則以連年被寇、力尽于支吾、取辯一切、未慮経久。其大者臂指相使之体統未明。……一年之財只彀半年支用、無名之費百出于民、……祖宗時備倭規制、沿海屯田水寨諸法、漫然無迹可考矣。故西北諸辺、莫急于振旧廃、東南海備、莫急于定新規、此其大較也。(唐順之「与某書」)
唐宋派の人たちって、実際のことを飾らずにかいたものがかなり多いです。あと、唐宋の古文には、実はあまり似ていないです。
もっとも、私の考えでは、李東陽だったり唐宋派みたいな感じのほうが、古い作品との距離感がちょうどいいと思うのですが、明代ってまだ擬古をはじめたばかりなので、ちょっと擬古の加減がわからなかったのかも……という気もしてます(清の擬古はもっとほどよい人が多いです)
こんな感じで、ときどき理論が極端になることもあったけど、いままでの名品を手探りで再現していく熱気にあふれているのが明代です。
ちなみに、明代末期(1600s前半)は、擬古派・反擬古派・唐宋派あたりがそれぞれ残っています。擬古派のほうでは「六朝の駢文もコピーしていいのでは――」という声だったり、反擬古派でも「俗っぽくない感情を描けば、もっと良くなるはず――」みたいなマイナーチェンジが入ります。
なんか話がまとまらないけど、明の文章は、擬古とのバランスにかなり悩んでいた感じがあります。ですが、この流れはつぎの清代において、よりバランスのいいものになっていきます。

というわけで、すごく長くなってしまいましたが、お読みいただきありがとうございました。