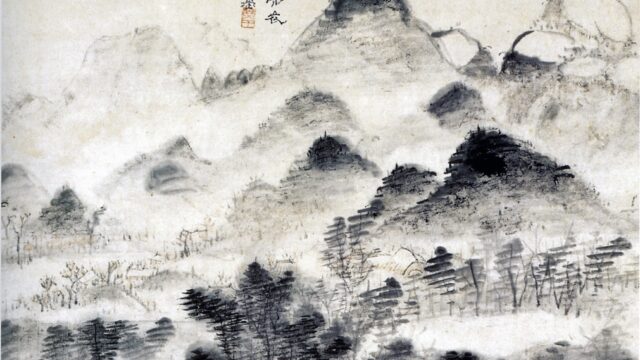「ぬぃの中国文学ノート」にご来訪ありがとうございます。
こちらの記事では、六朝の賦についてになります。
ふつう、賦(ふ)というと、漢代のものが有名です。漢のころの賦は、宮室や祭儀などの王朝をたたえるような作品が多かったです。あと、四文字の句と「○○○兮○○」みたいな楚辞っぽい句がたくさんでてきました。
ですが、六朝になると、もっと個人的な感情をかいた「詩(とくに一句が五文字のもの)」がでてきます。そして、賦はなんとなく詩に似ていることを描くようになります。
あと、六朝のときには、漢賦っぽい句のかたちで、いろいろと実用的な話を書くための「駢文(対句の多い装飾的な文体)」がうまれています。賦もしだいに対句が多くなるということで、六朝の賦を「駢賦(べんふ)」ともいいます。
というわけで、六朝の賦の中から、傑作をいくつかみてみます(今回は、隠れ傑作ではなく、王道の傑作ばかりです笑)
楼にのぼれば
まずは、乱世の悲しみを感じさせる魏のころの賦をみてみます。
この楼に上りて四方をみわたせば、わずかに日頃の憂いを忘れられるかと思えば――、楼はさらさらと流れる水にのぞみて、曲がった池の葦の中洲がみえるのでした。
今の世はごとごとと濁って流れる川に似て、長年をこのように過ごして今に至り、思いは低くねじれて故郷をおもえば、その思いを話すひともなく、ただ欄にもたれて遠くをみれば、路は曲がりてどこまでもつづいていました。獣たちは遠くの野を駆けながら仲間をさがし、鳥は鳴き合いながら飛んでいきます――。
登茲楼以四望兮、聊暇日以銷憂。……挟清漳之通浦兮、倚曲沮之長洲。……遭紛濁而遷逝兮、漫踰紀以迄今。情眷眷而懐帰兮、孰憂思之可任。憑軒檻以遙望兮、……路逶迤而脩迥兮、……獣狂顧以求群兮、鳥相鳴而挙翼。(魏・王粲「登楼賦」)
こちらは、楼にのぼって景色を楽しみたいと思っていたのに、目にうつるのは乱世の色だけで……という作品です。「遭紛濁而遷逝兮(今の世はごとごとと濁って流れる川に似て――)」みたいな句は、いかにも漢魏っぽいです(あまり凝った字は、六朝の賦には出てこなくなります)

自然描写の賦
こちらの作品では、作者の謝霊運が、実際の景色はどうだったのかを解説していきます(笑)
二つの巫湖は結ばれていて、二本の枝は沼をつなげている。近頃つくられた堤はうねうねとして、流れ落ちる泉はさらさら過ぎて、石だらけな山の下には水がめぐり、瀬々の石には流れが過ぎていき……
解説
大小の巫湖は、ひとつの山で隔てられている。その南北を通っている水路は、いずれもほそくて長い。
巫湖は古くてぶやぶやしていたので、近ごろ堤がつくられた。ふたつの巫湖をむすぶ水路はかなり長いため、「流れる泉」といった。そこには大きい石がたくさんあって水は曲がりつつ進むので、「石だらけな山の下には水がめぐる」。
内側の水路は、石を浸すようにして数里ほどあり、水は上から流れていくので、「瀬々の石には流れが過ぎる――」。
本文:二巫結湖、両軿通沼。……引脩堤之逶迤、吐泉流之浩溔。山磯下而回澤、瀬石上而開道。
解説:大小巫湖、中隔一山。……両軿皆長渓。……巫湖舊唐、故曰脩堤。長渓甚遠、故曰泉流。常石磯低而水曲、故曰「下磯而回澤」。裏軿漫石数里、水従上過、故曰「瀬石上而開道」。(南朝宋・謝霊運「山居賦 并自注」)
謝霊運の対句ってすごくきれいなのですが、実際の風景をかなり加工するのが上手いです。
こちらの作品では、「近頃つくられた堤はうねうねとして、流れ落ちる泉はさらさら過ぎて(引脩堤之逶迤、吐泉流之浩溔)」という対句で、大小巫湖の堤と、二つの湖をつなぐ水路が隣り合わせになっています(実際は少し離れています……)
一方で、「二つの巫湖は結ばれていて、二本の枝は沼をつなげている(二巫結湖、両軿通沼)」という対句は、「沼」が大小の巫湖なので、同じ風景をちがう形でみせています。
しかも、ただ無理やりつなぎ合わせているのではなく、“水がつながっている”“曲がって流れる水や堤”みたいに、必ず雰囲気が似ているものを並べているので、様々な趣きがつぎつぎにあらわれて、飽きずに読んでしまいます。
まぁ、そんな小賢しいことをしないでも、十分楽しめる作品ですが(全然作品の話をしていない笑)
民謡っぽい賦
梁の皇族だった蕭繹(しょうえき)の賦です。風景がぬるぬるしてて衝撃でした……。
あなたは十年前に旅にでて、わたしは自らのことを憐れむのです。楼の上から望めば、ただ遠くの樹が霧をおびていて、天と水はまざり合って、山と雲もぼんやりしているような――、山は蒼々として夜にもそびえて、水はさらさらとして揺れているのでした。
秋はいつも月が澄んでいて、その月はどこまでもひんやりと明るいのです。こんなとき、庭の花は露にしおれて、霜は楼のそばを白く染めるので、とおくで秋の水が綾のごとく波立って、秋の雲は薄い絹をかけたようなのでした。
蕩子之別十年、倡婦之居自憐。登楼一望、唯見遠樹含煙。……天與水兮相逼、山與雲兮共色。山則蒼蒼入漢、水則涓涓不測。……秋何月而不清、月何秋而不明。……於時露萎庭蕙、霜封階砌、……重以秋水文波、秋雲似羅。(梁・蕭繹「蕩婦秋思賦」)
この雰囲気は、呉歌・西曲(六朝前期の長江あたりの民謡)だったり、楽府(漢代の民謡)などを混ぜたような感じです。ちょっと田舎っぽい風景を出したり、同じ字をたくさん入れるあたりが、すごくそれです(蕭繹はそういう作風をすごく好みました)

あと、蕭繹の作品って、すごく光や湿度があるのです。たとえば、「秋雲似羅」の“羅(うすい絹)”も、月のひかりを帯びたうろこ雲です。
「山則蒼蒼(山は蒼々として)」も好きです。夜に山がどこか蒼みをおびている感がありますが、ふつう暗い方を書いてしまいそうなのに、わざわざ微妙に“蒼くみえる”なのが、すごく繊細な感覚です。
ごちごちな枯れ木
いよいよ、六朝末期の大家 庾信(ゆしん)です。
風流才子の殷仲文は、掃き出されるようにして東陽郡の太守になり、つねに鬱々として過ごし、庭の槐(えんじゅ)をみて「この樹はボサボサとして、生きる気力が尽きているようだ」と云った。
さて、その樹は、ぎりぎりと膨れねじれて、ごてごてと皮がめくれたように、ある瘤は熊や虎がふりかえるようで、ある瘤は魚や龍が身を屈めているようで、節はぼこぼこと山のように連なり、その紋はのよのよと水が波立つようでした。
これをみて工人たちは驚き目もくらむようで、さりさりと刀や鑿が加えられ、すりすりと鉋(カンナ)や鑚(キリ)が入りました。鱗をはがして甲羅を削り、角を落として牙をそぎ、ひらひらとして錦を裂いたごとく、はらはらとして花びらを重ねたようなのでした。
さて、昔の山河より切り離され、ばさばさと風の中に離別して、根を抜かれて涙を流し、幹を切られて血を垂らして、乾いたウロには火が燃えるほどで、割れた瘤からは脂が吹き出し、洞のそばにて横倒しになって引きずられ、山の踊り場にて転げてあやうく折れかけ、斜めの文様は百抱えほどの太さでも氷のひびが入り、まっすぐな筋も千仞にばきばきと裂けました。
殷仲文風流儒雅、……出為東陽太守。常忽忽不楽、顧庭槐而歎曰「此樹婆娑、生意盡矣。」……乃有拳曲擁腫、盤坳反覆、熊彪顧盼、魚龍起伏。節豎山連、文横水蹙、匠石驚視、公輸眩目。雕鐫始就、剞劂仍加。平鱗鏟甲、落角摧牙。重重碎錦、片片真花。……若乃山河阻絶、飄零離別。拔本垂涙、傷根瀝血。火入空心、膏流断節。橫洞口而欹臥、頓山腰而半折。文斜者百圍冰碎、理正者千尋瓦裂。(北周・庾信「枯樹賦」)
すごい密度です。実は、この作品はほとんどの句に原案になった出典があります。ですが、庾信のすごさはそこからです。
まず、「風流才子の殷仲文は、掃き出されるようにして――」のところで、失意のひとが枯れかけた木をみる場面から入ります。これはもとの話では、ただ、枯れかけた木をみるだけなのですが、庾信はさらに木の来歴などを重ねていきます。
この木は、ぼさぼさとして生気が枯れていて、あちこちを削り取られた跡があったり、瘤ができていたり……というふうに描かれますが、この瘤ひとつひとつが魚龍の胴のようだったり、熊や虎の身体にみえたり……という細部がすごいです。
あと、途中に「昔の山河より切り離され、……根を抜かれて涙を流し、……割れた瘤からは脂が吹き出し――」というのがありましたが、この場面は漢代の民謡で「豫章行」というものがあって、それにすごく似ています。

「豫章行」では、もともと山中に茂っていた大木が、宮室の梁につかわれることになり、枝などを切り落とされていく悲しみをかいています。ですが、庾信はさらに「幹を切られて血を垂らして、割れた瘤からは脂が吹き出し(傷根瀝血、膏流断節)」みたいに、身体をちぎられるようになります(ここは凄まじいです)
庾信は、いろいろな作品を混ぜあわせるようにして、ひとつの場面をすごい密度で書いていく――という作者です。
あと、この作品は、もともと故郷の梁にいたのに、梁が反乱で滅びかけたときに、北のほうの西魏に助けをもとめにいって、かえって西魏が隙をついて梁を滅ぼしてしまい、庾信はそのまま西魏にとどめ置かれて帰れなくなり、しかも何もできなくなった自分のことを詠んでいます……(大学院のときの専門が、庾信についてだったので、ちょっと語りすぎ)
というわけで、六朝の賦の傑作をいくつかのせてみました。まだまだいい作品はあるのですが、ぜひ紹介したいものは書けたとおもいます。
かなり狭くてマイナーな記事になりましたが、お読みいただきありがとうございました。