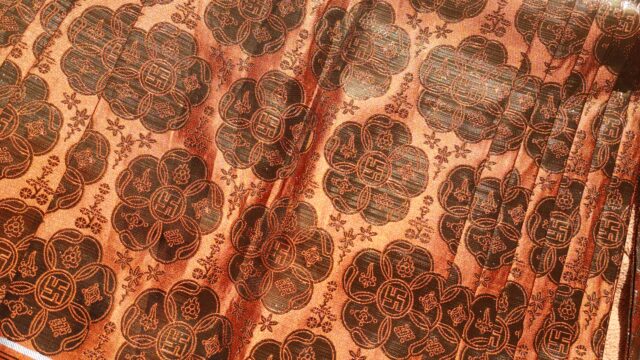「ぬぃの中国文学ノート」にご来訪ありがとうございます。
こちらの記事では、いろいろな記事にのせた作品の訳のなかで、とりわけ私が好きなものを選んでみました。
訳していて、もはや神憑り的な訳ができてしまうことがあり、そういうのはなんで出来たのか私にもわからない……というくらいすごく良いものだったりします(自分で云ってしまう)
というわけで、気に入った訳を厳選してのせてみましたので、少しでも楽しんでいただけたら嬉しいです(こういうときって、何が違うのでしょうね……。一日のうちでも、数時間経つと戻ってしまったりするんですよね笑)
五言絶句
楚山の上
あなたが揚州にいくと聞いて、楚山の上で見送れば、手を腰にまわして見下ろすと、江水はずっと流れているのです。
聞歓下揚州、相送楚山頭。探手抱腰看、江水断不流。(『楽府詩集』巻四十八「莫愁楽」)
とにかく調子が良かったです(笑)この日はなんか神憑っていた気がする。
明月の楼
廬山はぼんやりとして遠い壑(たに)を隠し、灌壘(水をまとった城壁)は中流にあり、城花は飛んで水を照らし、江月は明るい楼にのぼる。
匡山暖遠壑、灌壘属中流。城花飛照水、江月上明楼。(陳・張正見「湓城詩」)
どこかの妓楼の一室で、ぼんやりと暗くなっていく春の山をみているような風景ですかね。ちょっと平安時代っぽい――(前半に見慣れない字がたくさんあって、後半はすごくありがちな風景なのが、すごく綺麗な取り合わせ)
梨のきらきら
枝に接して秋にはつややかに脆く、情を含みて落ちればさらに香る。仙人の掌(て)の上におけば、きっと瑞露(吉祥の露)にきらきらと濡れているのでしょう。
接枝秋転脆、含情落更香。擎置仙人掌、応添瑞露漿。(北周・庾信「奉梨詩」)
これは最後の一句の意訳がすごく気に入ってます(とくに音の並びがすごくきれいに作れて嬉しかったです)
雲のむれ
道中にて雲と出会い、ふわふわさらさらと雷のごとく過ぎていったので、その雲たちは誰に命じられて、もこもこと下っていたのだろうか。
道逢南山雲、歘吸如電過。竟誰使令之、袞袞従空下。(北宋・蘇軾「攓雲篇」)
蘇軾が山中で、雲のむれと出会って、それを竹のはこに入れて持ち帰った話からつくった詩らしいです。こういう作品が、わたしは一番好きかもです(笑)
笛の音
あなたが笛が上手いと聞いて、来てみたら会えなかったので、舟と車で追ってみれば、笛の音が聴けました。
聞君善吹笛、已是無踪迹。乗舟上車去、一聴主与客。(八大山人「安晩冊 十四」)
すごくかわいい詩です。わたしは五言絶句がすごく好きなんだなぁ……とあらためて思いました。五言絶句の魅力は「かわいさ」です♪
五言古詩
潯陽楼
近ごろ永陽群(安徽省)の長官をやめて、また潯陽(江西省)の楼にてのらのろと過ごしておりますが、高い欄にはつめたい雨が降っていて、ほそい城壁は江に濡れております。
こんな雁の音を聞くような夜には、重ねて昔の別れの秋を思い出し、ただ酒などを出しながら、寂しさを紛らわせているだけです。
始罷永陽守、復臥潯陽楼。懸檻飄寒雨、危堞侵江流。迨茲聞雁夜、重憶別離秋。徒有盈樽酒、鎮此百端憂。(韋応物「登郡寄京師諸季淮南子弟」)
やはり注目すべきは「のらのろ」ですかね。これはもともと入力ミスだったけど、すごく気に入った雰囲気だったので、むしろ嬉しい偶然ですね(この擬態語がなかったら、たぶん入らなかったです)
あと、「酒などを飲みながら――」ではなく、「酒などを出しながら――」がいかにも寂しげで好きな表現です。
白馬山
渡しの水は深く澄んでいて、鴻は老いた樹の上に止まる。白馬山も洞天(山中の仙境)にして、昔の人は不思議なことに会ったという。洞門は見えずして、ただ水の声だけが聞えるのだが、山中の道観(道教の寺院)をみながら、舟に乗ったのだった。
長い廊は五つの殿を囲み、二階の閣は山の木々に映えて、そのつくりは大きく高く、ぐるりとめぐって木々に囲まれている。山の上から五つの渓をのぞみ、壺頭山はすぐ近くにあり、古い宮はその北にあって、古い瓦には松の霧がついている。
古い杉は晋の頃よりあるといい、中には住んでいる人がいた。外は四十尺ほどで、内には十人が入れるほどで、私はそのまま瞿仙館に行くと、壇の上には祭儀の色煉瓦が埋め込まれていた。
その下には八方にうねる坡(丘)がつづいていて、一つの亭にて多くの妙景を眺められて、ふたつの山の間に澄んだ沼があり、老木はがちがちと絡みあっていた。前をみれば澄んで遠く、座っていると寒さに襲われる。桃源はみえなくて、どうやら宮の南にあるらしかった。
その山路は深くて暗く、猿などがあちこち上下しており、石のすき間から水がでていて、しばらくそれをながめていたのだった。昔、漁をしていた人が、流れてくる水の先に洞があったというが、いま行ってみればそんなものはなく、道そのものが間違っていたらしい。残念なまま帰ってきて、この遊びも何度もはできず、すでに二十年が経ち、今でも不思議な旅だったように思える。
渡頭何清深、鴻鵠在高樹。白馬亦洞天、昔人有奇遇。洞門不可見、但聞水声怒。瞻彼羽人宅、乃乗方船渡。修廊夾五殿、重閣映千樹。規模象魏壮、回合緑陰護。山椒望五溪、壺頭入指顧。故宮在其北、屋瓦帯松霧。古杉晋時物、中空野人住。外圍四十尺、内可十客聚。我遊瞿仙館、壇上表遺歩。却下八畳坡、一亭衆妙具。両山抱澄潭、老木枝榦互。瞻前秀而迥、坐久凛難駐。桃源独不見、僻在宮南路。山行轉深邃、狙猿紛上下。石竇出微涓、令我意猶豫。昔聞漁舟子、水際見洞戸。今看去溪遠、定自後人誤。惆悵却帰来、此遊不得屢。於今二十年、歴歴経行処。(姜夔「昔遊詩 其九」)
これは素材がいいのです。私はたいして凝った訳をしなくても、そのまま訳せば名品になってしまうというのが近いです(古い杉の穴に住んでいる人が……の一節が、インパクト強すぎです)
洞庭の水
巨魚は大きい壑(谷)を喜び、積まれた水はいつまでも舟遊びをするに良く、千里の池がなければ、孤舟の翔ぶごとき楽しみもなし。
帆を揚げてめぐる風に従いて、浪はざらざらとして東より寄せるので、舲(舟)を横たえて往き来すれば、帆を転じるごとに水面の光は流れけり。軽き雲は上にてひらひらと散り、遠くより飆(風)が大きく茫々とふけば、碧のさざなみは遠くにて煙霞にまじり、夕陽の色はぼんやりと滲むばかりなり。
巴(四川)の丘はのろのろと翠の蘋(浮草)だらけで、波が立ちては揺れもせず、流れに随いて眺めつくせば、黄帝の廟に詣でる暇もなく、からりとして心の開け散るごとくして、秋の日のまだ傾かぬうちにいれば、さらに遊びてどこにいくのか――。ただ古き世の湖をみるのみ。
巨魚喜大壑、積水便修航。不有千里池、豈恣孤舟翔。揚帆順回風、激浪逆東行。横舲往復来、轉帆忽飛光。軽雲上靡靡、長飆浩茫茫。碧漣遠為煙、夕陰秀無央。巴丘延翠蘋、波湧無低昂。随流縦所如、未暇従軒皇。寂寥余懐曠、始見秋日長。行行何所期、攬古慰羈傷。(王闓運「方舟横洞庭」)
ごてごてとして重くて太くてきらびやか――という、すごく独特な美しさがあります。あと、なぜか古い口調で訳したくなります(こういう濁った味わいの美しさを、わたしは王闓運から教わりました笑)
仙境の宝鼎
朝には雲夢のくもの中に立てば、さらさらと青く流れる鏡のようで、糸を垂れて二匹の鯉をつれば、その中には三元の仙境の書が入っていて、その篆字はうねうねと赤い蛇のようで、するする馳せて飛ぶ如くして、帰ってきて天老に問うてみれば、その深き意は窺い得ず――、金の刀は青い帛(きぬ)を裂くようで、その霊書はきらきらとあざやかなのでした。
その霊書のごとく十二の玉を飲んでみれば、忽ちにして仙人の房にあり。ぼんやりと暮れていく上を紫の龍に乗って飛べば、海気はひんやりと肌をさして、龍の子は善く姿を変じて、梅花化粧の娘子(おとめ)となって、私にきらきらとした珠たちを贈れば、その色はさらさら洩れる明月の如し。私にも紅い糸を裳に縫うように勧めて、そのまま二人で手を取りて行けば、下界にはわずかに足音だけが聞こえました。
朝披夢澤雲、笠釣青茫茫。尋絲得双鯉、中有三元章。篆字若丹蛇、逸勢如飛翔。帰来問天老、奧義不可量。金刀割青素、霊文爛煌煌。嚥服十二環、奄見仙人房。暮跨紫鱗去、海気侵肌凉。龍子善變化、化作梅花妝。贈我累累珠、靡靡明月光。勧我穿絳縷、繋作裙間襠。挹子以携去、談笑聞遺香。(無名氏「上清宝鼎詩 其一」)
これは、降霊術の自動筆記でつくられた――とされている詩です……(道教にはそういうのがあります)
もはや説明不要なくらいの不思議さです。中国の作者不明の名品って、どこか飛ぶような流れるようなふしぎな味わいがあります。ちなみに「上清境」というのは、玉清境・太清境とならぶ道教の仙境です。
詞
楚女
楚女は南の水辺に帰っていくときに、朝には雨がふっていて、花はさびしげに濡れている。 小さい舟は揺れながら波をわけて花のうちに入るので、波が起きて、西風がどこかで鳴ります。
楚女欲帰南浦、朝雨、湿愁紅。 小船揺漾入花裏、波起、隔西風。(温庭筠「荷葉杯」)
大正ロマンっぽい温庭筠の詞。終わらせ方がすごく上手く訳せた気がする(こういう感じの詩って、大正時代にけっこうあった気がする)
鳳楼
幾度の鳳楼での宴、今日逢うことは、いままでよりも嬉しく思うのに、この前のことを話したいのに顔をそむけて、眉はあわい春の緑をひそめるのです。 蠟の涙はとろとろ流れて笛の音がさびしいので、衣を整えて唄いたいとおもっても、もう何かめんどくさい気もして、あとひと飲みしたら、なんか心が砕けそうなのです。
幾度鳳楼同飲宴、此夕相逢、却勝當時見。低語前歓頻轉面、雙眉斂恨春山遠。 蠟燭涙流羌笛怨、偷整羅衣、欲唱情猶嬾。醉裏不辞金爵満、陽関一曲腸千断。(南唐・馮延巳「蝶恋花」)
最後のほうの意訳っぷりが、かなり突っ込んでるなぁ……とおもいます(こういうのがいつも出せるといいのですが)
浮翠山房の白蓮
華の仙は連れだって舟遊びして、その肌は波の冷たさに怯え、霜の裳裾を彩る夜には、氷の壺は凝ったようで、塵のひとつもありませんでした。玉の花びらは軽くして、ひらひらと散っていきますから、鏡に臨んで粉を帯びれば、いよいよ白くあでやかでしょう。一片の雲のかかって、その白さを蔽えば、さらに影だけのぞくのです。
菱の間に歌いて、小さきひとの舟に乗りて、蓮の茎の絡むので、雪のうちの鴎や沙の鷺が来れば、夜にはともに寝て、朝にはその寒さに驚くでしょう。酒もなくなって、帯びた粉もわずかに湿り、蓮の色はいよいよ青く白いのでした。この花はきっと、瑶の池にて植えられて、白い蓮ばかりが咲くのでしょう。
蕊仙群擁宸游、素肌似怯波心冷。霜裳縞夜、冰壺凝露、紅塵洗尽。弄玉軽盈、飛瓊綽約、淡妝臨鏡。更多情、一片碧雲不捲、籠嬌面、回清影。 菱唱数声乍聴。載名娃、藕絲縈艇。雪鴎沙鷺、夜来同夢、暁風吹醒。酒暈全消、粉痕微漬、色明香瑩。問此花、蓋貯瑶池、応未許、繁紅并。(李居仁「水龍吟・浮翠山房擬賦白蓮」)
これはすごく難しかったです。とくに悩んだのは「色明香瑩」を「いよいよ青く白いのでした」と訳すところでした。花にあらず人にあらずの微妙な距離感であらわすのがすごく悩みます。
文章
祭江文
隋の開皇九年、元帥は長江の神を祭らせていただきます。この長江は、二つの流れを引きて、九つの枝をもち、四つの瀆(大水)で最も長く、百の川を呑んでおります。晋の永嘉年間よりのちは、天の霊は世を御さずに、呉越(長江下流)に藪のごとく、長年にわたって王朝が代わりました。
そんな中、民は泥と炭に落ちる苦しみに遭い、人も神も怨むことでしたが、此度の平定では、あちらの一方を清めて、多くのものを率いて長江を渡らせていただきます。神霊の助けを得て、無事に渡らせていただければ幸いでございます。
願わくは蛟螭(水龍たち)のしばらく波の内に隠れられて、舟の帳に波穏やかにして、陳を平らげてのちは、海内も泰らかになり、そのときは謹んで祭儀を行い、多くの供物を奉上したいと申し上げます。
維開皇九年、行軍元帥……敬祭南瀆大江之神、……引双流而分九派、長四瀆而納百川。自晋永嘉、乾霊落綱、蕞爾呉越、僭偽相承。……甿庶為其塗炭、人神所以怨憤。忝司九伐、清彼一方、分命将士、乗流南渡、仰憑霊祐、咸蒙利渉。……庶蛟螭竄于洲渚、帷蓋静于波涛、江表克平、海内清泰。謹申礼薦、惟神尚享。(隋・薛道衡「祭江文」)
重々しい六朝末期の骨っぽい作品です。わたしのお気に入りは「願わくは蛟螭(水龍たち)のしばらく波の内に隠れられて、舟の帳に波穏やかにして」ですかね。この格式張った雰囲気がうまく出せてうれしいです。