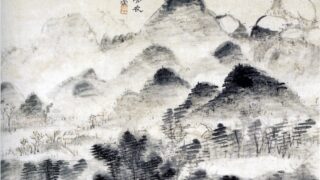「ぬぃの中国文学ノート」にご来訪ありがとうございます。
こちらの記事では、北宋の天才文人、蘇軾についてかいていきます。
もはや私ごときが紹介するのも蛇足な気がするのですが、中国文学のサイトをつくったのに、蘇軾についての記事がないのも何かちがう気がするので、あえてマイナーな作品を中心にいきます。
蘇軾の魅力は、ひとことでいうと「雑多さ」だとおもいます。というわけで、今回紹介するものは、いずれも雑多さを感じさせる作品ばかりになります。
雑多なもの
まずはこちらからです。「春牛」は、立春の日に、土でできた牛(春牛)を鞭でうって、農作物がたくさん取れるように祈るお祭りです。鞭でうって壊れた春牛は、みんなで分けあってお守りにします。
元豊六年の12月27日、夜明け前に、夢で数人の役人がひとつの紙をもってきて、その上には「春牛を祭る文をかいてください」とあった。
わたしは筆を取るとさらさらと一筆書いて「春の景色のすでに至りて、多くの草はあざやかにして、こんな日に春牛を出して、農事がうまく行くのを願う。衣は紅青のうつくしきものを着て、その身は土でできており、祭りが終われば壊れるゆえ、また何も怨まず。」
ある役人は微笑して「最後の“その身は土でできていて……”は春牛を怒らせないか」といったので、その横の役人が「いや、むしろ春牛を悟らせるだろう」と云っていた。
元豊六年十二月二十七日、天欲明、夢数吏人持紙一幅、其上題云:請祭春牛文。予取筆疾書其上、云「三陽既至、庶草将興、爰出土牛、以戒農事。衣被丹青之好、本出泥塗。成毀須臾之間、誰為喜慍。」吏微笑曰「此両句復當有怒者。」旁一吏云「不妨、此是喚醒他。」(蘇軾「夢中作祭春牛文」)
これ、すごく好きなんですよね(笑)
蘇軾は、荘子っぽい雰囲気があって、「人間はこの世界の雑多な変化のひとつとして生まれて、雑多なひとつとして死んでいくのだ」という雰囲気がいつでも流れています。
ここでは、祭りが終わるころには壊される春牛も、雑多な変化のひとつとして作られて、雑多な変化のひとつとして壊れていくのだから、そのことを書いても、怒らせるより悟らせるだろう――という話です。

もっとも、このあたりは他の作者にも多い特徴なのですが、蘇軾らしいのはその前の「三陽既至、……衣被丹青之好(春の景色のすでに至りて、衣は紅青のうつくしいのを着て……)」です。こういう雑多な表面も蘇軾はすごく楽しむのです。
むしろ、この雑多なことこそ、大きい変化のひとつであることなのだから、蘇軾は偏ることを恐れません(笑)
荊門の泉は高いところから流れてきて、石の脈を濡らすように下りてくる。さらさらとして白い瀾を散らして、あちこちで膨らんで崖を飲みこみ、めぐりながら小さい淵になって、その澄んだ色は中の石すらみえるほど――。
注いでいっては細い瀬になり、速く落ちては蛙たちを潤して、初めは一碗ほどもなかったのに、しだいしだいに白布を畳んだようになり、古くの言い伝えでは、この山中の神はものぐさにて仙域より追われ、雨を呼べずに、のろのろと冷碧の気を吐いているという。そして、山前の人たちに、麦や稲をつくらせるに至ったらしい。
泉源従高来、走下随石脈。紛紛白沫乱、隠隠蒼崖坼。縈回成曲沼、清澈見肝膈。潀瀉為長溪、奔駛蕩蛙蟈。初開不容碗、漸去已如帛。傳聞此山中、神物懶遭謫。不能致雷雨、灩灩吐寒碧。遂令山前人、千古灌稲麦。(蘇軾「荊門恵泉」)
ものぐさな山中の神が、雨を呼ぶ力がなくて、仕方なくだらだらと冷たく蒼い気を垂れながしている……なんて、ちょっと俗っぽくすらあるのに、むしろすごく美しくないですか(笑)
仙界の神々すらこんなにも雑多なので、この地にはきれいな流れがあって、しかも山の近くの人たちを潤しているのです、というのが、雑多なゆえの美しさだとおもいます。
詞の天才
もう一つ、蘇軾を語る上で、忘れていけないのは、蘇軾は詞の天才ということです。
詞は、もともと妓楼の音楽などの歌詞としてうまれてきたので、その内容はやわらかく繊細なものがほとんどでしたが、蘇軾はあまり詞で詠まれなかった雰囲気もつくってしまい、しかも詞らしい優美さもあってすごくいいのです(蘇軾以降は、詞の内容も技巧もすごく豊かになります)
高い楼より眺めやれば、遠い空の万里のかなた、雲すら留まらず――。
月の光は澄んで射して、秋の淡い碧の空はひんやりと深いのでした。天上の宮室は、鸞にのって行くべきところ、そんなとき人は清涼の国にいるのでしょう。江山の絵のごとくして、わずかに煙った樹がみえるだけです。
私は酔って歌いたくなり、酒に浮かんだ月とともに、影は延びてわずかに三人だけ――。しだいに舞って風露の下にあそび、今日の夜がいつの夕なのかも知らず。
風に乗って飛んでしまいたいと思うに、はらりと去れば、鵬の大きな翼に乗るまでもなく、水晶の宮にて、どこかで冷たい笛が聞えたのでした。
憑高眺遠、見長空萬里、雲無留跡。桂魄飛来光射処、冷浸一天秋碧。玉宇瓊楼、乗鸞来去、人在清涼国。江山如画、望中煙樹歴歴。 我醉拍手狂歌、挙杯邀月、対影成三客。起舞徘徊風露下、今夕不知何夕。便欲乗風、翻然帰去、何用騎鵬翼。水晶宮裡、一声吹断横笛。(蘇軾「念奴嬌・中秋」)
ちょっと枯れているような、それでいてひんやりと澄んでいるような不思議な詞です。
この詞の一番の魅力は、まるで神仙になって遊ぶかのような「冷浸一天秋碧、……人在清涼国(秋の碧の空はひんやりと深く、人は清涼の国にあり)」みたいな句です。
蘇軾はわずかに一時のこのような気分を、たとえ嘘と知っていても大きく書いてしまいます(清涼の国にいると思っていたつぎの句では「我醉拍手狂歌、挙杯邀月……」のようにふつうに地上にもどっています)
この一時の気分の高く舞うような、明るくて高らかな雰囲気が、乾いているような、それでいて繊細な味わいもあって、すごく新しかったのです(詞の魅力は、繊細さよりも虚実ないまぜなところなのかもです♪)
あと、「今夕不知何夕」は、もともとは春秋時代の「今夕何夕兮搴洲中流(今日はなんていい夜でしょう、川の中洲に舟をうかべて……)」という作品から借りてきたものです。こんなふうに、古い作品から借りた句を入れて詞をつくるのも、蘇軾あたりから始まります。
ちなみに、蘇軾以前の詞については、こちらにいくつか作品をのせています(これはこれで好き)

たくさんの妙
というわけで、蘇軾は偏りをむしろ愛している感がある、というのはなんとなく感じていただけたとおもいますので、その蘇軾の感性の本質がみえるような作品をのせてみます。
四川省眉山の道士の張易簡は、子どもに読み書きを教えていて、天慶観の北極院にてわたしも三年通っていた。海南島に流罪になって、ある夜 夢でそこにいくと、張先生はむかしのように庭の水くれをしていた。
その奥では子どもたちが『老子』の「不思議な世界のさらに不思議なところは、多くの良いものの生まれる場所――」を読んでいるところだった。
私は「良いことはひとつではないのか」というと、先生は「一つではつまらないし、良くもないのだ」といって、遠くで水まきをしたり、草を刈っている人たちを「あれもそれぞれ“妙”なのだ」といった。
私がみてみると、その二人の手は風雨のように草をゆらし、心の霧が晴れるような気がしたので、「妙とはこういうことなのか。牛を捌く名人や、小さな粘土を切る曲芸も、ほんとうにあったのだろう」ともらした。
すると張先生は「それはまだ本当の妙ではない、それは技が入っているのだ。あの蝉や鶏をみていると、蝉は木にのぼってずっと鳴いていて、鶏はいつも餌をついばんでいるが、ふだんの姿はそのようでも、抜け変わったり卵をあたためるときは、聖人の知でも何が起こっているのかわからない。これは技が入っていないものなのだ。」
すると遠くで草を刈っていた二人がちょうど通りかかった。張先生は「すこし待っていれば、私より上の老先生が来るからきいてみなさい」というと、通りかかった二人は「老先生でも知らないかもしれないから、鶏や蝉にきいてみると、きっと満足して天寿を生きられます」といっていた。
眉山道士張易簡、教小学……天慶観北極院、予蓋従之三年。謫居海南、一日夢至其処、見張道士如平昔、汛治庭宇、……其徒有誦老子者曰「玄之又玄、衆妙之門。」予曰「妙一而已、容有衆乎?」道士笑曰「一已陋矣、何妙之有。」……因指灑水、薙草者曰「是各一妙也。」予復視之、則二人者手若風雨、……蓋煥然霧除、霍然雲消。予驚嘆曰「妙蓋至此乎。庖丁之理解、郢人之鼻斫、信矣。」……曰「子未睹真妙、……是技與道相半、……子亦見夫蜩與鶏乎?夫蜩登木而號、不知止也。夫鶏俯首而啄、不知仰也。其固也如此。然至蛻與伏也、……黙化於荒忽之中、……雖聖知不及也。是豈技與習之助乎?」二人者出。道士曰「子少安、須老先生至而問焉。」二人者顧曰「老先生未必知也。子往見蜩與鶏而問之、可以養生、可以長年。」(蘇軾「衆妙堂記」)
これはすごく荘子っぽい話なのですが、荘子がどこか「どうしてそうなったのか分からないまま生きていく」というような、ちょっと振り捨てたような、内向的な感じになりますが、蘇軾はすごく明るくて楽しいんですよね(笑)
雑多にいろいろ異なっているものを楽しむ感性が、ひとときの仙界に遊ぶような詞になったり、もしくは作られてすぐに壊される春牛を飾ることも、その生と壊が隣りあっているのを悟らせることも一つの作品に入っていて、雑多なものがある世界そのものをみているような気がしてきます(それが聖人すらうかがえない不思議な世界なのかもです)
もっとも、蘇軾はこれ以外にも傑作がありすぎて紹介できてないのですが、すごく本質的な魅力はこんな感じだとおもいます。
お読みいただきありがとうございました。