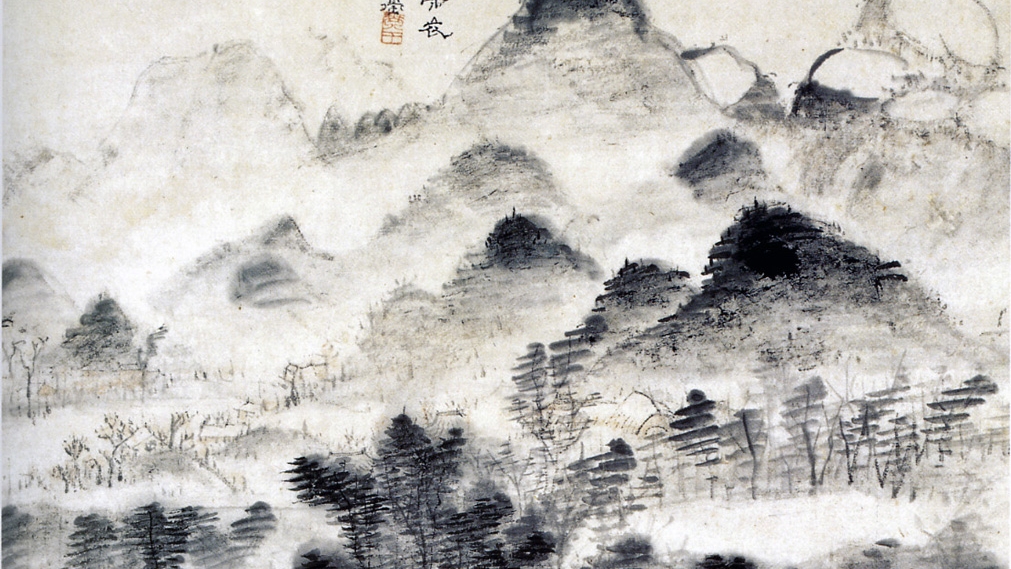「ぬぃの中国文学ノート」にご来訪ありがとうございます。
こちらの記事では、中国の文章の二大流派とされる「駢文(べんぶん)」と「古文」についてかいてみたいとおもいます。
このふたつは、中国の文章(きまった形のある詩歌ではなく、手紙やブログみたいな文章)において、いつも互いにまざりあいながら育ってきたものです。
ちなみに、駢文とは対句を多くいれて飾った文章、古文とは古い時代の飾りのすくない文章のことです。というわけで、さっそくいってみます。
未整理な先秦
まず、先秦において、中国ではまだ文章の書き方があまりきれいに完成されていなかった感じがあります。なので、とてつもなく読みづらいです。
庖丁が文恵君のための牛の解体をみせた。手のふれる様子、肩の傾き、足の曲がり、膝のかがみ方など、いずれもカラカラと刀を走らせるようで、文恵君は「あぁ、技というのはこれほど磨かれるのか」というと、庖丁は刀を置いていう。
「わたしがはじめて牛を捌いたときは、ただ牛の姿がみえるだけでしたが。いまは心で牛を感じるようで、大きいすき間に刃をいれて、大きい穴を通すように、その固まりに合わせていくのです。技は肉の絡みあったところすら引っかからないのですから、大きい骨などにはまず当たりません。
牛の関節にはすき間があって、その刃には薄いので、薄いものをすき間に入れていけば、ゆったりと刀をあそばせるようなものです。もっとも、每回難しいところに来ると……」
庖丁為文恵君解牛、手之所触、肩之所倚、足之所履、膝之所踦、砉然嚮然、奏刀騞然……文恵君曰「譆、善哉。技蓋至此乎。」庖丁釈刀対曰「……始臣之解牛之時、所見無非牛者。……方今之時、臣以神遇、……批大郤、導大窾、因其固然。技経肯綮之未嘗、而況大軱乎。……彼節者有間、而刀刃者無厚、以無厚入有間、恢恢乎其於遊刃必有餘地矣。……雖然、每至於族……。」(『荘子』養生主篇)
これ、すごく原文がおもしろいのですが、表現的にどうみても無理があるでしょ……みたいに云いたいところもそれなりにあります(でも好きです笑)
まず、「技経肯綮之未嘗(技は肉の絡みあったところに引っかからない)」が色々とすごいです。
しつこく訓読すると「技は肯綮(こうけい。絡みあった肉)を経ることの未だかつてせず」ですかね。肯は肉のつなぎ目です。綮は細かい織り目の布です。なので、肉が細かい目の布のように絡んでいるところが「肯綮」です。
しかも、そのあとの「未嘗(未だかつてせず)」は、“いまだに(肉の絡んだ場所にぶつかったことが)ない”です。ちょっと削りすぎです。
さらに、そのつぎの「大軱(だいこ)」はもっと難しいです。軱は、瓜のように大きい歯車のかみ合っているところなので、大きい骨が歯車みたいに絡んでいるところです。
もうひとつ云うと、「每至於族(族に至るごとに)」もちょっと無理を感じます。この「族」は、骨や肉が一族のようにあつまっている……なのですが、なんとなく知っている字で無理やり通じることを願っている感じがします。
こんな感じで、先秦の文章は、じつはまだ書き方が未整理で、あちこち無理して頑張っている感じがあります(これはこれで好きだけど)
文章に慣れてきた六朝
中国で文章の書き方が、なんとなく整理されてくるのは、だいたい後漢くらいです(前漢は、まだいろいろと未整理です)。というわけで、六朝期のものをのせてみます。
陝西省の雁門水はさらに東南にながれていき、曲がって東北にいき、たまって淵になっている。その淵は斜めに長くてゆがんでおり、東北に二十里ちょっとあり、広さは十五里で、葦がたくさん生えている。雁門水はさらに東北で陽門山に入り、これを陽門水といって、神泉水を合わさっている。流れは葦壁の北にでて、そのあたりの水には神霊がいて、雲があっても雨が降らないときや、乾きがひどいときは、ここで雨乞いが行われる。
雁門水又東南流、屈而東北、積而為潭、其陂斜長而不方、東北可二十餘里、広十五里、蒹葭藂生焉。……雁門水又東北入陽門山、謂之陽門水、與神泉水合。水出葦壁北、水有霊焉、及其密雲不雨、陽旱愆期、多禱請焉。(北魏・酈道元『水経注』巻十三 㶟水)
こちらは北魏のころの地理書としてつくられた『水経注』です。これはもともと、川の流れごとにその周りの地形をまとめたもので、かなり実用的な文章になります。
一見すると、すごく不規則にみえますが、実は四文字ずつのリズムがあります。「屈而東北、積而為潭(曲がって東北にいき、たまって淵になる)」などは「而」をいれて、ほどよく字数をのばしています。
「水有霊焉(そのあたりの水には神霊がいる)」「多禱請焉(よく祭祀が行われる)」なども、「焉」でほどよく延ばしています(而・焉はあっても無くても、あまり意味は変わらないです)
あと「蒹葭藂生焉(葦がたくさん生えている)」も、“四文字+焉”になっていて、「藂」は草が聚(集まっている)です。なので、あまり見ない字でも、なんとなく植物がいっぱいあるのかな……くらいは予想できます。
こんな感じで、後漢~六朝くらいに、四文字ずつのリズムができてきます。あと、植物についてはこういう字をもちいる……みたいな感覚も安定してきます(四文字ずつで書くのは、後漢~六朝の駢文がそういう感じでした。駢文では、さらに対句も綺麗に整えるのが大事になります)
あと、「其陂斜長而不方」も、「斜長而不方(斜めに長くてゆがんでいる)」が対句っぽいといえば、ゆるい対句っぽくもあります。

なので、駢文で四文字ずつに整えるのも、ただ形式的なことではなく、意味のまとまりがわかりやすい、という実用的な面もありました(「技経肯綮之未嘗」みたいな不規則すぎる句は、そもそも「未嘗」で終わるというのが予想できないです)
洗練された古文
そして、唐代になっても、まだ駢文はまだ流行っていました。ですが、中唐(安禄山の乱よりあとの数十年)になると、韓愈・柳宗元などが古文を重視します。
ちょっとした手紙や実務的な話すら駢文でかいていると、それほど云うこともないのにわざわざ対句にしたり、無理やり字数を整えるのは、はっきりいってあまり意味がない気がします。
それよりも、話の内容がしっかりと伝わるための書き方をするのが大事なのだから、駢文が生まれる前の内容重視のほうがいい、ということで古文(古い時代の飾りのすくない文章)を重んじるようになりました。
ですが、さきほどのせたように、先秦~前漢(駢文がうまれる前)の古文は、けっこう書き方が未整理だったので、ここで生まれたのは“洗練された古文”になります。
字数や対句にはこだわらないけど、意味のまとまりがわかりやすい&文字の選び方が洗練されている、というのが特徴です。
こちらは、唐の皇帝に即位をすすめるための儀礼的な文章です。こういう場面では、ほとんど駢文が用いられることが多かったのですが、柳宗元はより不規則で自在な駢文になっています。
臣下の申し上げるに、聖王が天にもならぶ皇位を受け継ぐときは、臣はかならず誠を尽し、尊号を献上するのが、形ばかりではなく、その内に礼がある故でございます。一つは天地の神々に告げ、二つめは祖先と農神をまつり、三つめは内外の民を安らかにするためですから、帝位の厳粛さも、廃するわけには参りません。
また、皇家は四方を覆い、祖先の功績も高く、時はいま穏やかにして、帝位にて德をしめすというのは、いままで見てきたことでもあり、古くより記されていることでもあります。
前の世のことを見てみればこのようで、今の世のことを考えてもそのようなのですから、たびたびの占いでも吉祥を告げられ、今日の元旦の日こそ、多くの物の改まるときにして、帝王の大きな礼にもかなう日でございます。
臣某言、伏以聖王之纂承天位也、臣子必竭懇誠、献尊号、安敢為佞、礼在其中。一則以告天地神祗、二則以奉宗廟社稷、三則以安華夏蛮貊。巍巍大称、其可廢乎。……皇家光被四表、祖宗烈文、時當太和、尊号表德、耳目所接、簡牘斯存。稽之於前典則如彼、考之於聖朝則又如此。今亀筮習吉、元正戒期、當品物惟新之時、乃皇王大禮之日。(柳宗元「礼部為百官上尊号第一表」)
いきなり固いものを出してしまったのですが、まず注目したいのは「一則以告天地神祗、二則以奉宗廟社稷、三則以安華夏蛮貊」のところです。こちらは、あえて三つが対句になっていて、ふつうの駢文が二つでまとめるので、駢文っぽいけどより不規則になっています。
そもそも、三つ書きたいことがあるのに、対句にするとどうしても二つずつしか書けない……なんていうのも不便なので、駢文らしさも残しながらの折衷です。
ちなみに「天地神祗(天地の神々)」「宗廟社稷(祖先と農神)」「華夏蛮貊(内外の民)」も、四文字ずつのリズムになっています。
「巍巍大称(巍巍たる大称)」もかなり練り上げられています。「巍巍(ぎぎ)」は高い山がぎりぎりとならぶ様子、「大称」は皇帝の称号です。山の様子を書くときには、山のついた字をいれるのは、漢代の賦にみられましたが、ここでは山のように高い帝位……という雰囲気になります。

「稽之於前典則如彼、考之於聖朝則又如此(前の世のことを見てみればこのようで、今の世のことを考えてもそのようなので)」も、不規則にみえて対句にもなっている――というように、かなり古文っぽい駢文です。
これをみると、駢文のときに生まれた意味のまとまりのわかりやすさなどは残しながら、形式に拘りすぎて内容が伝わりづらい駢文ではなく、より洗練されていて内容もある古文へ、という流れになっているのを感じます。
というわけで、古文と駢文のことについて書いてみました。両方の魅力を感じていただける記事になっていましたら、すごく嬉しいです。
お読みいただきありがとうございました。