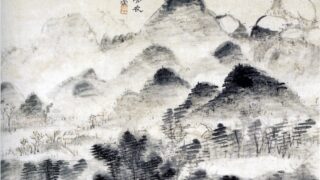「ぬぃの中国文学ノート」にご来訪ありがとうございます。
こちらの記事では、詞牌(宋代の詞の曲)についてかいていきます。もともと、妓楼などで音楽にあわせて歌われていた詞をさらに楽しめるかもなので、ちょっとマイナーな話になりますが、ぜひみていただけたら嬉しいです。
あと、これは今まで他に書いている人をみたことがないので、もしかすると私が勝手に思っているだけのことだったりするかもです(なので、ほどよい感じで聞いてください)
ちなみに、宋詞の大きい流れなどはこちらにまとめてあります。

詞牌について
まず、詞牌(しはい)についてなのですが、宋詞はもともと曲の歌詞だけをつくる――というふうに作られてきたので、曲に合うような音にするのが大事です。
そして、漢字の音を、平声と仄声にわけて(仄:そく。傾くこと)、曲ごとに平声・仄声の配置がきまっていました。
ちなみに、平声は現代中国語の一声・二声で、高く平らにきこえる音です。仄声は、現代中国語の三声・四声の傾いた音と、「楽」「積」「決」などのつまったような音です。
なので、詞牌はこんなふうにあらわされます(こちらは「蝶恋花」という曲です)
中仄中平平仄仄。中仄平平、中仄平平仄。中仄中平平仄仄、中平中仄平平仄。 中仄中平平仄仄。中仄平平、中仄平平仄。中仄中平平仄仄、中平中仄平平仄。
平は平声、仄は仄声、中はどっちでも可です。あと、色が変わっている字は韻をふむところです。あと、同じ曲でも、いくつか違うアレンジのものがあって、わずかに長さや平仄の配置がちがうこともありました。
ちなみに、宋がほろぶと次第に詞もうたわれなくなって、その曲も忘れられてしまうのですが、清代に平仄のならび方だけ復元された、という感じです(曲はよくわからないです)
あと、60字より短いものを「小令」、61~99字くらいのを「中調」、100字より長いのを「長調」といいます(この分け方は、ひとによって少し違うかもだけど)
詞牌の雰囲気
ところで、しばらく詞を読んでいると、なんとなくいつも似たようなところに綺麗な句があったり、みんな間延びしやすいところがあるなぁ……ということを感じます。
たとえば、さっきの蝶恋花を例にいくつかみてみます。
晩い宴はいつまでも池館の夜につづいていて、天の川の傾きかけて、春の光はあでやかなのです。紅と翠の袖は絡むように舞い、香檀の拍子は きんと響いて鴻を驚かせるのです。
明日は花の散るかもしれず、今夜の月は明るいのですから、いつか雨が降るとも限らぬ春に、歌の終わりやすいのを憂いていれば、東の路には楊柳があるばかり――。
密宴厭厭池館暮。天漢沈沈、借得春光住。紅翠鬥為長袖舞。香檀拍過驚鴻翥。 明日不知花在否。今夜圓蟾、後夜憂風雨。可惜歌雲容易去。東城楊柳東城路。(張先「蝶恋花」)
最初の「密宴厭厭池館暮(晩い宴はいつまでも池館の夜につづいて)」がいきなり濃密です。そのあとの「天漢沈沈、借得春光住(天の川は傾きかけて、春の光はあでやかなのです)」はあまり詰め込みすぎてないけど、色はきれいです。
そのつぎの「紅翠鬥為長袖舞。香檀拍過驚鴻翥(紅と翠の袖は絡むように舞い、香檀の木の音は老いた鴻を驚かして――)」も、かなり色が華やかですよね。
後半はあまり風景はかかずに、やや淡いというか、落ち着いた気分になります。この抑揚は、ほかの作者でもみられます。
紫府の天仙たちは名を隠したまま、五色のまだらの龍は、しばらく人の世におりて遊ぶのです。海がいつしか桑畑になった昔も忘れておりますが、仙桃の熟したような春の色。
露が彩りのある旗をぬらして雲をまとったような日に、だれも壺の中に、別天地の歌があるなど知らぬのでしょう。門の外では花が流れていきますので、こんな良き日を惜しまぬようにしたいのです。
紫府群仙名籍秘。五色斑龍、暫降人間媚。海変桑田都不記。蟠桃一熟三千歳。 露滴彩旌雲繞袂。誰信壺中、別有笙歌地。門外落花随水逝。相看莫惜尊前醉。(晏殊「蝶恋花」)
こちらも、まずは「紫府群仙名籍秘(紫府の群仙たちは名を隠したまま下り……)」で、てらてらと艶やかな感じを出しています。
そのあとの「五色斑龍、暫降人間媚(五色のまだらの龍は、しばらく人の世にて遊ぶのです)」はその余韻です。
そのつぎの「海変桑田都不記、蟠桃一熟三千歳(海がいつしか桑畑になった昔も忘れて、仙桃の熟したような春の色)」も、どこか優美で大きい句です。
後半はちょっと色が薄いというか、ひかえめです。
銭塘の満月の一月の夜、月はまるで霜のようで、人はみな画のようで、帳の奥では笙を吹く人、香を焚く人。一つの塵も起こらぬ夜で――。
ひっそりとした山の側では人も老いていくようで、鼓を撃って笛を鳴らす間を抜けて、農神の社に入っていくと、燈も消えかけて霜も下り、ぼんやりと雪のふるような雲ばかり。
燈火銭塘三五夜。明月如霜、照見人如画。帳底吹笙香吐麝。更無一点塵隨馬。 寂寞山城人老也。撃鼓吹簫、乍入農桑社。火冷燈稀霜露下。昏昏雪意雲垂野。(蘇軾「蝶恋花」)
こちらは前半の最初が「燈火銭塘三五夜(銭塘の満月の一月の夜)」で光にあふれています。そのあとの「明月如霜、照見人如画(月はまるで霜のようで、人はみな画のようで)」がその余韻になります。
後半は、一気に暗くさびしいところに出たようで、しんと暗くなります。作品によって雰囲気はちがいますが、前半と後半のつくりなどは似ているのが感じられます。
なので、蝶恋花は、74577・74577ですが、まず前半のほうが華やかで、後半はちょっとひかえめです(むしろ籠もったような余韻があります)。
そして、前半の最初はとりわけ明るく大きく入って、そのあとの二句(45)は余韻を入れて、最後の二句(77)はほどよく華やかにします。後半はちょっと暗く落ち着いた気分です(たぶん)
いろいろな詞牌
というわけで、いくつか有名な詞牌で、どんな盛り上がりになっていたのかを、なんとなく予想してみます(笑)
菩薩蛮
まずは、詞といえば、王道の中の王道といえる「菩薩蛮」からいきます。
哀しげな筝の音は湘水の曲を奏でれば、その声は淡い緑の波に似て、ほそい指が弦にかかりて、その悲しみが漏れそうなのです。 宴のそばの秋水は長く、玉の箏柱に雁が飛ぶような、曲はいよいよ悲しげにして、淡い碧の眉がつまります。
哀筝一弄湘江曲、声声写尽湘波緑。繊指十三弦、細将幽恨傳。 当筵秋水慢、玉柱斜飛雁。弾到断腸時、春山眉黛低。(晏幾道「菩薩蛮」)
こちらは前半(7755)はちょっと落ち着いているけど、後半の5555がかなり詰まったような細かい描写になります。後半にすこし崩れていくような味わい、みたいな。
浣渓沙
つづいては、こちらもすごく有名で王道の「浣渓沙(かんけいさ)」です。
玉の楼にて宴をすれば風に露が乱れているので、髪を直して心を整え酒器を運んでいくのです。もう帰りたいのに何をしているのかわからないのです――。 月の美しき夜にひとり眠れば、酒も醒めてふたつの眉がひそむ心地のして、こんなときには日頃のことがただ嫌いになるのでした。
閬苑瑶台風露秋。整鬟凝思捧觥筹。欲帰臨別强遅留。 月好謾成孤枕夢、酒闌空得両眉愁。此時情緒悔風流。(晏殊「浣渓沙」)
これはちょっと訳がわかりづらいと思うので書いておくと、たぶん妓女の気持ちを詠んでいるのだとおもいます……。
777・777ですが、最初の77は重くて、そのあとの7は余韻でしょうか。後半も、はじめの方が濃くて、しだいに霞んでいくような感じですかね(この包むような余韻がすごくいいです)
踏莎行
さらに、ちょっと変わった形の詞牌をみてみます。
雨が上がって風は明るく、春分の季節に、百の花はその艶やかさを並べていて、新しい燕たちはふたりで飛んで、籠の鸚鵡はさびしさに鳴くころでしょう。 蔓草の壁に這って、苔のあざやかな頃に、青楼のうちではやわらかな声が歌うのですが、ふと昔のことを思うと、どこか眉を縮めたくなったのでした――。
雨霽風光、春分天気。千花百卉争明媚。画梁新燕一双双、玉籠鸚鵡愁孤睡。 薜荔依墻、莓苔満地。青楼幾処歌声麗。驀然旧事上心来、無言斂皺眉山翠。(欧陽修「踏莎行」)
こちらは44777・44777です。そして、最初の44は、前半でも後半でも対句にするとさらにいいです。そのあとは、真ん中の7が大きい風景、そのあとの77が余韻でしょうか。
こちらも前半のほうが色が濃い感じですよね。感情をちょっとのぞかせるのは後半っぽいかもです。ゆっくり春の夕陽が沈んでいくような、どこかのろのろしている感じが詞っぽいです。
玉楼春
最後は、ちょっとマイナーな詞牌をいきます。
鈍い青の水草は漂いて、暁ごとに西湖は春の雨がたまり、燕たちは泥をくわえて飛ぶときに、風は花をわたしの上に散らすのです。 紅い袴は淡い眉たちのうちから引いて、朧の月は帰り道を照らすので、明朝はどこの楼の上で、玉の峰の下の路をみるでしょう――。
青銅貼水萍無数。臨暁西湖春漲雨。泥新軽燕面前飛、風慢落花衣上住。 紅裙空引烟蛾聚。雲月却能随馬去。明朝何処上高台、回認玉峰山下路。(張先「玉楼春・邠州作」)
これは7777・7777なのですが、最初の77は重くて色も濃く、つぎの77はそれなりって感じですかね。後半のはじめの77はそこそこ重くて濃い感じ、おわりの77はやや軽くなります。
この詞牌は、ちょっと独特な重さというか、粘りついて後をひくようなしつこさをどこか感じます(あまり軽いところがないんですよね笑)
というわけで、こんな記事に需要があるのかわかりませんが、もし詞をつくってみたいという方がいましたら、なんとなく参考にしていただければ嬉しいです♪
ここまで読んでいる方がいるのか謎ですが、お読みいただきありがとうございました。