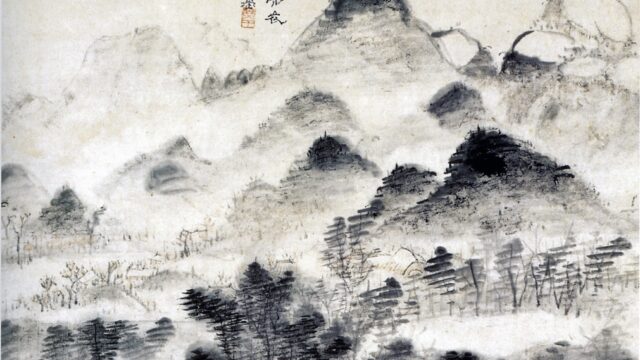「ぬぃの中国文学ノート」にご来訪ありがとうございます。
こちらの記事では、六朝~唐の初めあたりにすごく流行っていた「七言歌行(しちごんかこう)」についてお話していきます。
実は、六朝のときにたくさんつくられていたのは、ほとんどが五言詩(一句が五文字)でした。そして、七言詩(一句が七文字)はほとんど無かったのですが、六朝末期あたりに突然たくさんつくられるようになっていき、唐の初期にもすごく人気になります。
なので、こちらの記事では、そんな七言歌行がどんなふうに生まれてきたか、どんな魅力をもっているかについて、ご紹介してみたいとおもいます。
ちなみに、「歌行(かこう)」というのは、楽府(漢代の民謡)では「○○行」「○歌行」などのように曲名をつけていたので、民謡っぽい作品の七文字verが「七言歌行」になります。

賦の乱(エンディング)と七言歌行
まずは、七言歌行のはじまりについてです。(これはあまり書いている人をみたことがないので、かなりわたしの推測になりますが)七言歌行は、漢代の賦の乱(曲の終わりのみだれて賑やかなところ。七文字のタイプがたまにある)からうまれてきた――とおもっています。
乱にいわく:高く盛られた円い丘は、大きく立ちて天を隠し、登り下りする階段は峛崺(うねうね)ゆれて、大きく埢垣(ごろん)と丸まっている。そんなところに神を招けば、神は来たりて、俳佪招揺(うねうねゆらゆら)として、その霊は迉迡(いにょいにょ)としている。
乱曰:崇崇圜丘、隆隠天(an)兮。登降峛崺、単埢垣(an)兮。……徠祇郊禋、神所依(i)兮。俳佪招揺、霊迉迡(i)兮。(楊雄「甘泉賦」より)
それぞれの句のおわりにある「兮(けい)」は「♪」「~~(語尾の伸び)」だとおもってください。韻をふんでいる字は、現代中国語の音で読み方をかいてみました。これをみると、4+3字ごとに韻をふんでいるのがみえます。
乱にいわく:紅々とした霊宮、きらきらとして空に輝き、ぼんやりとして広がっていく。ごつごつぎちぎちとして、きりきりきしきしと飾られて、並びてごてごてと華やかで、ぐねぐねぎりぎりと曲がって、ぐちゃぐちゃごろごろと絡んで、その横にしずかに傾いていく。からからもこもことして、雲がのよのよ覆うように、ぼんやり暗く霞んでいく。
乱曰:彤彤霊宮(ong)、巋嶵穹崇(ong)、紛庬鴻(ong)兮。崱屴嵫釐(i)、岑崟崰嶷(i)、駢巃嵷(ong)兮。連拳偃蹇(an)、崙菌踡嵼(an)、傍欹傾(ing)兮。歇欻幽藹(i)、雲覆霮䨴(i)、洞杳冥(ing)兮。(王延寿「魯霊光殿賦」より)
今回は意味はあんまり重要じゃない話なので、訳がめちゃくちゃです(笑)こちらは、韻のふみ方がちょっと複雑なタイプですね。4・4・3でひとつの韻で、しかも途中の4・4のところは小さいセットになっています。
ところで、この4・3ずつの組み合わせは兮、楚辞の「招魂」という作品にみられます(些は、兮みたいなものです)
高い堂と深い宮で、欄干は幾重にもかさなって、積み上げられた楼閣は、高い山にのぞんでいる。
高堂邃宇、檻層軒(an)些。層台累榭、臨高山(an)些。
こんな感じで、賦の中でも「乱(終わりの賑やかなところ)」では、けっこう4・3字のセットになる句がでてきます。あと、乱はとりわけ擬態語がたくさんでてきます。
「埢垣(けんえん)」「霮䨴(たんたい)」などの子音や母音が同じ擬態語は、なんとなく音の雰囲気で意味が感じられたりします。「埢垣」だと“ころんと丸くなっている”、「霮䨴」だと“どろどろと溜まっている”みたいな感じです。
なので、漢賦は擬態語がたくさんでてくるのですが、その中でもとりわけ擬態語が多い乱では、さらに擬態語だらけになって、すごく感覚重視(音の手触り重視)なところになります。なんとなく雰囲気で感じて楽しめるのが、乱だとおもってください。
白紵舞の歌詞
つづいての六朝前半では、あまり七言っぽいものは出てこないのですが、晋あたりのときに江南でつくらた「白紵舞歌詞」という作品は、七言歌行っぽい雰囲気になっています。
「白紵舞(はくちょぶ)」というのは、白い紵(からむし)の布をひらひらさせる舞のことです。そして、これが作者不明の隠れた名品なのです。
ふたつの袖のひらひらと上がれば鸞鳳の飛ぶごとく、うすい裾の飄颻(ひらひら)として姿は光をまとい、步くごとに姿は淡い光を流して、弦歌は澄んで春を照らす。人生はたちまち過ぎる電(いかづち)のごとく、楽しいときは少なく、苦しい日は多い。
幸いにして良き日に会いて春の華もあでやかに、舞と曲もつやつやと流れる。……百年の命も傾くごとく過ぎていくので、ぜひ早く燭を取って夜もあそんで、東は扶桑の仙島に行き、西は崑崙の仙城にのぼりましょう。
雙袂斉挙鸞鳳翔(ang)、羅裾飄颻昭儀光(ang)。趨步生姿進流芳(ang)、鳴弦清歌及三陽(ang)。人生世間如電過、楽時每少苦日多。幸及良辰耀春華、斉倡献舞趙女歌。……百年之命忽若傾(ing)、早知迅速秉燭行(ing)。東造扶桑遊紫庭(ing)、西至崑崙戯曾城(eng)。(『楽府詩集』巻五十五「晋白紵舞歌詞 其二」より)
まず、“悲しみの多さを感じたら、ぜひ生きている間の楽しみを大切にして過ごしましょう――”というのが、漢代の楽府とすごく似ています。
そして、一句は七言にみえても、かならず4・3で切れます。たとえば「楽時每少・苦日多」「西至崑崙・戯曾城」みたいな感じです。なので、七言歌行は賦の乱から「兮」を無くしたverにけっこう似ています。
なので、七言歌行は“漢代の賦の乱っぽいスタイルで、漢代の楽府っぽいことを書いている”というのが近い気がしてきます。七言で「歌行(楽府)」をつくっている、みたいな……。
あと、途中の「過・多・華・歌」は、中国語読みすると微妙にちがうのですが、日本語読みすると韻をふんでいます。
六朝後期~唐の初め
そして、六朝後期になってくると、しだいに七言歌行はたくさんつくられるようになります。あと、このときから韻の間隔が大きくなります。
珊瑚挂鏡臨網戸、芙蓉作帳照雕梁。房櫳宛轉垂翠幕、佳麗逶迤隱珠箔。風前花管颺難留、舞処花鈿低不落。(陳・江総「雑曲三首 其二」)
百丈遊絲争繞樹、一群嬌鳥共啼花。啼花戯蝶千門側、碧樹銀台萬種色。複道交窓作合歓、雙闕連甍垂鳳翼。(唐・盧照隣「長安古意」)
これをみると、韻を踏まない句がたまにまざっているのがみえます。さらに「風前花管颺難留」「一群嬌鳥共啼花」などは、「風前の花管は漂いて留めがたく」「一群の嬌鳥は共に花に啼く」みたいに、七文字すべてを主語+述語みたいにしていることがあります。
こんな感じで、六朝末期~唐のはじめあたりには、4・3ではなく7文字という感覚になってきているのがみえます。
七言歌行の完成形
というわけで、七言歌行の最終形とでも云えるような作品を紹介して終わります。
唐のはじめに流行った七言歌行は、「春江花月夜」という傑作を生みだします(こんな作品を、一生にひとつでもつくれたら幸せです)
春江の水は遠く海までつらなり、海上の明月は潮とともに上ってくる。灩々たる波は千萬里まで照らして、いずこの春江に明月なきか。
江はめぐりて中洲の草を浸し、月は花林を照らしてさらさらと雪の散るに似て、空には霜の漂うように明るく、中洲の白沙もかすむようで、江天一色にして塵もなく、こってりと空中にひとつの名月。
江畔の人はだれが初めに月をみて、江月はいつから人を照らしているのか。人生は代々にして終わらず、江月は年々にしていつも似ているのに、江月は人を待っているのかも分からず、ただ長江が流れていくばかりで、白雲は一片 悠々として去り、青い楓は浦の上で愁いをたたえていそうなのだけど――。
春江潮水連海平、海上明月共潮生。灩灩随波千萬里、何処春江無月明。江流宛轉繞芳甸、月照花林皆似霰。空裏流霜不覚飛、汀上白沙看不見。江天一色無繊塵、皎皎空中孤月輪。江畔何人初見月、江月何年初照人。人生代代無窮已、江月年年望相似。不知江月待何人、但見長江送流水。白雲一片去悠悠、青楓浦上不勝愁。……(張若虚「春江花月夜」)
このさらさらと流れるようで、つやつやとしているのが唐の初めらしさです。韻とかは、もうさっきまで書いてきたので飛ばします(笑)
ぜひ注目したいのは「人生代代無窮已、江月年年望相似。不知江月待何人、但見長江送流水」のところです。
漢代の楽府では「人間の一生の中に悲しみがあるのではなくて、悲しみが川のようにながれている上に、人間の一生が浮かんでいる」という感覚が底にながれている――とわたしは思っています。
そして、こちらの作品でも「人の世は代々にして終わらず、江月もずっと空にあって、そんな中、長江はただ流れていく――」のようになっています。さらに、そんな長江のそばでは「青い楓は愁いに堪えられずに……」のように、ほのかな悲しみがあふれています。
春の長江のつややかなひかりに慰められつつ、それでも大きな悲しみの中にうまれていることをどこか感じずにはいられない――という組み合わせが、すごく美しいです。
こんな感じで、七言歌行は、七言だけど楽府っぽい内容をかいている作品だとおもってください(すごく無理やりなまとめ方)。
というわけで、お読みいただきありがとうございました。