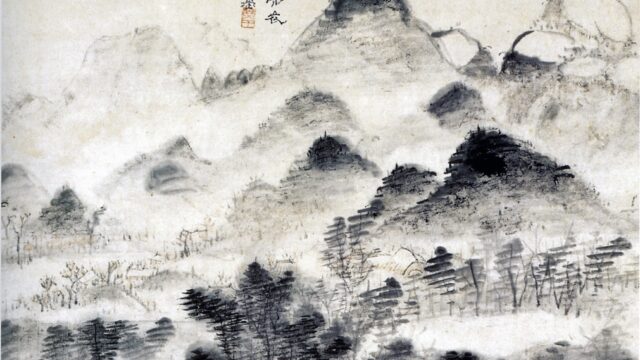「ぬぃの中国文学ノート」にご来訪ありがとうございます。
こちらの記事では、六朝時代のちょっと真ん中あたりにいきていた謝朓(しゃちょう)という詩人についてかいていきます。
後漢のころに生きていく悲しみを無名の作者たちがえがいていた五言詩(一句が五文字の詩)は、三国時代の魏では乱世の不安をえがくようになります。そして、東晋あたりで自然のうつくしさと、それにつつまれている人間も大きな変化のうちにただよっていることなどを書いていきます。
そして、自然のうつくしさの描写をかなり重んじたのが、陶淵明・謝霊運のふたりです(このふたりは南朝宋のころに生きていました)。ですが、このふたりは純粋に自然のうつくしさを描いているというよりは、ちょっと荘子っぽさが多く入っています。

そんななか、南朝宋のひとつあとの南斉(なんせい)になると、謝霊運とおなじ一族に謝朓がでてきます。そして、謝朓は自然描写を受けつぎながら、荘子っぽさはしだいになくなっていきます。
というわけで、さっそくいってみましょう。
つやつやに濡れた霧
まずは、すごく謝朓らしさを感じる作品をみてみましょう。
長江のちかくの山より南京のみやこをのぞめば、白い日ざしは高い甍(瓦)にきらきらとして、参差(あちこちの色)が美しい。残った霞はわずかに綺(綾絹)のようで、とろりと澄んだ江は静かで濡れたいろの生地に似て、鳴く鳥は春の中洲に多く、さまざまな花は若草の小島にあふれる。
去ろうとしていつまでも残ってしまい、悲しいことに宴も終わっていく。良い時はそう何度も得られず、涙は大つぶの玉のごとく流れる。人はみな郷里をおもってしまうのだから、楽しみが終わると身の老いる気すらするのです。
灞涘望長安、河陽視京県。白日麗飛甍、参差皆可見。餘霞散成綺、澄江静如練。喧鳥覆春洲、雑英満芳甸。去矣方滞淫、懐哉罷歓宴。佳期悵何許、涙下如流霰。有情知望郷、誰能鬒不変。(謝朓「晚登三山還望京邑」より)
まず、なんといっても「残った霞はわずかに綾絹のようで、とろりと澄んだ江は静かで濡れたいろの生地に似て(餘霞散成綺、澄江静如練)」がとても美しいです。わずかな霧がとろとろとして絹のように濡れている、なんてすごいセンスじゃないですか……。
すこし前の謝霊運にも「林の色は暮れていく紫を吸いこんで(林壑斂暝色)」のような句はありましたが、謝朓のほうはよりつやめきと輝きにあふれています。あと、江南の水分の多い雰囲気をすごく感じます。
それ以外にも、「さまざまな花は若草の小島にあふれ(雑英満芳甸)」がいいとおもいます。こんな美しい「雑」の字の使い方をほかに知りません(笑)雑多な花が中洲にあふれるように咲いている――みたいに、細かい描写よりも雰囲気を重視しているのがすごく魅力的です。
そして、詩の内容については、謝霊運は「わたしたちは複雑で極まりない変化の中にいて、山水の色をみていると、それをすごく感じるのだ――」というような、どこか荘子っぽい感じだったりします。
ですが、謝朓は「この宴が終わると、さびしさが襲ってきて、ひとえに老いる気すらするのです」みたいな、どこか世俗的な哀楽になっている感があります(これは退化というより、もともとの五言詩は、こういう作風がメインだったので、謝霊運のほうが独特なのかもです)

官人の詩
そして、もうひとつ、謝朓の詩は、謝霊運には入っていないものがありました。それが官人(役人)としての生活です。
高い館は荒れた路にのぞみ、清らかな川は長い陌(みち)がずっと隣りにある。館の上には遠くを思う人、昔を思い出して郷里に帰ろうとする客がいて、庭の池には紅い花が草のうちにまざり、樹のそばには白い花がさいている。日が暮れれば城壁も重々しく、別れの席での思いも切れない――。
高館臨荒途、清川帯長陌。上有流思人、懐旧望帰客。塘辺草雑紅、樹際花猶白。日暮有重城、何由尽離席。(謝朓「送江水曹還遠館」より)
役人としての生活なんて、いい詩の真逆ではないのか――とおもわれるかもですが、これを読むと全然そんなことないです。
こちらの詩でも「庭の池には紅い花が草にまざり、樹のそばには白い花がさいている(塘辺草雑紅、樹際花猶白)」は、やはり遠目からみたぼんやりした色のまざりあいを感じさせる描写です。
ちなみに、ここで送別されている人は、江水曹(水曹は、水の利用などを管理する係です)になります。こんな感じで、送別の宴では、みんなで詩を送りあうことが南斉あたりから慣習になってきます。
そして、みんなで合わせてつくるときは、この作品のように八句でつくるのが基本になりました。さらに「高館臨荒途、清川帯長陌」「塘辺草雑紅、樹際花猶白」などのような対句を入れるのも流行りました。
これをみていると、なんとなく律詩に似ていませんか。実は、律詩はこのときになんとなく生まれた八句でひとつで、しかも対句が入るというスタイルをより洗練させてつくられていきます(律詩は、三・四句めと五・六句めが対句になります)
なので、律詩は役人としての生活での、贈答用の詩から生まれてきたスタイルだったりします。あと、律詩は、それまでの不規則な古詩にくらべて、どこかきちんとしてきれいに整えられている感があります。
謝朓は、そんな初期の律詩っぽいものでも、かなりの名品を残していて、それがいままでの謝霊運や陶淵明との大きなちがいになります。
五言絶句の名手
さらに謝朓は、五言絶句でも魅力的な作品をたくさん残しました。
夕方の殿では珠の簾をおろして、飛ぶ蛍はながれてまた消える。長い夜にひらひらとした衣を縫って過ごせば、あなたをいつまでも思うばかりで――。
夕殿下珠簾、流蛍飛復息。長夜縫羅衣、思君何此極。(謝朓「玉階怨」より)
なんていうか、小さくてかわいい詩です。
もともと、五文字を四句、というスタイルは江南の民謡から生まれてきました。そこでは、おもに恋愛についての作品がたくさんありましたが、謝朓あたりから文人も五文字で四句のスタイルをつくるようになります。
ですが、もともとは恋愛などをえがく民謡から生まれたということで、文人たちもやや素朴な民俗やとろりと柔らかい自然がみえるような感じをめざしてつくっていきます。なので、どこかほんのりと古色をおびた雰囲気になるのが、五言絶句の魅力になります。
(すごく細かい話をすると、南斉あたりから、漢字の音を、高い音と傾いている音にわけて、それを組みあわせてきれいに聞こえるルールなどもつくられていって、唐になってから完成します。絶句・律詩はそのルールが完全に守られているものになります。そのルールを外れている作品は「古詩」といいます。古詩は、長さも音のルールもとくにきまってないです。あと、対句がそれらしくできていれば“律詩っぽい古詩”といったり、絶句のときは“古絶”といったりします)

こんな感じで、唐以降にできあがる律詩(きちんとした様式のある詩)・絶句(民謡っぽさもあるかわいい詩)みたいな区分が、なんとなく謝朓あたりで生まれてきます。
ちなみに、謝霊運を「大謝」、謝朓を「小謝」といって(大小は先輩後輩の順です)、あわせて「二謝」のようにいうこともありますが、このふたりは自然描写を得意としているのは同じでも、けっこう雰囲気が変わります。
謝霊運は、かなり荘子っぽさもあり、それでいて長さも不規則な古詩がほとんどです。一方で、謝朓は、律詩っぽいものが生まれつつもあり、五言絶句を作りはじめていたりして、唐以降の分け方にけっこう似てきます。
こんな感じで、謝朓の味わいを紹介してみました。ちなみに、どうでもいいですが、わたしが初めて六朝のなかで全集を買ったのは謝朓でした。それくらい思い入れが深くて、しかも初めてで謝朓を選んでいるセンスに今さらながらおどろきです(笑)
というわけで、謝朓の魅力をすこしでも感じていただけたらうれしいです。お読みいただきありがとうございました。