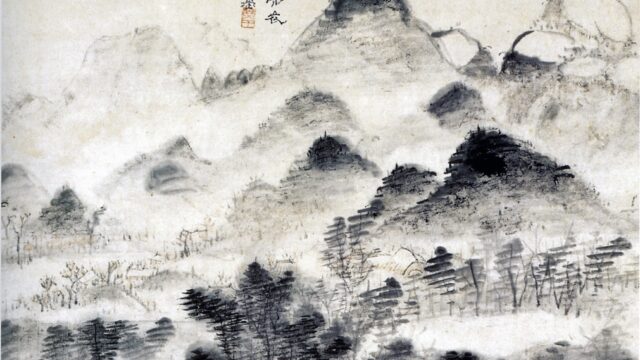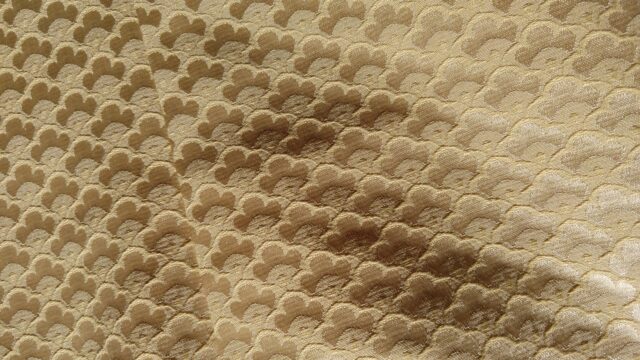「ぬぃの中国文学ノート」にご来訪ありがとうございます。
こちらの記事では、漢代の五言詩についてかいていきます。
漢代の文章といえば賦(楚辞の○○○兮○○のような句形をもちいる長編の作品)が多かったので、いわゆる「詩」といわれてイメージするようなものはまだ表に出てきません。
ですが、だいたい後漢くらいから、一句が五文字の詩(五言詩)がでてきます。そして、後漢の五言詩は、そのころの民謡とかなり似た味わいをもっています。その味わいとは、わたしは「生きていくことの悲しみ」だとおもっています。
この時期の五言詩は、ほんとうに読んでいて泣けるものが多いので、ぜひその魅力をお伝えできるような記事にしていきたいと思います。それでは、作品を紹介させていただきます。
ひとときの楽しみ
ところで、さっき書き忘れてしまいましたが、後漢のころの五言詩の名品は、『文選』の中で「古詩十九首」としてまとめられています。ここから紹介するのは、すべてその古詩十九首からです(すべて作者不詳です)
青々たる墓のそばの柏、磊々(ごろごろ)とした澗(たに)のあいだの石。
人生は天地の間にて、たちまち過ぎる旅のようで、ひとときの宴の酒も、とろりと濃くしておきたいもので。
車にのって馬を走らせて、南都・東都にあそべば、洛中はなんとも鬱々(きらびやか)で、着飾った人たちが挨拶し合う。長い通りは狭い路地をはさみ、王侯の邸宅も多く、ふたつの宮は遥かに望みあい、その高さは百尺にもなる。宴をして心を楽しませて、悲しみを迫らせないようにしたい日です。
青青陵上柏、磊磊澗中石。人生天地間、忽如遠行客。斗酒相娯楽、聊厚不為薄。駆車策駑馬、遊戯宛與洛。洛中何鬱鬱、冠帯自相索。長衢羅夾巷、王侯多第宅。両宮遥相望、雙闕百餘尺。極宴娯心意、戚戚何所迫。(古詩十九首 其三)
……なんだろう、この極度に即物的でドライなのに、人生の悲哀をどことなく感じる世界ですよね。
まず、書き始めがすごくいいのですよね。「青々たる墓のそばの柏、ごろごろした澗のあいだの石」っていうのが、都のすぐ近くには、がさがさと荒涼とした世界がせまっているのに、そこから目をそむけるように都の中の楽しみだけが描かれる感じが、かえってもの悲しいです。
はっきり言って、句の描写力においてはまるで賦の豊かさには及びません。漢代の賦がこぞって描いた宮室や飾りのきらきら感は、「洛中何鬱鬱(洛中はなんともきらきらして)」の一句で終ってしまいます(漢賦のすさまじい描写力についてはこちらです)

ですが、この漂って溢れてやまない悲しみがにじみ出ていることが、漢代の詩の魅力になります。
江を渡って芙蓉(はすの実)をとれば、蘭澤にはきれいな草が多い。これを採って誰に贈るのか、思う人は遠くにいる。かえりみて故郷をのぞめば、長い路はぼんやりとかすんでいて、心を同じくして離れて暮らし、憂いつつ老いていくのです。
涉江採芙蓉、蘭澤多芳草。采之欲遺誰、所思在遠道。還顧望旧郷、長路漫浩浩。同心而離居、憂傷以終老。(古詩十九首 其六)
漢代の詩は、かかれていることとしては「富貴声色の楽しみ、死生離別のかなしみ」だけだったりします。なので、内容はかなり俗っぽいと云ってしまえばそうなるのですが、それ以上に“人間の一生の中に悲しみがあるのではなくて、悲しみが大きな暗い川のようにながれている上に、人間の一生が浮かんでいるのだ”というような気持ちにさせられます。
そんな世界に生きているのだから、たとえどんな楽しみをひととき味わったとしても、もはやそれが俗っぽい快楽だとかではなく、それ以上に大きい悲しみが流れているのだ――という感じです。
この時代の詩って、がらんとして何もない世界みたいな感じがしませんか。こちらの詩の「長路漫浩浩(長い路はぼんやりとかすんでいて)」って、実際の風景描写よりも悲しみの暗い色だけがたまった地をみている気がしてきますよね……。
車を走らせて東北の門より出れば、遥かに北の墓たちをのぞむ。白楊は蕭々(さらさら)として、松柏は広い道をはさんでいて、下にはかつて亡くなった人がいて、杳々として長い夜をすごしている。黄泉の国にてしずかに眠り、千年を経てもめざめることはなく、浩々(からから)として季節は移り、命は朝露のごとし。
人生はたちまち過ぎて、命は金石のごとき固さもなく、萬歲のつぎつぎ過ぎ去って、聖賢すら免れないのだから、霊薬を飲んで神仙にあこがれても、薬を誤ってかえって死ぬものも多い。よき酒をのんで、きれいな服を着て生きるのが一番いいのだろう。
駆車上東門、遥望郭北墓。白楊何蕭蕭、松柏夾広路。下有陳死人、杳杳即長暮。潜寐黄泉下、千載永不寤。浩浩陰陽移、年命如朝露。人生忽如寄、寿無金石固。萬歲更相送、聖賢莫能度。服食求神仙、多為薬所誤。不如飲美酒、被服紈與素。(古詩十九首 其十三)
こちらの詩にも「浩浩陰陽移(からからとして季節は移り……)」の「浩浩」がでてきました。さらに「蕭蕭(さらさらともの寂しく木がゆれること)」もでてきます。浩は大きくて果てのない水の流れです。
世界は悲しみのながれの底にあって、いつでも枯れていくような木々の色がのぞいている……というのが、やはり通じていますよね。
どうでもいいけど、私は着飾ったりする楽しみを感じていいのだろうか……、それは薄っぺらい下らないことなのではないか……みたいに思ったりしたこともあったけど、この世に生きているのがもはや誰でも深い悲しみの中にいるのかもしれない――と感じるようになって、そういう考えに引っかからなくなりました(なので、生きている間はぜひ楽しむべきです笑)
鳥の悲しみ、木の悲しみ
一句が五文字のスタイルは、漢代の民謡にもみられると紹介しました。なので、ここからは民謡のほうから私が好きなものをのせてみます。
ちなみに、これらの民謡は「楽府(がふ)」とよばれています。もともと、漢代には民謡をあつめてくる役所があって、それが楽府といったのですが、しだいに民謡そのものが楽府とよばれるようになっていきます。
楽府は、より民間っぽいというか、ちょっと田舎っぽい風物などがでてきます。たとえばこんな感じです。
白楊ははじめて生まれたとき、豫章(江西省)の山にあって、上の葉は青い雲までとどき、下の根は黄泉まで通じるほどだった。
ひんやりとした八九月、山客が斧をもって入ってきた。わたしの……は皎々(きらきら)として、若い芽は切り落とされていく。根や株は断ち切られて、岩石の間にたおされる。工匠は斧をもって、鋸で切り両端をととのえる。山から下りて四五里をすべり、枝葉はばきばきと折られていく。川までくると船に積まれて、身は洛陽宮にあって、根は豫章の山にのこっている。
多くの枝葉がちぎられて、またつながることもなく、わたしは百年を生きて、どうしてか多くの手によって、根株から切り離されてしまったのか。
白楊初生時、乃在豫章山。上葉摩青雲、下根通黄泉。涼秋八九月、山客持斧斤。我□何皎皎、稊落□□□。根株已断絶、顛倒巌石間。大匠持斧縄、鋸墨斉両端。一駆四五里、枝葉相自捐。□□□□□,會為舟船蟠。身在洛陽宮、根在豫章山。多謝枝與葉、何時復相連。吾生百年□、自□□□俱。何意萬人巧、使我離根株。(『楽府詩集』巻三十四「豫章行」より)
ちょっと欠けている字が多いのですが、それでも名品とわかるだけの味わい深さです。山中の大木の気持ちになって、この世界がただよく分からない運命に流されているだけ――という悲しみを感じさせます。
個人的には、終わりの「何意萬人巧、使我離根株(どうしてか多くの手が、根株から切り離してしまったのか)」が、運命がひたすらがたがたと苦しいことへの嘆きを感じて泣けます。
もうひとつ、すごく好きな一篇をいきます。
夫婦の白鳥が飛んできて、西北から十々五々と列をなして飛んできた。妻が病気になってしまい、一緒にいくことができなくなり、五里にしてふりかえり、六里にしてうろうろとして、咥(くわ)えて飛んでいきたいけれど、そんなに口も開かないし、背負って飛んでいきたいけれど、そんなに羽ももたないだろう。
楽しいことは新たな出会い、憂いを生むのは別離のことで、ためらいつつ群れをみて、涙をながしてどうしていいかもわからない。君と別れることを思うと、胸がつかえて何も言えず。
それぞれ無事にすごしてください、遠い道はいつ帰るのかもわからないですし、私はここで一人で巣を守り、門を閉ざして鍵をかけて待っています。もし生きていたらまた会いましょう、亡くなっても黄泉にて会いましょう。そして、今日を最後に楽しんで、いつまでも生きていたいと願うのです。
飛来雙白鵠、乃従西北来。十十五五、羅列成行。妻卒被病、行不能相随。五里一反顧、六里一徘徊。吾欲銜汝去、口噤不能開。吾欲負汝去、毛羽何摧頹。楽哉新相知、憂来生別離。躊躇顧群侶、涙下不自知。念與君離別、気結不能言。各各重自愛、遠道帰還難。妾當守空房、閉門下重関。若生當相見、亡者會黄泉。今日楽相楽、延年萬歲期。(『楽府詩集』巻三十九「艶歌何嘗行」より)
最後の一段は、たぶん妻鳥の気持ちです。
この吹き荒れている冷たい風が、浩々として陰陽を移らせて、白楊を蕭々(さらさら)とゆらしているような風だったり、夫婦の鳥たちが飛んでいる風なのかもですね……。最後の「今日を最後に楽しんで……」って、いかにも悲しみの上にわずかに浮かんだ楽しみです。
(ちなみに、楽府は六朝期の文人にとってすごく魅力的だったらしくて、楽府っぽい作品をまねしてつくることも流行りました)
というわけで、後漢のころの五言詩の魅力をご紹介してきました。ちょっと暗い作品も多くなってしまいましたが、この味わいはすごく好きなので、悲しみの多さを感じたら、ぜひ生きている間の楽しみを大切にして過ごしましょう♪(こういう話だっけ……)
お読みいただきありがとうございました。