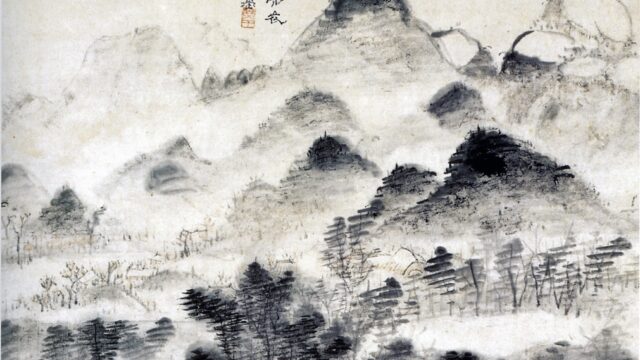「ぬぃの中国文学ノート」にご来訪ありがとうございます。
こちらの記事では、六朝時代にたくさんつくられた「志怪小説」についてかいてみます。すごく個人的な話なのですが、高校のときの教科書で「白水素女」っていうお話がのっていて、あんな感じのふしぎな物語をイメージしてもらえると近いです。
もっとも、わたしは六朝志怪はそんなに詳しくないので、せいぜい私の感想くらいに読んでいただければいいのですが、なんとなく「道教ふうの民間伝承」っぽい世界だなぁ……とおもっています。
というわけで、ちょっと道教について解説をして、わたしがとりわけ気に入っている話をいくつか紹介してみます。
道教について
道教というのは、もともと先秦~漢くらいにあった神仙思想(不老不死をめざすために神を祭ったり、霊薬をさがしたり、海の上の霊山をめざしたりする。山東~遼寧省あたりで生まれました)から発展してきたものです。

もともと神仙思想は一人一流派みたいなところがあり、ぜんぜんきれいに体系化されていなかったのですが、六朝期になるとしだいに位の高い神々の名前がきまってきて、それが「道教」になり、まつる人は道士(道教の僧侶)とよばれるようになります。
ですが、そのようにまとめられたのは上位の神々だけで、土着の神々だったり、地域の伝承だったりは、わずかに道教の体系に入れられながらも、いままでどおりの土着の香りを残しています。そんな土着のふしぎなことが描かれているのが六朝志怪(志は「誌」と同じで、怪異の記録ということ)……みたいに感じています。
天の川の槎
というわけで、土着の民間信仰と、道教の体系がまざりあったお話をいくつかいってみます。
古い言い伝えでは「天の川と海はつながっている」といわれていた。近ごろ、海のそばで暮らしている人がいて、毎年八月に槎(いかだ)が遠くにあらわれることに気がついた。
この人はあることを思いつき、槎の上に家をつくって、食べ物を積んで、漕ぎ出していった。十日ほどの間はまだ星がみえたが、そのあとは茫々忽々(ぼやぼや)として昼夜もわからないようになって、十日ほどして、ある場所にたどりついた。
そこは高い城壁があり、家もしっかりとしていて、宮中に布を織る女性が多くいるのがみえた。そんなとき、ある牛飼いがいて、その人をみると驚いて「どうやって来たのです?」と問うので事情を話して、ここはどこかを訊いた。
その牛飼いは「帰って蜀(四川)のほうにいって、厳君平(占いの名人)にきくとわかるだろう」と答えたので、岸には上がらず、そのまま帰った。のちに蜀に行って厳君平にきくと「ある年の○○日に流れ星が牽牛(ほこぼし)のあたりを通った」というので、調べてみると、その人が天の川にいたときに重なっていた。
旧説云「天河與海通。」近世有人居海渚者、年年八月有浮槎去来不失期。人有奇志、立飛閣於槎上、多齎糧、乗槎而去。十餘日中、猶観星月日辰、自後芒芒忽忽、亦不覚昼夜。去十餘日、奄至一処、有城郭状、屋舍甚厳、遥望宮中多織婦。見一丈夫牽牛渚次飲之、牽牛人乃驚問曰「何由至此。」此人具説来意、并問此是何処。答曰「君還至蜀郡、訪厳君平則知之。」竟不上岸、因還。如期後至蜀、問君平、曰「某年月日有客星犯牽牛宿。」計年月、正是此人到天河時也。(『博物志』巻十より)
道教には占いなども入っているので、厳君平もそこにつながりそうですが、むしろ主役はふしぎな古伝承のほうです(この話、不思議で大好きなんですよね。とくに、空の「茫々忽々」が風情あります)
洞庭山
洞庭山は水の上にあって、その下には金堂が数百間にわたって広がっており、玉女がそこには居て、いつでも管絃の声が聞こえて、山頂までとどいている。その山には霊洞もあり、薬や石を取りに入った人が、行くこと十里にして、からりと天は高く霞も光っていて、花や柳も茂り、楼閣もきらきらとして、外の世界とはまるで異なっていた。
洞庭山浮於水上、其下有金堂数百間、玉女居之。四時聞金石絲竹之声、徹於山頂。……其山又有霊洞、……採薬石之人入中、如行十里、迥然天清霞耀、花芳柳暗、丹楼瓊宇、宮観異常。(『拾遺記』巻十より)
こちらは、道教にでてくる「洞天(山中の洞の奥には、別天地のような大きな仙境がある)」を感じさせます。有名な「桃花源記」も、ちょっと洞天っぽさがある気がします……。ちなみに、「薬や石を取りに……」も、たぶん不死の仙薬の材料です。
蠱毒の家
滎陽郡(河南省)に廖氏という家があり、その家では代々「蠱」をつかって富を得ていたが、新しく嫁いできた妻には、そのことを話さずにいた。あるとき、家の人がみんな出かけてしまい、この妻が一人で留守番をしていた。
そんなとき、たまたま大きい甕があるのに気がつき、開けてみたところ、中には大きい蛇がいた。その妻は湯をわかすと蛇にかけて殺してしまい、家の人が帰ってくると、妻はそのことを話した。家の者たちはみな驚き悲しみ、それからいくらも経たずに、ほとんどが病にかかり亡くなってしまった。
滎陽郡有一家、姓廖、累世為蠱、以此致富。後取新婦、不以此語之。遇家人咸出、唯此婦守舍、忽見屋中有大缸、婦試発之、見有大蛇、婦乃作湯灌殺之。及家人帰、婦具白其事、挙家驚惋。未幾、其家疾疫、死亡略尽。(『搜神記』巻十二より)
これは有名な話だから、知っている方もいるかもですね。蠱(こ。もしくは蠱毒)というのは、多くの虫や蛇などをひとつの容器にいれて、そこで生き残った一匹に霊力がやどるので、それが「蠱」になります。
蠱は、他の家に呪いをかけて富などを奪ってきてくれます(怖)ですが、他の家に呪いをかけるのをやめると、飼っている家の人間を呪って食べます(もっと怖い)
なので、一度飼いはじめてしまったら、ずっとまわりの家に呪いをかけていないと、自分たちが亡んでしまいます……。あと、蠱によってもたらされた富は、蠱がいなくなるとすべて無くなります(めっちゃ怖いし嫌だ)
もはや道教にすら含まれないような、不気味で薄暗い民間信仰の匂いがただよう話ですね……。
顓頊の子
昔、顓頊(せんぎょく)には三人の子がいたが、亡くなって疫病神になった。一人は長江にいて、瘧(マラリア)の神になり、一人は若水(四川省の川)にいて、魍魎鬼(はやり病の神)になり、一人は宮室にいて、子どもを驚かす小鬼になった。なので、歳が変わるときに、方相氏に命じて追儺(ついな)をして疫病神を追い出させる。
昔顓頊氏有三子、死而為疫鬼。一居江水、為瘧鬼。一居若水、為魍魎鬼。一居人宮室、善驚人小児、為小鬼。於是正歳、命方相氏帥肆儺以駆疫鬼。(『搜神記』巻十六より)
これもふしぎな話です。顓頊は、上のほうにのせたリンクでちょっと出てきますが、古い時代の帝王で、北を守る黒帝とされてきました。
そして、「方相氏(ほうそうし)」というのは、四つの目がある黄金の仮面をかぶって、戈をふって悪い鬼を追い出す係です(周の時代には、そういう役職があったとされます。こちらのリンク先にくわしく書いてます)

ですが、このふたつの間にはもともと何もつながりは無かったので、その間を埋めるように小さい伝承が生まれてきた感があります(たとえば、日本でも出雲のほうではスサノオとヤマタノオロチが○○した場所みたいなのがたくさんあります。でも、古事記などにはそういう場所は細かく書いてなかったりします。正式な記録のまわりに、小さい伝承がふえていくといいますか……)
白水素女
謝端は、幼くして父母をなくし、親戚もいなかったので、隣の人に養われて育った。十七~八になり、つつしみ深く、不法なことはしなかった。隣人の家をでて暮らしはじめたが、まだ妻はなく、夜おそくに寝て朝早くおきて、畑仕事などをしていた。
そんなとき、道で大きな螺(巻貝)を拾い、三升の壺(1.2ℓくらい)あったので、これは不思議だとおもって持ち帰り、甕の中で飼っておいた。十日ほどして、謝端は毎日早くから外にでて、帰ると夕食の準備がしてあったので、だれかやってくれているのだと思い、きっと隣人だろうと思った。
何日もこんな感じだったので、隣人にお礼をいいに行くと、「わたしは何もしていません。妻がいて、こっそり作っているのに、私にお礼をいうなんて笑。」といわれてしまった。
謝端はよく分からない気がしたが、その後、朝早く出かけると、すぐに帰ってきて、垣根の外から様子をみていた。すると、ひとりの少女が、甕から出てきて、かまどで火を炊きはじめた。謝端は門から入り、甕のところに行くと、殼があるだけだった。台所までいって「あなたはどこから来て、お米を炊いているのです?」と問うた。
少女は大いにあわてて驚き、甕の中に帰ろうとしたが戻れず、「わたしは天漢(天の川)の中にいる白水素女です。天帝はあなたが若くして一人になって、それでもちゃんと頑張っているのを憐れんで、わたしを使わしてご飯の用意をさせたのです。十年のうちには、きっとあなたは富を得て妻もできたら、そのころ私は帰るつもりでした。ですが姿をみられてしまっては居ることもできません。ですが、今後はすこし暮らしも良くなるでしょう。こちらの殼をおいていくので、そこにお米を入れれば、なくなることはありません。」といった。
謝端は留めようとしたが、そんな時、急に風雨がおこり、たちまち消えるように去ってしまった。そんなこともあって、神座をつくってそれを祀り、暮らすのはいつも十分になったが、大きく富むこともなかった。そして、里の女性を妻にして、後に県令にまでなった。
謝端、少喪父母、無有親属、為鄰人所養。至年十七八、恭謹自守、不履非法。始出居、未有妻、……端夜臥早起、躬耕力作、不捨昼夜。後於邑下得一大螺、如三升壺、以為異物、取以帰、貯甕中。畜之十数日。端毎早至野、還、見其戸中有飯飲湯火、如有人為者、端謂鄰人為之恵也。数日如此、便往謝鄰人。鄰人曰「吾初不為是、……卿已自取婦、密著室中炊爨、而言吾為之炊耶?」端黙然心疑、不知其故。後以鶏鳴出去、平早潜帰、於籬外竊窺其家中。見一少女、従甕中出、至灶下燃火。端便入門、逕至甕所、視螺、但見殼。乃到灶下問之曰「新婦従何所来、而相為炊?」女大惶惑、欲還甕中、不能得去、答曰「我天漢中白水素女也。天帝哀卿少孤、恭慎自守、故使我権相為守舎炊烹。十年之中、使卿居富得婦、自當還去。而卿無故竊相窺掩、吾形已見、不宜復留、當相委去。雖然、爾後自當少差。……留此殼去、以貯米穀、常可不乏。」端請留、終不肯。時天忽風雨、翕然而去。端為立神座、時節祭祀。居常饒足、不致大富耳。於是郷人以女妻之、後仕至令長云。(『搜神後記』巻五より)
これ知っている方もいるかもですが、一応のせてみます。
「天帝」の使いとして、大きい巻貝という組み合わせがすごくいいですよね……。たぶん、天の川の中にすんでいる貝だとおもいます(笑)「白水」は澄んだ水、「素女」はもともと神仙思想で「神女」のことです。
小さいほこらで素女をまつっているというのも、民間のちいさな道教っぽくて、すごく趣きのある話です……。こんな感じで、とおくの方に道教の体系がのぞいているけど、話のメインになっているのはむしろ土着的で、ちょっと泥臭い世界なのが、六朝志怪っぽいなぁ……とおもいます。
かなり長くて、引用が多い記事になってしまいましたが、六朝志怪のいい意味で田舎っぽい感じを楽しんでいただけたら嬉しいです。
お読みいただきありがとうございました。