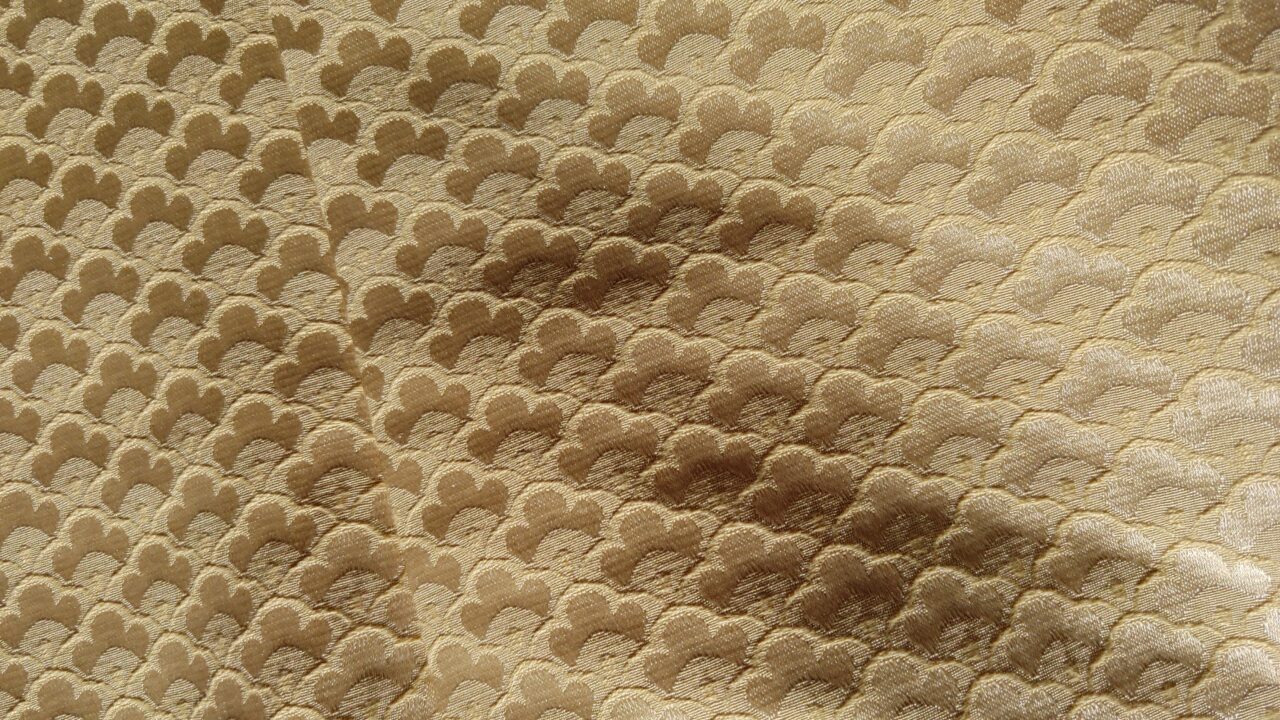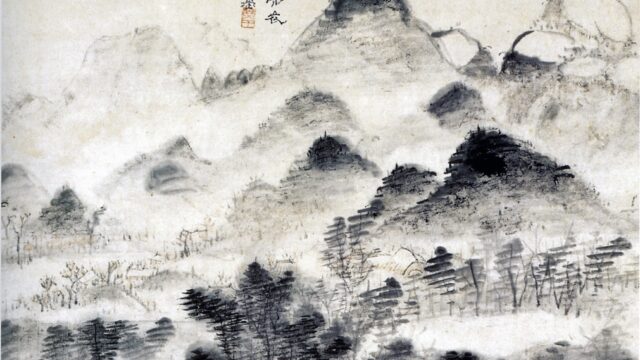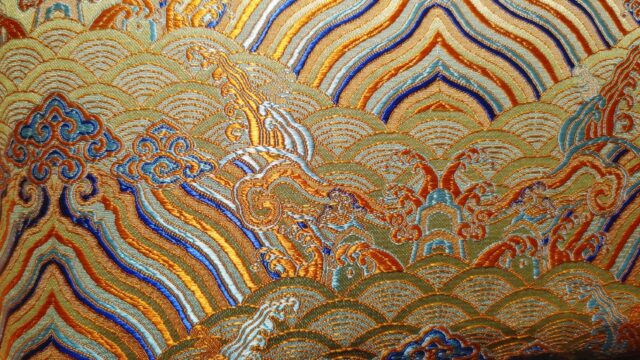「ぬぃの中国文学ノート」にご来訪ありがとうございます。
こちらの記事では、前漢のはじめ頃にいた、とても不思議な文章家 枚乗(ばいじょう)についてかいていきます。
あまり有名ではないですが、枚乗の味わいはわたしがとりわけ好んでいるタイプなので、ぜひ知っていただきたいです。
まず、漢代の賦(楚辞の句形や擬態語多用のスタイルを借りながら、楚の土着文化ではないものを詠むようになったもの)が生まれつつあるけど、まだきれいに完成していないのが前漢の初めくらいです。

そんなとき、枚乗は、楚辞っぽさよりも、戦国時代の弁論術(奇抜で目を引くたとえ話で、王たちを丸めこむ感がある)をメインにしたスタイルをもっていた人になります。
なので、枚乗の作品は、読んでいるとどこか煙に巻かれたような、あやしい議論にのせられてしまったような楽しさがあります(笑)
甘餐の毒薬
このタイトルの意味が謎だと思うので、ぜひこちらを見てみてください(笑)
楚の太子は病があり、呉から来た客がたずねてきた。
呉の客「太子さまはご病気とうかがいましたが、いかがでしょうか?」
太子「疲れているので、客は帰ってくれ。」
呉の客「今は天下安寧にして、四方も平和です。太子さまはまだお若いのに、日夜 歓楽にふけってばかりで、邪気が逆襲してきて、体内は結ばれた筵(むしろ)のように絡まっておりましょう。
紛屯澹淡(ごたごたぼそぼそ)として、寝ても寝られず、精神は洩れ騒いで、百病がつぎつぎ出ております。聡明さもくらくらぼんやりして、喜怒もめちゃくちゃで、このままではきっと大命も傾いていかれるでしょう。
さて、今の貴人の子は、みな宮室の中に寝起きして、飲むもの食べるものはみな温淳甘膬(こってりと甘いもの)、脭醲肥厚(ぽってりと脂っぽいもの)ばかり。衣裳は雑遝曼煖(ぞべらぞべらほこほこ)として、暑くて溶けてしまいそうなほど。これでは金石のような堅いものでも、だらだらと緩んでしまいます。
なので、諺にも「耳目の欲を尽して、身を動かさずにいると、血脈の和を損ない、輿に乗ってばかりだと、蹶痿之機(足が弱るもと)になる」といいます。深い寝室と暗い宮は、寒熱がおかしくなったり、皓歯娥眉(色欲尽くし)は、性を刈り取る斧になりますし、さらに甘脆肥膿(とろとろ甘いもの)は、腸を腐らせる薬になります。
いま、太子さまの肌色はたるんで、手足もだれて、筋骨もゆるみ、血脈も浮かれて、それでも宴会を行き来して、深い宮室のうちに欲のかぎりを楽しんでおられます。これぞ「甘餐の毒薬」というもので、猛獣の牙に戯れていると思うべきでございます。」
楚太子有疾、而呉客往問之、曰「伏聞太子玉體不安、亦少間乎?」太子曰「憊。謹謝客。」客因称曰「今時天下安寧、四宇和平。太子方富於年、意者久耽安楽、日夜無極。邪気襲逆、中若結轖。紛屯澹淡、……臥不得瞑。……精神越渫、百病咸生。聡明眩曜、悅怒不平。久執不廃、大命乃傾。……今夫貴人之子、必宮居而閨処、……飲食則温淳甘膬、脭醲肥厚。衣裳則雑遝曼煖、燂爍熱暑。雖有金石之堅、猶将銷鑠而挺解也。……故曰:縦耳目之欲、恣支體之安者、傷血脈之和。且夫出輿入輦、命曰蹶痿之機。洞房清宮、命曰寒熱之媒。皓歯娥眉、命曰伐性之斧。甘脆肥膿、命曰腐腸之薬。今太子膚色靡曼、四支委随、筋骨挺解、血脈滛濯、……往来游醼、縦恣于曲房隠間之中。此甘餐毒薬、戯猛獣之爪牙也。」(「七發」より)
……このまっとうなことを云っているのに、むしろでろでろと腐っている文章、最高じゃないですか♪
枚乗は、いつもこんな感じで、危なっかしくて毒々しいものほど甘美に描いていきます(笑)そして、甘美な毒薬を首に注入するかのようにして、その恐ろしさを伝えていく――という方法を好みます。
ここでも、邪気が体内で涌きあがってくる様子(邪気が筵のように絡みあっている)だったり、甘いもの・脂っぽいものの食べすぎでべとべとドロドロになった様子を「金属や石すら溶けてしまう」といったり、甘いものは「腸を腐らせる薬」といっています……。
枚乗って、こういう方面だけは語彙がやたらと豊かじゃないですか(笑)そして、「甘餐の毒薬(餐:食事)」というのは、毒薬のごとく恐ろしいものをトロトロに甘美に魅せるという意味で、もはや枚乗の作風そのものです。
龍門の桐
もうひとつ、甘餐の毒薬をどうぞ。こちらは、呉の客は太子にもっと健康的な楽しみを紹介していくところです。
呉の客「龍門(山西省河津市の渓谷の出口)の桐は、高さ百尺にして枝もなく、その幹はごつごつと鬱屈してひねり絡まり、根は扶疏(ぼそぼそ)として分かれており、千仞の峰の上に生えていて、百丈の谷にのぞんでいます。
激しい流れは波を逆立て、また澹淡(どぽどぽ)と深くつづいて、その根は半生半死でございます。冬になれば烈風に雪・あられの降り注ぎ、夏になれば雷のべきべきと鳴り、朝には多くの鳥たちが鳴き、夕方には迷い鳥や旅の鳥がそこに宿を借りるほどで、ほかにも朝の鶴が一匹止まり、悲しげに鳴く鳥がその下を飛びまわります。
そして、秋から冬になっていくときに、その木を切りだして琴をつくれば、その音は、飛ぶ鳥は翼を垂れて飛べなくなり、獣は耳を垂れてうずくまってしまい、これこそ天下の最悲というものでございます。」
呉の客「龍門之桐、高百尺而無枝。中鬱結之輪菌、根扶疏以分離。上有千仞之峰、下臨百丈之谿。湍流溯波、又澹淡之。其根半死半生。冬則烈風漂霰飛雪之所激也、夏則雷霆霹靂之所感也。朝則鸝黃鳱鴠鳴焉、暮則羈雌迷鳥宿焉。独鵠晨號乎其上、鵾雞哀鳴翔乎其下。於是背秋涉冬、使琴摯斫斬以為琴、……飛鳥聞之、翕翼而不能去。野獣聞之、垂耳而不能行、……此亦天下之至悲也。」(「七發」より)
太子にこんな琴の曲を聴いてみたらどうですか……とすすめているのですが、琴の曲そのものよりも、圧倒的に素材の桐についてのほうが長いです。
琴の奏でる悲しげな音は、この桐が吸いこんできた悲しみによっているのです――ということで、桐の危うげで不穏な悲しみのほうがメインになっています。このぞわぞわする毒薬をのぞくような興奮を感じさせて、しかも内容はまっとうなことを云っているというアンバランスさが枚乗の魅力なのです。
弁論術の集大成
枚乗が仕えていたのは、呉王(漢の皇帝の親戚で、長江下流あたりを任されていた皇族)になります。ところが、その呉王は漢に反乱を起こそうとしたので、枚乗はそれを止めさせるための書状を書いたりしています(というわけで、その書状をみてみます)
福が生まれるのは元があり、禍が生まれるにも種があります。その元を入れて、その種を絶てば、禍はどこから来るでしょうか?太山の雨だれは石にも穴をあけますし、井戸の桶の縄は掛かっている木もすり切ります。ですが、水は錐(きり)でもなく、縄はノコギリでもありません――、少しずつの積み重ねがそうするのです。
一銖ずつ数えていると、一石(46000銖のこと)に至るころには必ずズレがあり、一寸ずつ測っていけば、一丈(100寸)になるころに必ずズレてきます。はじめから石や丈で数えていれば、速くて間違いもありません。
あの十人でかかえるような大木も、はじめは小さな蘖(ひこばえ)だったのですから、足で折ってしまったり、手で抜いてしまえるのですが、それも未生のうち、未形のうちだからです。磨礲砥礪(やすりや砥石)は、その削れるのが見えず、いつのまにか無くなっていきます。木や動物を育てるのも、大きくなるのがみえませんが、いつのまにか大きくなります。德を積むのも、その良さは目立ちませんが、いずれ効いてきて、義に背くのもその害はみえずして、いつしか亡んでいくのです。
福生有基、禍生有胎。納其基、絶其胎、禍何自来?太山之霤穿石、殫極之䋁断幹。水非石之鑽、索非木之鋸、漸靡使之然也。夫銖銖而称之、至石必差。寸寸而度之、至丈必過。石称丈量、径而寡失。夫十圍之木、始生而蘖、足可搔而絶、手可擢而抓、據其未生、先其未形。磨礲砥礪、不見其損、有時而尽。種樹畜養、不見其益、有時而大。積德累行、不知其善、有時而用。棄義背理。不知其悪、有時而亡。(「上書諫呉王」より)
この書状のメインの話は「義に背くのもその害はみえずして、いつしか亡んでいきます」だけなのに、それまでのじわじわと害悪が積み重なっていき、その害に気づけないでいる様子のほうがやたらと長くて、しかも多彩でくらくらするほど豊かです。
ちなみに、この部分には原案にしたとおもわれるものがあり、
国のためを思うものは、悪をみれば農夫之が雑草を取るように、芟夷(刈り払って)蘊崇(積み重ねて焼いて)しまい、その根を絶ち、ふえないようにするのです。
為国家者、見悪如農夫之務去草焉、芟夷蘊崇之、絶其本根、勿使能殖。(「左伝」隠公六年)
株をけずり根を掘り出してしまえば、禍と隣り合わせることもなく、禍はなくなるのです。
削株掘根、無與禍鄰、禍乃不存。(「戦国策」秦策一)
のように、災いの根っこを掘り出して切ってしまうことを木や草にたとえることがけっこうあります。ちなみに、ふたつめのほうは「禍」の字もあるので、枚乗の「福が生まれるのは元があり、禍が生まれるにも種があります……」の原案かもです。
そして、小さい木がいつしか大きくなるように、小さい動物がいつしか大きくなるように、小さな雨だれがいつしか石に穴をあけるように、小さな重さや長さのズレがいつしか大きくなるように――のように、より長く豊かな比喩を派生させていくのが枚乗のスタイルです。
もはや本題よりも比喩のほうが多いという、煙につつまれて本心がみえづらいような、不穏であやしい弁論術、というような不思議な文章です。
というわけで、枚乗のすごく独特な味わいを、ちょっとでも楽しんでいただけたら嬉しいです。お読みいただきありがとうございました。