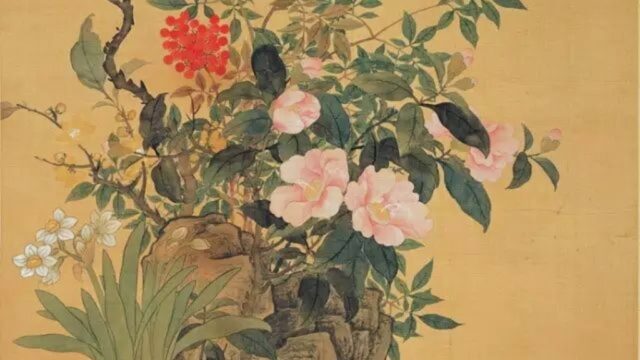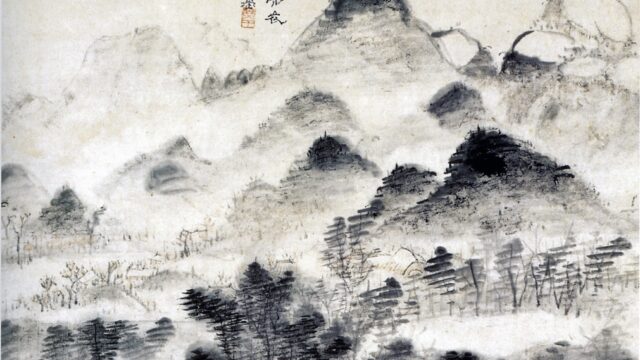「ぬぃの中国文学ノート」にご来訪ありがとうございます。
こちらの記事では、春秋戦国時代にでてきた諸子百家のひとつとして『荘子』についてご紹介してみます。
『荘子』最大の魅力は、なんといってもすごく巧妙で不思議な比喩にあります。そして、話の内容がどれも感動します(笑)わたしは、高校2年のときに『荘子』を読んで衝撃をうけてしまい、それで漢文に興味を持ったという経緯がありますし、大学時代の専門も『荘子』でした。
そんなわけで、ぜひともみなさんにもその魅力を感じていただきたいので、とりわけ気に入っている話を紹介させていただきます(高校のときに訳で全篇読んだのですが、いまだに気に入った話とか覚えていて、そういう記憶って不思議ですね)
水の性
まずは、いかにも『荘子』らしい人間観が出てくるこちらのお話からです。
孔子は呂梁(山西省の渓谷が多い地名)にいったとき、40mほどの瀧があり、四十里先まで泡が流れて、魚や亀も泳げないようなところがあった。
そんな中、一人のひとが泳いでいたので、これはきっと苦しみから自殺したに違いないと思い、弟子に下流のほうから助けさせようとした。ところが、数百步ほどいくと、その人は上がってきて、髪を濡らして歌いながら池のそばを歩いていた。
孔子はこの人に「私がさっきみたときは、あなたは妖鬼かと思いましたが、どうやら人間らしいです。あのように泳ぐのは何かやり方があるのですか?」
その人は「とくにないですね。私は故(もともとの条件)をもって生まれて、性(私の中の性質)を育てて、命(天命)にまかせて生きているのです。吸いこむ流れとともに沈み、涌き上がる流れとともに浮けば、水の道に従っていて余計な力が入りません。こんなふうにしているだけです」
孔子は「その“故(もともとの条件)・性(自分の中の性質)・命(天命)”というのは何ですか」ときいたので、その人は「私は陸に生まれたことは故(もともとの条件)です。水に慣れ親しんで育ったのは、性(私の中の性質)です。それによって何故かできるようになったのは、命(天命)という感じです。」
孔子観於呂梁、縣水三十仞、流沫四十里、黿鼉魚龞之所不能游也。見一丈夫游之、以為有苦而欲死也、使弟子並流而拯之。数百步而出、被髮行歌而游於塘下。孔子従而問焉、曰「吾以子為鬼、察子則人也。請問蹈水有道乎?」曰「亡、吾無道。吾始乎故、長乎性、成乎命。與斉俱入、與汩偕出、従水之道而不為私焉。此吾所以蹈之也。」孔子曰「何謂始乎故、長乎性、成乎命?」曰「吾生於陵而安於陵、故也。長於水而安於水、性也。不知吾所以然而然、命也。」(達生篇より)
なんていうか、どこまでも荒唐無稽で、それでいて面白くないですか(笑)
『荘子』はよく『老子』とセットにされることが多いですが、老子はけっこう技芸否定の思想が入っています。
五つの色は人の目を悪くさせ、五つの音は人の耳を悪くし、五つの味は人の口を狂わせる。(12章:五色令人目盲、五音令人耳聾、五味令人口爽。)
民が良いものをたくさん持つようになると、国はいよいよ乱れる。人が技巧を多くもつと、奇物がいよいよ出てくる。それを取り締まる法令が多くなると、盗賊はいよいよ出てくる。だから聖人は「私は何もしないことを民に示せば、民も穏やかになり、わたしが静かさを好めば、民もしぜんと正しくなる」と云う。(57章:民多利器、国家滋昏。人多伎巧、奇物滋起。法令滋彰、盗賊多有。故聖人云「我無為、而民自化。我好静、而民自正。」)
老子は素朴主義・無味主義みたいなところがありますが、一方で荘子は“技芸は人の生まれもった心から派生してくるものなので、自然なものなのだ”という思想があります。
さっきの例でいうと、滝つぼで泳いでいた人は、水のちかくで生まれ育ったので、小さい頃から水になれていて、自然のままに生きることは泳ぐのが上手くなることだった、みたいな感じです。
そして、荘子は技芸を肯定していますが、それはかならず流れて止まないこの世の変化の一隅のようなものであるべきで、末端的な技に縛られるべきではない――としています。
洞庭の鐘
というわけで、荘子の技芸観がよく出ている一節をみてみます。
北門成(人名)は黄帝に「あなたが洞庭湖で奏でた音楽は、始めのほうは恐ろしい感じがして、しばらくするとぼんやりしてきて、そのうち訳がわからなくなって、蕩々黙々(ぼやぼやもごもご)としてきました。」
黄帝は「そのとおりだろうなぁ。私は奏するときに天理にしたがって、五德をまぜ、自然に応じさせて、さらに四季を入れ、万物を溶かしたのだ。四季はつぎつぎ入れかわり、万物もめぐり、一盛一衰して、激しくなり穏やかになり、一清一濁して、陰陽も調和していたのだ。一死一生して、滅んだと思えば始まり、そのきわまり無い様子は何ひとつ予想できなくて、あなたは不気味に感じたのだ。
さらに私は、その声を短くしたり長くしたり、強くしたり柔らかくしたり、変化して止まらないようにしたので、それを見ようとしても見えず、これを追いかけても追いつけず、儻然(ぼんやり)として暗い道に立っているようで、目は見届けられず、足も追いつかず、ふらふらとしてしまったので、ぼんやりしていたのだろう。
わたしはさらにごちゃごちゃと入り乱れて、林のようにたくさん出てきて、形のないところから出てきたようで、ずっと暗闇にいるような音にしたが、あるときは死して、あるときは生まれ、あるときは実り、あるときは咲き、流れて散って、声が留まらないようにした。世の人はこれを聖人の姿にたとえるが、聖人とは“情に通じて天命を生きること”なのだ。だから、それを讃えて「聴いても聞こえず、みても見えず、天地にあふれて、六極(上下四方)をつつんでいる」というが、あなたも何を聞いているのかわからなくなって、訳がわからなくなったのだろう。」
北門成問於黄帝曰「帝張咸池之楽於洞庭之野、吾始聞之懼、復聞之怠、卒聞之而惑、蕩蕩黙黙、乃不自得。」
帝曰「女殆其然哉。吾奏之……順之以天理、行之以五德、応之以自然、然後調理四時、太和萬物。四時迭起、萬物循生、一盛一衰、文武倫経、一清一濁、陰陽調和、……一死一生、一僨一起、所常無窮、而一不可待。女故懼也。
吾又奏之……其声能短能長、能柔能剛、変化斉一、不主故常、……望之而不能見也、逐之而不能及也、儻然立於四虚之道、……目知窮乎所欲見、力屈乎所欲逐、……乃至委蛇。汝委蛇、故怠。
吾又奏之……混逐叢生、林楽而無形、……動於無方、居於窈冥、或謂之死、或謂之生、或謂之実、或謂之栄、行流散徙、不主常声。世疑之、稽於聖人。聖也者、達於情而遂於命也。……頌曰『聴之不聞其声、視之不見其形、充満天地、苞裏六極。』汝欲聴之而無接焉、而故惑也。(天運篇より)
ちょっと長いですね……(これでもかなり削ったのですが)。
まず、すごく面白いのが、老子とおなじく「聴いても聞こえず、みても見えず……」と出てくるのですが、こちらの荘子ではその後に「天地にあふれて、上下四方をつつんでいる」のが、一定の形のない不思議な音楽なのだ、という感性になります。
なので、天地四方をつつむように、その中には林のようにたくさんの音がごちゃごちゃと生えていて、清濁陰陽ぐちゃぐちゃにまざりあって、花が咲いたり、実がなったり、芽が出たり、枯れていったり――という音が入っているのが聖人に似ている音楽になります。
逆に老子では、無音主義とでもいう感じで、余計な音がしないのが穏やかな世界なのだ、というのが聖人の考えになります。
ただ、荘子はただ技巧を極めればいいかというと、それらの技巧はかならず四季や自然の移り変わりに似たようなものであるべき(その変化こそが不思議さをつくっているのだから)という面もあります。
さらに、聖人とは「達於情而遂於命(情に深く通じて、天命のままに生きていく)」ような人――としています。漢文で「情」は感情・心情だけでなく、物事の様子などもあらわすので、そのような自然の変化を感じ取って、天命(なぜそうなっているのか分からないまま生きていくこと)を遂げていくのが、『荘子』の聖人になります(もちろん人の心情もその変化に含まれます)
天籟問答
というわけで、最後にいままでの話をまとめるような部分をのせておきます。この中にでてくる「籟(らい)」は笛の音みたいな意味です。
南郭子綦(なんかくしき。人名)は机にもたれて座り、天を仰いで息をつき、顏成子游(がんせいしゆう。子綦の弟子の名)はその前に立っていた。
子綦は「子游よ、お前は人籟(人の音)を聞いたことはあるだろうが地籟(地の音)はまだ聞いたことがないだろうか、もしくは地籟(地の音)は聞いたことがあっても、天籟(天の音)は聞いたことがないだろう。」
子游は「どういうことでしょうか」といった。
子綦は「大塊(大地)が息を吐き出すと、それが風になる。その風が吹けば、かならず地上のさまざまな穴が鳴き叫ぶことになる。その翏々(びゅうびゅう)という音を聞いたことがあるだろう?山林のざわざわとゆれて、大木の百人で抱えるほどの大きさのものにある穴が、あるものは鼻に似て、もしくは口に似て、耳に似て、四角い木組みに似て、円い杯に似て、臼に似て、沼に似て、くぼみに似て、激しい音、矢のような音、吼える音、吸う音、叫ぶ音、泣く音、深い音、哀しむ音などが聞こえ、前者がうぅと鳴けば後者がごぉと答え、冷ややかな風が小さくつづいて、速い風が大きく鳴り、はげしい風が過ぎてしまうと穴はみな静かになる。それでいて、さらさらからからという風の音はするだろう?」
子游は「地籟(地の音)は風に鳴る穴で、人籟(人の音)は笛などですね。だとしたら天籟(天の音)とは何でしょうか。」
子綦は「その風の音はさまざまだが、それらを穴の形によってさまざまに鳴らしていることが「天の音」なのだ。」
南郭子綦隠几而坐、仰天而嘘、……顏成子游立侍乎前、……子綦曰「偃、……女聞人籟而未聞地籟、女聞地籟而未聞天籟夫。」子游曰「敢問其方。」子綦曰「夫大塊噫気、其名為風。是唯無作、作則萬竅怒呺。而獨不聞之翏翏乎?山林之畏佳、大木百圍之竅穴、似鼻、似口、似耳、似枅、似圈、似臼、似洼者、似汚者、激者、謞者、叱者、吸者、叫者、譹者、宎者、咬者、前者唱于而随者唱喁。泠風則小和、飄風則大和、厲風済則衆竅為虚。而独不見之調調、之刁刁乎?」子游曰「地籟則衆竅是已、人籟則比竹是已。敢問天籟。」子綦曰「夫吹萬不同、而使其自已也、咸其自取、怒者其誰邪。」(斉物論篇より)
これ、すごく良くないですか(高校のときに、荘子の魅力に呑み込まれたのは、この一節がきっかけです)
まず、風の描写がとてつもなく美しいです。ごつごつした木の凹みがさまざまな形になっていて、そこに風が入り込んでいくところもきれいですし、「天の音(天籟)」とは「地籟」「人籟」の複雑で多彩なことそのものが「天」なのだ、という話も素敵です。
さっきの黄帝の話でも、四季や自然のうつりかわりのような多彩さこそが、聖人のような音楽――とされていますが、ここでも地上に鳴るさまざまな音こそが「天の音楽」というふうにされます。
そして、最初の滝の話になりますが、そのような多彩な性質がそのまま生きていくことが「天命(どうしてそうなったのか分からないまま、生きていくこと)」……ということになります。
なので、荘子の世界では、人間は大木の穴に鳴る風のように、それぞれ違った形で、雑多な変化の中のひとつの音のように生きていくものだ――という人間観になっています。
まぁ、これだけで『荘子』をすべて紹介できたわけではないですが、だいたい私なりに重要そうなところは書いたつもりです。
(すごく細かい話をすると、荘子では「聖人」は「至人(真理にたどり着いた人)」みたいにいうことが多いです。あと、荘子は一人のひとが書いたものではないので、けっこう雑多なものが入ってます。ここで紹介した話は、その中でも本質的な部分です)
というわけで、かなり長くなってしまいましたが、荘子の変幻自在で渾沌とした川のような魅力を少しでも感じていただけたら嬉しいです。
お読みいただきありがとうございました。