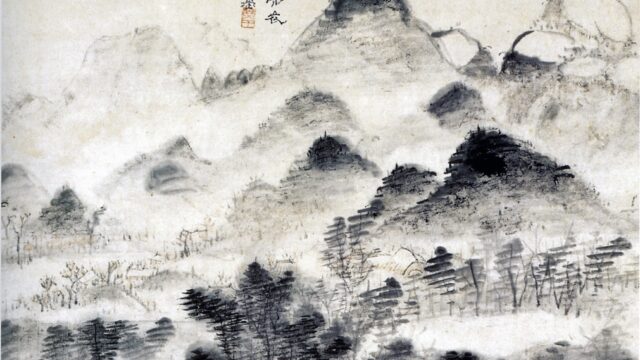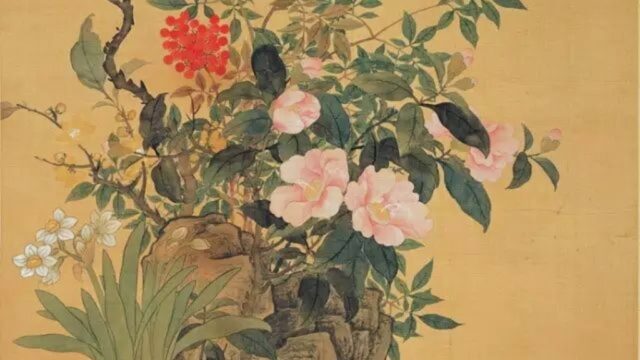「ぬぃの中国文学ノート」にご来訪ありがとうございます。
こちらの記事では、中国で最初の文学とされている「詩経」についてかいていきます。
詩経は、まぁ正直いってしまうとかなり読みづらい作品が多いので、その魅力をなるべくわかりやすく伝えるのは、かなりむずかしいのです(笑)
まず、すごくざっくりいってしまうと、詩経は「国風」「小雅」「大雅・頌」の三つにわかれています。
国風は、周の時代のさまざまな国の民謡のことです。それぞれの国の風俗――みたいなイメージです。
小雅(しょうが)は、やや現実世界への憂いなどを唄ったような作品が多いイメージです。まぁ、現実世界のいいことを書いているときもあるのですが、いずれもけっこう真面目な雰囲気のものが多いとおもっています。
大雅(たいが)・頌(しょう)は、どちらも王家のことを讃えるような作品が多いです。王家の歴史の一幕をえがいていたり、有名な王のことをまとめた詩、というふうに思っていれば近いかとおもいます。
というわけで、国風からそれぞれわたしが好きなものをのせてみます。
国風 淫風溺々
国風の魅力は、まずなんといってもその民俗の素朴さです。
こちらは、葦の茂る水辺の神を祀るために、ちいさい舟を出して、水の上にいる人が詠んだ詩なのですが、詩経のなかでもとりわけ美しい一篇とされています。
葦の葉の蒼々(さらさら)として、白い露は霜になる頃、その人は、水の一方にあり。
溯洄(さかのぼ)って会いにいけば、道は険しくて長く、流れにのって会いにいけば、その水の中央にあり。
葦の葉の萋々(ひらひら)として、白露はまだ乾かず。その人は、水の湄(ほとり)にあり。
溯洄(さかのぼ)って会いにいけば、道はけわしくて躋(折れ曲が)り、流れにのって会いにいけば、その水の中州にあり。
葦の葉の采々(さやさや)として、白露はまだ消えず。その人は、水の岸にあり。
溯洄(さかのぼ)りて会いにいけば、道はけわしくて右に曲がり、流れにのって会いにいけば、その水の中沚(小島)にあり。
蒹葭蒼蒼、白露為霜。所謂伊人、在水一方。
溯洄従之、道阻且長。溯游従之、宛在水中央。
蒹葭萋萋、白露未晞。所謂伊人、在水之湄。
溯洄従之、道阻且躋。溯游従之、宛在水中坻。
蒹葭采采、白露未已。所謂伊人、在水之涘。
溯洄従之、道阻且右。溯游従之、宛在水中沚。(秦風・蒹葭)
国風は、こういう繰り返しの詩が多いです。この葦しかない水辺にふわふわとただよう謎の神って、いかにも古代的な素朴さと不思議さにあふれていませんか。
これがつくられたのは、西のほうにある秦の国なのですが、けわしい地形の中にいきなり大きい水辺があって、そこをわたる心細さとあやしげな風俗がたくさん残っている感じがきれいですよね。
あと、同じ形を繰り返しながら、歌詞をすこしずつ変えて単調にならないようにして、水辺の様子が少しずつみえるようになっているところなどもすごく魅力的です。
小雅 まじめな小市民
というわけで、今度は小雅です。(「庭燎」は、宮中の庭におかれた灯かりのことです)
夜は如何(いか)ほど、夜はまだ明けず、庭燎(ひわび)の光。君子の来たりて、鈴の音は将々(しゃんしゃん)。
夜は如何ほど、夜はまだ尽きず、庭燎は晣々(ちらちら)。君子の来たりて、鈴の音は噦々(さらさら)。
夜は如何ほど、夜は明けていき、庭燎は煇々(きらきら)。君子は来たりて、その旂(はた)を観る。
夜如何其、夜未央、庭燎之光。君子至止、鸞声将将。
夜如何其、夜未艾、庭燎晣晣。君子至止、鸞声噦噦。
夜如何其、夜郷晨、庭燎有煇。君子至止、言観其旂。(小雅・庭燎)
これは、周の王宮に、さまざまな諸侯たちが夜明け前に参内していく様子をえがいたものです。夜明け前の宮中で、しずかに燃えている大きな灯かりと、遠くから聞こえる鈴の音(車につけられている鈴)のやや冷たい響きがすごく惹かれます。
朝早くから宮中にきて、政務に励むことをかいていて、かなり真面目な作品ではありますが、その情趣はすごく独特で、きれいなひとときを切り取ったような作品です。あと、詩の形もきれいです。
大雅・頌 重厚なる王朝
最後は、王家のことをかいた大雅・頌から、ひとつみてみます。
もっとも、このシリーズはかなりの長篇が多いので、魯頌の中から「閟宮(ひつきゅう)」という作品の一部をのせてみます。
泰山の巌々(ごつごつ)として、魯の国の仰ぎみる山。亀山・蒙山を覆い隠し、大きく東にのびていく。海まで至れば、淮水の民もやって来て、みな魯に従うのも、魯公の功なり。
……徂来山の松、新甫山の柏。これらを切って整え、一尋(ひとひろ)一尺(いっしゃく)。松の軒木は大きく垂れて、霊廟は孔碩(がらりと広く)、新しくて奕々(きらきら)として、これは奚斯(人名)がつくったもの。大きく曼(のびてひろが)り、萬民の喜び従うところ。
泰山巌巌、魯邦所詹。奄有亀蒙、遂荒大東。至于海邦、淮夷来同。莫不率従、魯侯之功。
……徂来之松、新甫之柏。是断是度、是尋是尺。松桷有舄、路寝孔碩。新廟奕奕、奚斯所作。孔曼且碩、萬民是若。(魯頌・閟宮)
閟は、秘密の「秘」と同じなので、ひっそりと閉ざしてしずかな祖先をまつるお堂のことです(中国では「廟(びょう)」といいます)。
徂来山・新甫山などの山々(いずれも魯にあります)から切り出してきた木で、魯の祖先をまつる廟をつくったことを詩にしているのですが、さきほどの国風・小雅などとくらべて、かなり複雑で長い作品になっているのがわかります(これでも全体の一部です)
そして、出てくる風景などもかなり複雑で多彩になっていて、魯の山々が大きく延びていく様子などは、それだけ魯の国が大きくて力にあふれている比喩みたいになっています。
ちなみに、魯はいまの山東省あたりの国で、周の王家の分家です。淮水のあたりには、周王朝から外れている人々もたくさんいたのですが、魯の盛んなことをみて慕ってやってくる……というあたりも、かなり格式高いというか、より公的な感じの作品になっています。
ちなみに、ちょっと余談をかいておくと、のちの時代から詩経は“文学の祖”とみなされていくのですが、「風雅」といったときは「古典的な文章」、「雅頌」といったときには「格調高くきちんとした文章」みたいなイメージがあります。
というわけで、すごくざっくりではありますが、詩経の中からわたしの好きな作品をいくつか紹介させていただきました。
これ以外にもいろいろなものはあるのですが、素朴で純粋な古代ふうの世界を感じていただけるきっかけになっていたら嬉しいです(中国の人にとっても、詩経はあまりに素朴すぎてわかりづらい……と思われていたらしく、メインの文学の祖は、すこし後にあらわれた「楚辞」だったりするのですが……。)
そんなわけで、お読みいただきありがとうございました。